生成AI時代における組織内ナレッジ共有ソリューションの最前線
|
|

2024年5月22日に、株式会社アシスト・株式会社アイアクト共催のオンラインセミナー
「これで決定!ナレッジ共有の最新トレンドと生成AI活用方法」を開催しました。
ビジネスにおけるナレッジ共有の重要性が叫ばれるようになって久しく、これまでも数多くの企業が社内ポータルやナレッジベースなどを使った情報共有に取り組んできました。ここへ来て動画や生成AIといった新たな技術・メディアを取り入れることで、これまでにない高いレベルのナレッジ共有が実現できるようになっています。
アシストではいち早く最新のナレッジ共有ソリューションを自社内に導入し、大きな効果を上げるとともに、その成果を数多くのお客様にフィードバックしてきました。本セミナーでは弊社の取り組み内容を紹介するとともに、パートナー企業のアイアクトが提供する生成AIソリューションのご紹介も行いました。
HeadLine
ビジネスのアジリティを獲得するための基盤
「Internet of Knowledge」
本セミナーの冒頭には、アシスト DX技術推進本部 ナレッジプラットフォーム技術部 八木康介が登壇し、「知識の力を組織全体へ
生成AIや動画、ポータルを活用したナレッジ共有戦略」と題して、アシストがこれまで取り組んできたナレッジ共有の施策について紹介を行いました。
アシストでは現在、With/Afterコロナ時代における「コミュニケーション分断」の課題を克服したり、デジタル技術を活用した生産性向上をさらに推し進めるために、「 Internet of Knowledge 」という概念を掲げて様々な施策を展開しています。

企業がビジネスアジリティを獲得するには、「察知力」「意思決定力」「実行力」の3つの能力を高める必要があると言われています。またそのための具体的な取り組みとして、「知恵」「知識」「情報」「データ」を組織内で絶えず循環させ、組織知を強化することで変化を素早く察知して正しい意思決定を行うことが求められます。
アシストが提唱するInternet of Knowledgeは、まさにこの循環を支えるための基盤を提供し、企業におけるナレッジ共有を促進することでビジネスアジリティの向上を企図したものです。
CMS製品「NOREN」を導入して社内ポータルの運用プロセスを改善
ここ数年の間で、コロナ禍に伴うテレワークの急速な普及などを背景に、企業において求められるナレッジ共有の形は大きく様変わりしました。かつてのような組織単位での働き方を前提とした「組織内に閉じた情報共有」から、現在では組織や場所の壁を超えたプロジェクト型の働き方に適した「組織を超えた情報共有」が求められるようになってきました。
そのためにアシストでは、組織の壁を超えてあらゆる個人やチームが社内共通の「仮想的なナレッジベース」にナレッジを蓄積し、その内容を全社員が効率的に参照できる世界観を提唱しています。そしてこれを具現化するための製品・サービスとして、ガイダンス・プラットフォーム製品「 テックタッチ 」、コンテンツ管理基盤「 NOREN 」、エンタープライズ動画管理基盤「 Panopto(パノプト) 」、インサイトエンジン「 Glean 」を提供しています。
|
|
コンテンツ管理基盤NORENに関しては、2012年に真っ先に自社で導入しました。そして社内で運用する中でその有効性を確認できたことから、現在ではお客様にも提供しています。かつてアシストでは、部門ごとに独自に社内向けイントラサイトを公開していたのですが、サイトのレイアウトや操作性が統一されていなかったり、掲載されている情報の正確性が担保されていなかったりと、様々な課題を抱えていました。
そこで以前からCMS製品として定評のあったNORENを導入し、社内の全てのイントラサイトのコンテンツ制作・承認フローや公開スケジュール管理などのプロセスをNOREN上に集約したことで、全てのイントラサイトでデザインや操作性が統一され、社員が欲しい情報に短時間でたどり着けるようになりました。またコンテンツのアクセス権限や承認フローをNOREN上で集中管理できるようになったことで、コンテンツの質も大幅に向上しました。
現在ではこうした自社運用のノウハウを生かして、数多くのお客様にNORENを使ったナレッジ共有ソリューションを提供しており、例えば積水化学工業様や三菱重工業様といった大手企業が実際にNORENを使って社内向けイントラサイトやポータルサイトを運用している実績があります。
|
|
動画管理基盤「Panopto」で動画を通じたナレッジ共有を促進
エンタープライズ動画管理基盤Panoptoも2020年から社内で活用しており、既に大きな成果を上げています。Panoptoは「動画を、企業内の“当たり前”に」をコンセプトに開発された企業向け動画プラットフォームで、いわば「社内版YouTube」として従業員が気軽に動画を制作・公開して、それを組織内で広く共有できるというものです。

こうした動画のメリットを手軽に享受できるよう、Panoptoは特別な機材やアプリケーションを使わずともブラウザだけですぐに動画を撮影・公開でき、またコンテンツの数も「作り放題」「見放題」で特に制約は設けられていません。さらには動画視聴の統計データから「バズった」動画の傾向を分析したり、公開された動画に視聴者がコメントを付けることで双方向コミュニケーションを促すなどして、動画を通じたナレッジ共有を活性化するための様々な仕組みが備わっています。
ちなみにアシストでは既に社内で4万本弱もの動画が登録されており、総視聴時間も約172万時間に達するなど、今やなくてはならないナレッジ共有プラットフォームとして日々多くの社員が利用しています。
|
|
生成AIを使って社内のナレッジ共有をさらに加速させる「Glean」
2023年からは、新たにインサイトエンジン「Glean」の社内活用も始めています。Gleanは企業内利用を前提に最適化された検索エンジンと生成AIの機能を提供するサービスで、いわば「社内版Google」「社内版ChatGPT」とでも位置付けられる製品です。

Gleanはこうした課題を解決するために開発されたサービスで、社内で運用している業務システムはもちろんのこと、TeamsやSlack、Salesforce、Google DriveといったSaaSアプリケーションで管理されている自社データも含めて横断的に情報を検索できます。
なおGleanが備える生成AI連携機能を使い、ChatGPTと同様にユーザーがプロンプトを投げ込むと、自動的にその回答文を返してくれます。使い勝手はChatGPTとかなり似ていますが、回答の内容は検索でヒットした社内情報を基に作成するため、一般公開されている生成AIでは難しい「社内固有の情報に基づいた回答」が得られます。

|
|
AI検索とRAGを組み合わせて高い回答精度を達成した
「Cogmo Enterprise 生成AI」
続いてアシストのパートナー企業である株式会社アイアクトの取締役 CTO、西原中也氏が登壇し、同社が提供するナレッジ共有ソリューションの紹介を行いました。
アイアクトは元々Webサイト制作を主に手掛けるベンダーでしたが、2016年からIBM Watsonを用いたAIソリューションの提供を始め、これまで数多くの実績を積み上げてきました。特に企業・組織内に散在している大量かつ雑多なドキュメントの中から、ユーザーが求めるものをAI技術を駆使して高精度で探し出せるAI検索サービス「Cogmo Search」は、多くのユーザーを獲得してきました。
現在ではこれにさらにChatGPTの技術を組み合わせ、ユーザーの質問に対して高い精度の回答文を提示できる「Cogmo Enterprise 生成AI」の提供も始めており、早くも様々な業界で導入が進んでいます。この製品を開発する上で重要なキーファクターとなったのは、「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」と呼ばれる生成AI技術でした。
一般的なChatGPTの使い方は、インターネット上に公開されている様々なデータを学習して構築されたChatGPTエンジンに対して、OpenAI社が提供するインターフェースやAPIを通じてプロンプトを投げかけて回答を得るというものです。この方式では、一般的な質問に対しては高精度な回答を生成できるものの、インターネットに公開されていないクローズドな情報はあらかじめ学習することができず、よって社内情報に関する質問には正確に答えることができません。
そこでRAGでは、ChatGPTに対して質問する際に、質問内容に関連する社内資料などのドキュメントをあらかじめ送付した上で「これらの情報を基に回答を生成してください」とプロンプトを投げかけます。これを受けたChatGPTは渡されたドキュメントの内容を解釈して、それを基に適切と思われる回答を生成します。
この方式において回答の精度を担保するためには、「ChatGPTにあらかじめ手渡すドキュメントの選定」が重要になってくると西原氏は指摘します。

|
|
プロンプト技術を使わずとも生成AIのメリットを享受
「Cogmo Enterprise 生成AI」の画面でユーザーが質問を入力すると、まずCogmo Searchが社内に存在する様々なドキュメントを検索し、その結果を関連性が高いと思われるものから順番に提示します。それと同時に、検索結果上位の幾つかのドキュメントをChatGPTに送付し、これらの内容を基にユーザーの質問に回答するよう依頼します。そしてChatGPTから回答文が返ってきたら、その内容を同じ画面上に表示します。
こうした仕組みを企業のイントラサイトやポータルサイトを通じて社内に公開することで、これまで社内に蓄積されてきた膨大な量の情報の中から欲しいものを瞬時に探し出し、かつその内容を分かりやすく要約して参照できるようになります。既に多くの企業において、社内規定に関する従業員からの質問に自動的に回答するチャットボットや、業務上の必要に応じて過去の資料や顧客対応履歴などを素早く検索、要約して活用する仕組みなどに活用しています。
さらには江戸川区が住民向けの情報検索サービスに「Cogmo Enterprise 生成AI」を導入するなど、組織内での利用に限らず外部向けのサービスにも適用する例が増えてきています。

|
|
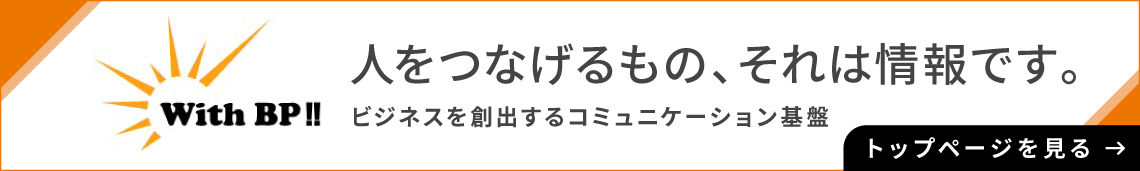
|
|

