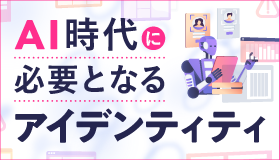- ID管理
iDoperation V2とWindows Server 2016のWサポート終了に備える!移行の勘所
iDoperation V2のサポート終了を目前に控えたユーザーの方向けに、スムーズな移行のポイントをまとめました。
|
|
みなさんこんにちは。長谷川まりです。
近年、従来から潜在的に存在していたID周りの課題が顕在化していることをよく伺います。今回はなぜ、多くの企業がID周りの課題に追われてしまうのか、その背景を紐解きながら、課題解決の捉え方を「ちょっと前向きに」お伝えしたいと思います。
まず、企業を取り巻くビジネス環境とIDの関係について、3つ、整理してみましょう。
今のビジネス環境を示す、VUCA(ブーカ)という言葉をご存じでしょうか。2016年のダボス会議(世界経済フォーラム)で使われた表現で、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)を表す4つの単語の頭文字を取っています。社会環境が複雑性を増し、将来の予測が困難な状況でも、企業は変化へのスピーディな対応が求められているという状況を説明していますが、多くの共感が得られているのか、この表現はビジネスシーンでよく使われるようになっていると思います。
まさにVUCAの環境において、人の管理に対する考え方が変わってきました。柔軟性や創造性の向上、意思決定の迅速化、コミュニケーションといった課題をクリアするために、人の管理も従来の組織型から、いわゆるプロジェクト型へとシフトしつつあると思います。これまで組織という枠組みの編成そのものが変更したり、人が組織から組織へ異動する、というほぼ定期イベントとして捉えられていたのが、その人のスキルやジョブアサインなど役割に応じ、柔軟でダイナミックなプロジェクト型に組み替えられるよう変化していて、人とシステムを紐づけるIDの管理も、手作業の運用からより効率的な運用の見直しが迫られるようになりました。
|
|
また、各企業で既に進んでいるクラウドの活用という観点で、セキュリティに関する考え方もアップデートされていると思います。最新のテクノロジーやサービスをスピーディに採り入れる目的で、クラウドの活用が積極的に行われていると思いますが、社内外を問わない連携など、その活用範囲も広がっています。目的を果たす一方、ゼロトラストに代表されるように、環境変化に合わせたセキュリティの見直しが問われるようになりました。
実際に、クラウドセキュリティアライアンス(CSA)によるクラウドの11の重大脅威「パンデミックイレブン」を示した資料によると、システムの入口部分のリスクに関する点が上位に来ていることがわかります。コロナ禍以前の2019年には、認証に関する内容は4位でしたので、近年、認証部分の脅威への対応は、より重要性が増してきていると感じます。
3つ目は、データドリブンの考え方です。データドリブンとは、直感や経験だけでなく収集されたデータ分析により、意思決定や行動のための洞察を得ることですが、これには精度の高さや客観性が求められます。扱うデータの量も増えているため、膨大なデータ漏洩のリスク管理とともに、データにアクセスするのは「誰が」「どんな権限」で「何に」アクセス可能なのか、いわゆるアクセス管理を慎重に行うことが必要となっています。
アクセス管理というと、従来はセキュリティの観点から、守りの側面が強かったと思いますが、データドリブンでは、必要なタイミングで必要なデータにすぐさまアクセスできる、いわゆる「攻め」のアクセス管理が課題となってきます。攻めと守りのバランスをどう決めていくか、その戦略が新たに問われていると思います。
|
|
以上のように、ビジネスという大局的な捉え方で、ITシステム利用のためのIDが果たす役割はとても大きくなっています。セキュリティ対策はゼロトラストの考え方を採り入れる企業が増えていますが、アメリカのCISAが提唱するゼロトラスト成熟度のモデルでも、まずはIDの整備が前提とされています。システムを利用する際には必ずIDが必要となるという大原則に立ち返ると、ネットワークの境界ではなく、IDや認証を境界とし、さらには「基盤」として捉えると、セキュリティ対策の機能は、大きな底上げが期待できそうではないでしょうか。
|
|
もう少し、IDの管理がIT活用の基盤として機能すると、どんなメリットがありそうかを考えてみましょう。クラウドを代表するスピード感やデータドリブンといった他、お店やECサイト、アプリ上など顧客とのあらゆる接点(チャネル)をつなげる役割として、ビジネス推進が期待できそうです。また、IDを効率的に管理することで、管理者にとっても利用者にとっても、ストレスを減らし生産性の向上が期待できます。そして、セキュリティ対策はIDが正しく管理されていることを前提と考えると、ゼロトラストの採用やさらにはシステム間の連携面でも安心、安全なアクセスにつながり、セキュリティガバナンスが強化されていきます。このようにIDの課題を解決することはメリットがいっぱいです。1つ1つの課題解決を果たしていくことで、ビジネスを支える大きな基盤として機能する、という捉え方を、ぜひお伝えできたらと思っています。
ビジネス推進:
生産性の向上:
セキュリティガバナンス強化:
VUCAの背景から起こる組織の流動性の変化、クラウド活用といったシステム環境の変化、そして意思決定にデータを活用するデータドリブンといった課題に直面する今、情報アクセスの基礎情報となるIDの管理が問われています。これをいかに無理や無駄なく管理できるかを基盤として捉えると、ビジネス面でのメリットが大きく期待できることがわかります。ITシステムを安心、安全、そして効率的に利用するために、ID周りの課題については、ぜひアシストにご相談ください。
|
|
IDを分類し、それぞれどのような課題があるのか、解決策とソリューションがわかる資料です。全体像を通じて、長期的な対策の計画を、未来像としてイメージができます。是非ご活用ください! |
長谷川 まり
|
|

iDoperation V2のサポート終了を目前に控えたユーザーの方向けに、スムーズな移行のポイントをまとめました。
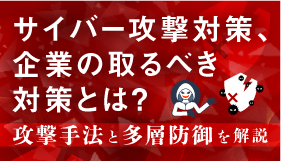
最新のサイバー攻撃手法から、企業の取るべき対策までをご紹介します。サイバー攻撃によるデータの奪取や暗号化などのリスクを下げるために、有効な対策を複数実施し、防御層を重ねる「多層防御」について解説します。