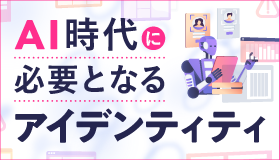- ID管理
iDoperation V2とWindows Server 2016のWサポート終了に備える!移行の勘所
iDoperation V2のサポート終了を目前に控えたユーザーの方向けに、スムーズな移行のポイントをまとめました。
|
|
みなさんこんにちは。長谷川まりです。
AWS、Azure、Googleなど、クラウドインフラを利用する企業が増えています。そこで今回はクラウドサービスの中でも34%ものシェアを占める(※)AWSに注目し、安心してAWSを運用する秘策「特権ID管理」を、わかりやすく図を使って解説します!
皆様ご存知のとおり、IAMユーザーはAWSの管理コンソールを利用して日々の運用を担うユーザーです。ではIAMユーザーが複数いるとしたら、ログインIDはどんな単位で作るべきでしょう?個人毎?それとも組織や役割単位でグループ毎に共有IDを作る?IAMユーザーIDの管理は、AWSのセキュアな運用にあたり、とても重要な課題の1つになります。まずは、それぞれのリスクを整理してみましょう。
|
|
この場合はログインする個人がIDで特定できるので、何かあった場合に証跡が残りますが、利用ユーザー数分のIDの作成も管理も煩雑に。アクセス権限の細かな設定がしきれなかったり、退職者のID情報が残ったままになることで、不正アクセスの恐れがあります。
|
|
ではこちらはどうでしょう?IDの管理負荷は減りますね。ただ共有IDなので、EC2サイトなどが勝手に作られても、「誰」が「何」をしたのかをログからでは確認できなくなり、統制が効かなくなってしまいます。さらに、定期的なパスワード変更をしていないと、やはり外部からの不正アクセスの恐れも。クラウドの怖いところですね。
このように、IAMユーザーのID管理は、リスクヘッジとのバランスが難しいところですよね。「あっちを立てればこっちが立たず」ですし、クラウドという特性上、常に外部ネットワークからの不正アクセスのリスクもつきまといます。
そこで、管理負荷を減らしながらリスク対策もできてしまう方法として、特権ID管理製品を導入する、という選択肢があります。AWSの運用管理を担うIAMユーザーも、オンプレと同じように、特権ID管理製品で管理ができるというわけなのです。世の中には特権ID管理製品と呼ばれるものはたくさんありますが、その効果をクラウド環境にも広げて適用できてしまうものは、まだ、多くはありません。
特権ID管理製品「iDoperation(IDO)」での例を挙げてみましょう。OSやDBの特権ID管理に実績のある製品ですが、5つの機能でこれを実現します。
これを1枚の図で表すと、このようなイメージになります。
|
|
IDOを使うと、ユーザーはまずIDOにログインすることになります。自分に利用が許可されたサーバに対してパスワード入力不要で対象のリソースを利用できるので、そもそもパスワードを覚える必要がなくなります。また管理者の立場からも、にログインしたIDではなくユーザー単位でどんな作業を実施したかを見やすい動画ログで参照でき、仮に特権IDのような共有IDを利用していても、「誰」が「何」をしたかを把握できます。
そしてIDOはAWS連携機能を持っているので、IAMユーザーもオンプレと同じように管理できます。
以下のように、IDOではレポートから、同じ申請時間内、同じ共有IDでも誰が利用したかをきちんと識別できていることがわかります。
|
|
|
|
|
|
何といっても嬉しいのは、IDO自身がAWS上のAMIとして提供でき、DBもRDSと連携してすぐに利用できちゃう、というのがポイントです。
以上のように、AWSのセキュアな運用には、IAMユーザーのIDをしっかりと管理できることがポイントです。特権ID管理製品を利用すれば、管理の効率化とセキュリティの向上が同時に見込めます。
現在、AWS管理で同様の課題を持っている方、今後AWS移管を検討されている方は特権ID管理製品のIDOを検討してみてはいかがでしょうか?
|
|
クラウドサービスの特権IDをしっかり管理したい方に、IDOの利用メリットを2ページで簡単にサマリした資料です。
対応している管理対象プラットフォームもわかります。 お気軽にダウンロードしてご利用ください。 |
長谷川 まり
|
|

iDoperation V2のサポート終了を目前に控えたユーザーの方向けに、スムーズな移行のポイントをまとめました。
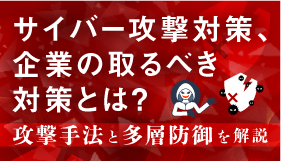
最新のサイバー攻撃手法から、企業の取るべき対策までをご紹介します。サイバー攻撃によるデータの奪取や暗号化などのリスクを下げるために、有効な対策を複数実施し、防御層を重ねる「多層防御」について解説します。