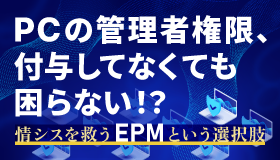
- エンドポイントセキュリティ
- ID管理
- 認証
PCの管理者権限、付与してなくても困らない!?情シスを救うEPMという選択肢
PCがサイバー攻撃で狙われる理由から、管理者権限や同一パスワード運用がもたらすリスク、そしてそれらの課題を解決する手段として注目される「EPM(エンドポイント特権管理)」について解説します。
|
|
みなさんこんにちは。長谷川まりです。
新型コロナウイルスの脅威に対応するため、テレワーク実施企業が急増しています。今回は、テレワークの分類とその中でご紹介できる端末のセキュリティ対策ソフトウェアを4つご紹介します。
ここ数年、テレワークは東京オリンピックを控えた交通交雑緩和を目的に、政府や自治体から推奨されてきました。総務省『平成 30 年通信利用動向調査』によると、2018年9月末時点でテレワークを導入している、または予定があると回答した企業はまだ26.3%でした。これが2020年に入り、新型コロナウイルス対応でいよいよ導入が加速している印象があります。アシストにも、お客様からソリューションのお問い合わせを多く頂いています。
テレワークを大々的に実施することになったところで、セキュリティ対策は同時並行で考えなければなりません。そこで、テレワークのセキュリティ対策の方針作りに役立つ資料の1つが総務省の「テレワークセキュリティガイドライン」です。このガイドラインではテレワーク端末の導入方式を異なる環境の6パターンに分類しており、対策すべき観点を整理しやすくなっています。
|
※「テレワークセキュリティガイドライン(第4版) 」P.9 「表 1 テレワークの6種類のパターン」 |
この6つの方式の選択は、導入のしやすさや対策強度、ユーザー利便性など、各社それぞれの優先ポイントに基づき決定されていると思います。アシストでは上記に色をつけたパターン1,2とパターン6に対応するセキュリティ対策をご紹介しています。いずれもテレワークにおいて強く求められるユーザー利便性を落とさないよう、しっかりと設計されたソフトウェアをお奨めしています。
|
|
この方法では端末にデータを残さないので、最もシンプルでセキュリティ強度の高い環境を構築できます。万が一端末を紛失しても物理的な情報漏洩は発生しませんし、画面転送方式のため基本的には端末と社内システム間の実データのやりとりも発生しません。またインターネットを流れるデータも暗号化により守られます。ユーザーにとってはPCを持ち帰らずに済むメリットもあります。アシストではコストパフォーマンスの高さに定評のある製品をご紹介しています。
テレワーク環境から社内環境へのリモート接続機能をシンプルに実現する製品です。手軽にテレワークを始めたい方におすすめです。
テレワーク環境から社内環境へのリモート接続機能に加え、管理機能も充実した製品です。他要素認証との連携や、テレワークで利用させるアプリケーションの管理をしたい方におすすめです。
|
|
この方法は、普段ユーザーが使い慣れたノートPCなど、いつも会社で利用している端末を利用します。テレワークを初めて体験するユーザーも受け入れやすい方法ですね。端末にデータを残すので、想定される情報漏洩の脅威をシステム的にしっかりと防止し、情報を保護する必要があります。
紛失盗難やデータの持ち出しに備える機能はもちろん、社内と同様のセキュリティ対策を担保するために、オフィス外からの接続方法をVPNに限定させることができます。コストと使い勝手、両面を求めるお客様にお奨めできる製品です。
マルウェア対策ソフトウェアです。テレワークでは従来のパターンマッチング型のアンチウイルスソフトでのパターンファイル更新漏れが課題になりますが、これに代わる次世代の対策を提供します。AIの良さを実感していただける製品です。
以上のように、アシストでは総務省の『テレワークセキュリティガイドライン』の分類上のリモートデスクトップ方式、デスクトップ仮想化方式、会社PCの持ち帰り方式の3パターンに沿ったセキュリティ対策ソフトウェアをご紹介しています。これらの方式でテレワークのセキュリティ対策を検討される方は、選択肢のひとつとしてアシストにぜひご相談ください。
長谷川 まり
|
|
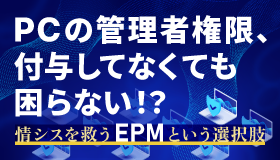
PCがサイバー攻撃で狙われる理由から、管理者権限や同一パスワード運用がもたらすリスク、そしてそれらの課題を解決する手段として注目される「EPM(エンドポイント特権管理)」について解説します。
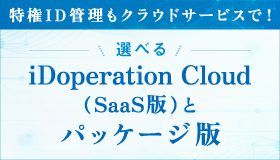
従来のパッケージ版に加え、クラウド版もリリースしたiDoperation。高い可用性が求められるサーバーの特権ID管理もSaaSで利用できるようになったことで、今後ますます需要が増えそうです。

サイバー攻撃では多くの場合、Active Directoryが狙われています。企業の中核システムとして止められない。多機能で運用も複雑。そんなActive Directoryを守るには、どうしたらよいのでしょう。

