経理部門が語るS/4HANAによる変革と期待 ~後編~

アシストでは創立50年を迎えた2022年、激変するビジネス環境、ますます加速されるスピード化に対応するため、今まで20年以上にわたり利用し続けてきた基幹システムの刷新を行うためのプロジェクト(社内名称:NEXIS)を発足しました。
この、基幹システム刷新の状況をなるべくリアルタイムに近い間隔で、社内キーパーソンへのインタビューを中心に、良い話も悪い話も区別なく皆様にお届けしたいと思います。
今回は2024年1月にカットオーバーした会計領域(SMILE(旧会計システム)をSAP S/4HANAに刷新。これをStage0.5と呼ぶ)について、経営管理部長の小牧健一と財務会計チームのプロダクト・オーナーである小島陽子へのインタビューを通して業務担当側の視点でお伝えします。
こんにちは。インタビューを担当させていただきます営業の真下(ましも)と駒形(こまがた)です。
前回に続き、経営管理部長の小牧さんとNEXISプロジェクトの財務会計チームのプロダクト・オーナーである小島さんにお話を伺います。
Fit to Standardについて
真下:SAP標準で利用するために、業務側で変更した点があれば教えてください。
小島:今までは支払先マスターを、請求書に記載されている支払い先口座ごとに作成しており、1社に複数のマスターを登録していました。これをStage1.0(販売領域)で対応するマスター管理を見据えて、仕入先のLBCコード(企業を特定するためのコード)単位で一つのコードで管理するように変更しました。これによりマスターは経理側で自由に追加するのではなく、システムチーム側で管理するように変更となりました。ここが大きくシステムに合わせて変更したことです。
真下:それは1社に対して口座は1つにするということですか。
小島:口座はいくつか設定することはできますが、1社に対して1つのコードで管理することになりました。LBCコードが同じであれば、それに紐づく支払い先も一緒に管理されます。
真下:それは業務にどのような影響を与えましたか。
小島:良い意味での影響はまだ実感はできないですが、決算処理時に債務管理の観点から取引先ごとに債務としてまとめることが容易になるメリットがあります。ただし、固定された支払い口座以外で支払う必要がある場合は手作業で変更しなければならないため、ひと手間増えてミスにつながる可能性があります。
真下:固定口座以外の支払いは頻繁に発生するのでしょうか。
小島:はい。頻繁に発生します。そのため、この部分は手作業が増えてしまっています。
小牧:SAPはマスターがしっかりと整備されているので、例えば勘定科目に対して「税込み」という設定がされている場合、異なる消費税コードを使用しようとするとエラーが発生します。そのため、マスターのメンテナンスによる最新化は重要となります。運用が始まり、今はまだベンダーとの契約があるので対応してもらえますが、ベンダーとの契約が終了した後、どのようにしてマスターの鮮度を維持していくかが課題です。マスター専門のチームの設立についても議論があるようです。
真下:専門チームを作らないとならないくらいマスター管理業務があるということでしょうか。
小牧:はい。支払い先の追加など、現状も日々変化しており、そのために支払いがうまくいかないこともあると聞いていますので、その対応が必要になります。
小島:例えば、勘定科目の税控除を自由に設定できるように変更すると、移送処理が生じます。そうなると、小牧さんの承認を得てシステムチームに依頼し、ベンダーにマスターの修正を依頼してもらっています。この時、ベンダーも本番環境で直接修正するのではなく、一旦検証を行ってからの対応となるため、タイムラグが生じています。あとは、今まで仕入先を自分たちで増やすことができたのですが、それができなくなりましたので、急ぎで新しい仕入先を登録して支払いに回すことができなくなりました。
真下:営業でも、受注する前に見積もりを出すようなケースではマスターがないと大変になりそうです。例えば、特別支援の見積もりなどは、都度マスターに登録してもらってから作成しないとならないようなので、大変そうだと感じています。経理側で管理するマスターというのは、細かい取引明細レベルではなく、仕入先などのマスター管理が必要になるという意味合いでしょうか。
小牧:経理だけではなく、得意先、仕入先、品目など複数のマスター管理が必要となります。
小島:移行作業を行いましたが、本当にたくさんありました。全銀データを全部登録する必要があり、毎年マスターを更新します。勘定コードや消費税が変われば、それに応じてマスターも更新する必要があります。
駒形:マスターの管理は本当に重要ですね。ベンダーに頼むので修正には時間がかかるということですが、社内にマスター管理チームができれば多少作業時間を短縮できたとしても、現状よりはやはり時間がかかってしまいそうですね。
小島:はい。部署をまたいだ依頼を行うことになりますので、今に比べたらどうしてもタイムラグは発生します。ただ、今後は1ヵ所でマスターを管理することになるので、データの精度という面では良いことだと思います。
小牧:Fit to Standardを推進していくと、アシストがこれまで長年当たり前に行っていた処理がSAPのビジネスプロセスに合わないことが洗い出されてきます。この処理はアシスト独自の処理であることはわかるのですが、なぞそのような処理をしているのか、理由は誰もわからない状態になっており、SAPのビジネスプロセスに合わせても不都合がないということもわかりました。このようにSAPへのFit to Standardによってアシストの業務がどうなっているかを改めて確認できました。この点もFit to Standardによって得られたメリットだと思います。
小島:現在はプロダクトごとの経理処理というのがあるのですが、特定の担当者でないと処理ができない状況です。このプロダクトごとの処理を標準化させるためにプロダクトコードをなくす議論を行いましたが、Stage0.5ではAMIS(現行の販売管理システム)が残っておりできませんでした。最終的には標準化された状態で計上処理が一本化されるよう実装する予定です。
小牧:ある経理社員が2018年にアシストを退職する際に作成してくれた評価レポートがあるのですが、そのレポートには本当だったら計上処理は数名でできると書かれています。しかし、なぜできないのかというと、AMISに買掛金の処理機能がないこととイレギュラー対応することが多すぎて処理が進まないことが原因です。これが、Stage1.0がカットオーバーされたら解決されるはずですので、とても待ち遠しいです。

プロトタイプ型の開発手法について
真下:前回までのインタビューで、今回はプロトタイプ型の開発手法を用いてSAPの開発を実施していると聞いています。この手法に対して、業務部門の視点から良かった点と悪かった点について教えてください。
小島:今回、プロトタイプ評価を3回に分けて実施しました。1回目で浮上した問題点を2回目で解決し、2回目で新たに出た課題を3回目で取り組むという方法で徐々に問題を解決していきました。このアプローチにより教育トレーニングを行う前に大きな問題を解消できたことが大きな成果だと思います。ただ、プロトタイプの初期段階ではユーザーが直接操作して評価するという計画でしたが、1回目ではユーザーがシステム操作に慣れることに多くの時間を費やしてしまい、本来のプロトタイプ評価が進まないという問題が生じました。そのため、ベンダーが操作しているところを見せてもらい評価する方法に変更することで、スケジュール通りに進めることができました。しかし、実機を操作せずに見るだけでは評価が難しいという意見が多く出ました。さらに、「実際に操作できない状態のままで大丈夫か」という不安の声が上がりました。そこは、トレーニングでしっかりとフォローすることを伝え、ベンダーの操作説明をもとに評価を進めました。
駒形:SAPの画面は使いづらいという声を聞きますが、そう感じますか。
小島:はい。一般的な会計システムの仕訳で貸借は横一列に表示するのに対し、SAPは縦に表示されるため、まず、その表示方法に慣れることが大変でした。
真下:テスト段階でテストツールを利用する時間と工数を割り当てられなかったと聞きましたが、できれば使いたかったしょうか。
小牧:会計側では、大量処理や再現性のテストなどはあまりないので、そこまで必要性は感じませんでした。販売管理では使いたいと思うのではないでしょうか。
トレーニングについて
駒形:ユーザーへのトレーニングは、ベンダーが行ってくれたのでしょうか。
小島:いいえ。アシストで行いました。ただ、わからないところがあればベンダーには来社してフォローしてもらう体制にしていました。
駒形:トレーニングカリキュラムは、小島さんが作成されたのでしょうか。
小島:トレーニングカリキュラムというよりも、ベンダーがプロトタイプ検証用に準備してくれていたシナリオを元に、実際にトレーニングを行う担当とリーダーでシナリオを作り、テストデータを準備して行いました。このテストデータは、想定通りの動きになるデータはもちろんですが、あえてエラーがでるようなデータを準備して、リカバリーができるか、というテストも行いました。
真下:Stage0.5領域の中でトレーニングの担当は細分化されているのでしょうか。
小島:はい。例えば、支払いを担当している人や売掛金の計上を担当している人など、業務フローに合わせて各担当者にトレーニングを実施してもらいました。
駒形:使うのは正社員だけでしょうか。
小島:まずは正社員が慣れないとBPO(業務の外部委託先)の方に教えられないので、現在は正社員だけです。
真下:先ほどの「実際に操作できない状態のままで大丈夫か」という不安は、実際のトレーニングで払しょくできたのでしょうか。
小島:はい。ただ不安に思っていた期間はかなり長かったです。プロジェクトが始まった1年前頃は、SAPの用語を少しずつ説明していましたが、反応が悪く全然わからないという状況でした。それが2023年12月頃に、執務室内の経理のシマで、普通にSAP用語が飛び交っていることにふと気が付きました。この時、2024年1月に無事カットオーバーを迎えられるなと実感できました。
真下:トレーニングやテストはいつ頃から開始されたのでしょうか。
小島:2023年11月中旬頃からです。本当は、2023年9月から開始したかったのですが、トレーニングを自分たちで計画して実施するという経験がありませんでした。そのため、どのように進めるのかというアレンジを行うところから始めなくてはならなかったので、開始までに時間がかかってしまいました。
小牧:小島さんとITS(社内IT部門)の方が尽力してくれました。統合テストとトレーニング期間が重なることが多かったので、機能ごとにリーダーを設定し、そのリーダーを中心にして数人のチームでそれぞれを主体的に進めてもらいました。最初は戸惑いもあったので全員一緒に座学で学ぶということもありましたが、慣れてくれば、期限に合わせてチームごとに検証を進めることができました。そのため、2023年11月後半から2023年12月中旬は超過密スケジュールの中、少人数で本当に頑張ってテストとトレーニングを100%完了していただきました。これにより、本番カットオーバーに向けて自信を持つことができたと考えていますので、販売管理チームに参考にしていただけたらいいなと思います。
駒形:日常業務を行いながら、このプロジェクトを遂行するのは、本当に大変だったのではないでしょうか。
小牧:小島さんはPO(プロダクト・オーナー)なので専任で携わってもらいました。推進力のある人が運営しないとプロジェクトはうまく管理できないなと実感しました。小島さん以外の方は兼務でしたので、日中はトレーニングを受けて、遅い時間まで既存業務を行っていただいていました。
真下:業務量を減らしてほしいという要望はありませんでしたか。
小牧:ありませんでした。これまでの監査法人が評価してくれているように、本当にプロフェッショナルな人たちで、実は進捗の遅れがあるのでは?と気にしたこともあるのですが、「大丈夫です」と返答があり、実際にきちんと終わらせてくれました。
真下:小島さんは、SAPには初めて携わることになったと聞きましたが、POを担う上でSAPに関して勉強はされましたか。
小島:皆さんよりも先行してK2社(SAPの教育を委託した会社)の研修を受講し、理解を深めることをしました。Signavio(ビジネスモデリングツール。詳しくは「アシストが抱える業務面、システム面の課題について ~後編~」)で業務フローを作成していたので、データのつながりを想像してから、皆さんと議論をしました。
小牧:昨日、経理担当から2024年1月の売上データの表をもらいました。一見、なんの変哲もない表なのですが、これは、初めてSAPのデータで作られた表だったので、嬉しく思いました。
駒形:特にトラブルはありませんでしたか。
小島:細々としたトラブルはありましたが、大きなトラブルはありませんでした。やはり移行処理はトラブルが多かったです。
駒形:そのトラブルはもうなくなりますか。
小島:そうですね。後はStage1.0で債権データの移行があるので、その時に少し発生してしまうかもしれませんね。
Stage1.0への期待と課題について
真下:改めて、Stage1.0への期待と実現するにあたっての課題や今、苦労していることを教えてください。
小牧:ついに販売から会計までの一連の流れがスムーズに機能する統合システムが完成しようとしています。これまでのように部門間で断絶されていた状態から脱却し、初めて全体がつながったシステムに対する期待は非常に大きいです。経理部門はこれまでバックエンドで最終的なチェックを行い、数字を調整する作業をしていましたが、この新システムによりそのような作業は基本的に不要になるはずです。その結果、経理の生産性が飛躍的に向上すると考えています。また、それは営業などの前工程の業務にも良い影響をもたらし、全体の生産性が大きく向上することを期待しています。ただ、現状はいくつかの課題があり、販売管理と会計のチームが共同で検討を始めています。お互いの業務が重なる部分があり、会計側だけでは解決できない問題もあるため連携が必要です。これらの課題を2024年2月から2024年4月初めにかけて解決し、テストやユーザーカットオーバーに向けて進めていければと思っています。
真下:実際には期の変わり目である2024年9月にカットオーバーを行う必要があると岡田さん(プロジェクト・マネージャー)もおっしゃっていました。そのためにはテストやトレーニングを2024年4月までにはある程度完了させる必要がありますね。
小牧:そのとおりです。開発のスケジュールも決まっており、どれだけ開発工程をクリアできるかがプロジェクトの成功を左右します。現在、そのための開発範囲を販売管理担当が検討しているところです。
真下:なるほど、楽しみにしています。
小牧:統合テストとトレーニングも控えており、この時期はとても忙しくなると予測しています。
真下:それはいつ頃の話ですか。
小牧:プロジェクト終盤の最後の3ヵ月間です。なんとかみんなで頑張っていきたいと思います。
駒形:本日は長時間にわたり話を聞かせていただきありがとございました。
(本記事は2024年2月に行ったインタビューをもとに執筆しています)
※記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
インタビュアー&執筆者情報
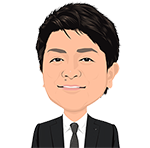
真下 悦拡(ましも よしひろ)
東日本営業本部 東日本営業統括部
粘り強い営業に定評あり。同世代のエース。

駒形 美鈴(こまがた みすず)
東日本営業本部 東日本営業統括部
童顔からは想像できないキレキャラ。番犬的存在。

