
- Oracle Database
もう迷わない!SYSAUX表領域の肥大化の原因と対処法を徹底解説!
本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
|
|
Oracle Databaseライセンスに関する第5回「高可用性編」です。
今回の連載は、本記事でひとまず最終回となります。
これまではエディション、ライセンスの種類、カウントの方法、という基本的な部分と、構成面の理解として仮想化環境とクラウド環境の考え方をご紹介してきました。
本記事では、データベースの非機能要件として必要不可欠な「高可用性」構成について、Oracle Databaseライセンスの定義やルールをご説明します。
前回までもご紹介していますが、まずOracle Databaseライセンスの原理原則について触れておきます。どのような場合にもこれを念頭に置いて読んでいただきたいと思います。
|
|
新たなシステムを構築、あるいは既存のシステム更改などのケースにおいて、重要なシステムであればあるほど何かしらの「冗長化対策」は検討されていると思います。冗長化要件(RTOやRPOなど)を踏まえ、最適な構成を考えていくことになりますが、同時にコスト面も考慮する必要があります。
構成を確定した後、「ここにもライセンスが必要とは知らなかった」となって、コスト試算が手戻りにならないようにしましょう。
さて、Oracle Databaseでは様々な冗長化方法があります。よく知られているところでは Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) や Oracle Data Guard があげられます。メーカが提唱している「Oracle Maxinum Availability Architeture (Oracle MAA)」(下図) でも、様々な方法が挙げられています。
こういった様々な方法がある中、Oracle Databaseのライセンスはどこに必要となるかご存じでしょうか?本記事では基本的な考えをご紹介していきます。
|
|
本ブログの連載では、冒頭で原理原則を紹介しています。
「ライセンスはサーバに対して許諾」
「ライセンスはインストールされているサーバまたは稼働しうるサーバに必要」
特に高可用性構成では、この原理原則を軸に考えると理解しやすいです。
先にご紹介したOracle MAAの他にも、様々な冗長化の手法が考えられます。「〇〇のパターンでは△△にライセンスが必要」のように、その都度確認していくのは大変です。原理原則に照らし合わせながら、そのポイントを理解するようにしましょう。
高可用性構成では冗長化のために複数のサーバが存在しています。関連して、
障害時に迅速に復旧させるために、Oracle Databaseがインストールされているサーバや稼働するサーバが複数用意されているのが一般的です。
その構成で
「Oracle Databaseがインストールされ、稼働するサーバはどこなのか?」
ここをきちんと捉えることで、Oracle Databaseライセンスが必要なサーバを適切に見定めることができます。
Oracle Databaseで一般的な高可用性構成を踏まえると、下記3パターンで捉えることができると考えております。
|
|
これらの3つの考え方について、1つずつ見ていきましょう。
「バックアップする際には、Oracle Databaseライセンスは必要ですか?」
こういった相談もよくいただきます。このようなケースでは「バックアップの保管のみ」と「代替機の存在有無」を確認します。
まずバックアップの保管ですが、バックアップを取得するだけではOracle Databaseのライセンス対象にはなりません。原理原則に当てはめて考えると、バックアップを保管する先、例えばストレージやテープデバイスにOracle Databaseソフトウェアはインストールされていないことが多いです。Oracle Databaseソフトウェアがインストールされていない場合にはライセンスは不要となります。
一方、バックアップから復旧する方法として、本番機とは別に代替機が用意されていることがあります。この代替機にはOracle Databaseライセンスが必要です。
「代替機は、通常時はOracle Databaseは稼働していないので、ライセンスは不要ではないか?」こういった疑問をもたれる方もいらっしゃるかもしれません。原理原則では「インストールしたサーバにライセンスは必要」であり、また障害時には「Oracle Databaseが稼働しうる状態」になるため、代替機にはOracle Databaseライセンスは必要という考え方になります。
昨今ではクラウドを検討する方も多いと思います。代替機にクラウドのPaaSを用意した場合には稼働する時間帯の利用料金となります。クラウドのPaaSが利用でき、かつ利用時間が少なく想定できる場合には、こういった方法も検討する価値があります。
整理すると、以下のようになります。
▷ バックアップ構成で必要となるOracle Databaseライセンス
|
|
|
|
先にあげたOracle RACや商用クラスタソフトウェアを活用した、Oracle Databaseを利用するシステムでは、最もよく利用されている高可用性構成のパターンです。
クラスタ構成の場合には、対象となるサーバ(ノード)で Oracle Databaseが稼働する状態になっているため、基本的には全てのノードで Oracle Databaseライセンスが必要です。ここはシンプルに考えることができます。
クラスタ環境におけるOracle Databaseライセンスを検討する際に、ぜひ覚えていただきたいことは「フェイルオーバー構成」の場合、待機系サーバ1台分は本番系のライセンスを利用できるケースが存在するということです。このルールは「Oracle データ・リカバリ・ポリシー」で定義されています。
▶Oracle データ・リカバリ・ポリシー 文書
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/datarecoverypolicy-079765-ja.pdf
簡潔にいうと、1つのシングルストレージまたはSANを利用する構成で、クラスタソフトウェアを利用したActive/Standy構成では、待機側サーバの利用が年間10日間以内を前提に、これを本番機ライセンスで稼働させることが可能、というものです。
このパターンはActive/Standy構成であるため、サーバ障害にはある一定の時間切替が必要にはなりますが、この切替時間が要件として許容できる場合には、待機サーバのOracle Databaseライセンスコストの節約につながります。注意点としては、年間10日間以内という稼働条件があるため、切り戻しの運用は検討する必要があります。実際に、ライセンスの有償オプション「RAC One Node」などをご利用のお客様では多く採用されているケースです。ぜひご認識いただきたいルールの1つになります。
整理すると、以下のようになります。
▷ クラスタ構成で必要なOracle Databaseライセンス
|
|
|
|
最後はハードウェアや拠点の障害対策、またはBCP対応の場合に検討される、Oracle Databaseが稼働する環境を複数用意し、データを同期しながら冗長構成をとるパターンです。
オラクル製品ではOracle Data GuardやOracle GoldenGateを採用したり、あるいは類似する3rdベンダー製品の選択やストレージ技術利用など、実装にはいくつかの方法があります。
このケースでは、Oracle Databaseライセンスという観点では、本番系、待機系、両方にライセンスが必要とシンプルに考えることができます。待機系でもOracle Databaseが稼働しうる状態にあるためです。ここは、「A.バックアップ構成の考え方」で説明した待機系サーバが存在するパターンと同様です。
待機系については、方式や手法によって必要となるライセンスが異なりますので考慮が必要です。本番機と同一構成にすべきケース、または本番機と異なってもいいケースがあります。これはそれぞれ採用するソリューションごとに確認してください。
整理すると、以下のようになります。
▷ データ複製 構成で必要なOracle Databaseライセンス
|
|
高可用性構成でのOracle Databaseライセンスの考え方は、ご紹介した3つのパターンで概ねカバーできると考えますが、共有ディスクに製品を導入するケースの相談もいただくため、その場合の考え方をご紹介します。
本記事では原理原則を紹介してきましたが、共有ディスクにOracleソフトウェアモジュールをインストールした場合には「ストレージに接続する全てのサーバに対しOracle Databaseライセンスが必要」という考え方になります。
仮に運用として、Oracle Databaseを稼働させるサーバを決めていたとしても、共有ディスクにOracleソフトウェアモジュール(Oracleバイナリ)がある場合には、他サーバでもOracle Databaseが稼働しうる状態になります。
共有ディスクにOracle Datatabaseを導入した場合には、ライセンス対象となるサーバ数に注意するようにしましょう。
整理すると、以下のようになります。
|
|
第5回の本記事は、いかがでしたでしょうか。
高可用性構成では、場面場面でOracle Databaseが稼働したり稼働しなかったり、また普段動いていない待機系はどう考えればいいのか?など、一見理解しづらいと思われがちです。ただ検討される可用性パターンと原理原則に照らし合わせてみると、整理しやすいのではと捉え、このような観点でまとめてみました。
本連載は、この回を持って一旦終了しますが、Oracle Databaseライセンスに関しては、ほかにも様々なトピックがあります。今後もデータベース業界の動向を踏まえ、お客様のお役に立つ情報をお届けしたいと思います。
本連載でご説明している内容を、無料のウェビナーでもご紹介しています。
ブログを読むだけでは理解しづらいところも、実際の講師の解説のほうが分かりやすいこともあります。
ここまでお読みくださった方は、データベースの非機能要件として必要不可欠な「高可用性」構成時のOracle Databaseのライセンスルールはご理解いただけたかなと思いますが、もしかしたら消化不足の部分もあるかも知れません。ご都合が合えばウェビナーに参加してブログで復習する、それでも自社の環境固有の課題で不明な点があれば、お問い合わせいただくこともできますし、また個社別の勉強会も承るなどフォローアップも万全です。
オンデマンドで時間の取れるときにいつでも何度でもご覧いただけます。詳しくはこちらのページ
でご確認ください!

|
|---|
アシスト入社後、サポートセンターやフィールド支援を経て、現在はプリセールスエンジニアとして製品やソリューションの紹介からインフラ提案といった業務に従事。
また「今だから見直そう!Oracle Databaseライセンスの活用方法」ウェビナーを始め、Oracle Databaseライセンス関連のセミナー/ウェビナー講師も担当。
趣味は登山で、セブンサミッツをじかに見てみたいと思っている。 ...show more
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
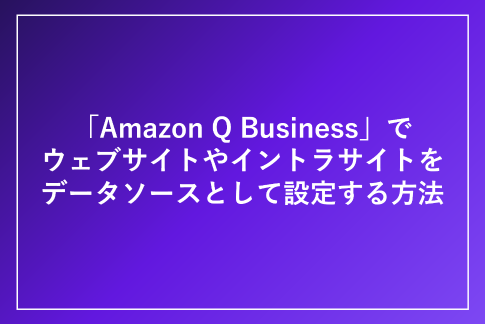
この記事ではAmazon Q Businessでウェブサイトやイントラサイトをデータソースとして設定する方法についてご紹介します。
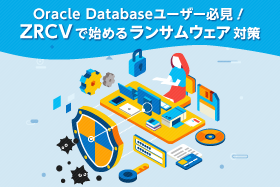
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。