
- Oracle Database
もう迷わない!SYSAUX表領域の肥大化の原因と対処法を徹底解説!
本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
|
|
2024年9月にラスベガスで「Oracle CloudWorld 2024」が開催されました。
アシストからも技術者が参加し、多くの情報をキャッチアップしてきました。
その「Oracle CloudWorld 2024」にて、新サービスのOracle Exadata Database Service on Exascale Infrastructure(エクサスケール。以下、ExaDB-XSと表記)がリリースされました。
日本でも、すでに東京リージョンと大阪リージョンの両方でExaDB-XSが提供されています。
そんなExaDB-XSについて、既存のPaaSサービスとスペックがどう異なるかなど気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで、ExaDB-XSの特徴をまとめてみました!
Index
ExaDB-XSは、Oracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)上でExadataのサービスが利用できるPaaSサービスです。
既存のOCI PaaSサービスのOracle Base Database Service(以下、BaseDB)とExadata Database Service on Dedicated Infrastructure(以下、ExaDB-D)の中間に位置するようなサービスと考えるとわかりやすいでしょう。
|
|
ExaDB-XSが注目されるポイントを3つ紹介します。
ExaDB-XSは、OCI上でExadataを共有のインフラストラクチャで利用できるという点が大きな特徴です。共有インフラストラクチャは物理的な基盤を他のユーザーと共有しているため、それぞれのユーザーが利用したい容量のストレージを利用でき、無駄がありません。
OCI上でExadataを利用する場合、これまでは専用インフラストラクチャのExaDB-Dという選択肢しかありませんでした。ExaDB-Dは大規模システムで利用する場合に最適な基盤としてその強みを発揮しますが、コスト面や規模の点で中小規模のプロジェクトには適さないケースもありました。
ExaDB-XSは、必要なだけのリソースを使うことができるため、効率的であり、かつスモールスタートが可能です。インフラストラクチャが共有(オラクル社が管理)であることの制限として、ExaDB-Dと異なり、自動メンテナンスの日時をユーザーが指定することはできませんが、その点についても対応されています。ExaDB-XSはRAC構成となっており、サービスを止めることなく自動メンテナンスが行われるため、ユーザーの業務に支障をきたすことはありません。
なお、自動メンテナンスは2週間前までに通知されるため、それまでに手動で再起動することで自動メンテナンスを避ける(≒手動で再起動することでメンテナンスの日時をある程度コントロールする)こともできます。
ExaDB-XSは、前述のとおり、必要最小限のリソースからスタートできます。そして、システムの成長に応じて柔軟にスケールアップできます。
具体的には、CPU数やストレージ容量をオンラインでスケーリング可能であり、その際CPU数とメモリー容量をそれぞれ指定できるため、初期投資を抑えつつ、ワークロードの拡大に合わせた柔軟なスケーリングが可能です。
ExaDB-XSでは、Smart ScanなどのExadata固有の機能が利用できます。
従来のExadataサービスとの大きな違いは、Exadataサービスで採用されているOracle Automatic Storage Managementとは異なる固有のストレージアーキテクチャが採用されている点です。
Smart ScanなどのExadata固有の機能で高い性能を担保しながら、このExaDB-XS固有のアーキテクチャにより、SPARCEディスクグループを用意しなくても、データベースのクローン機能を利用できるようになりました。まさにいいとこ取りのサービスと言えます。
次はExaDB-XSの位置付けをより明確にするため、既存のPaaSサービスであるBaseDBおよびExaDB-Dとのスペック比較表を示します。
| BaseDB | ExaDB-XS | ExaDB-D | |
|---|---|---|---|
| インフラストラクチャ | 専有 | ||
| 1クラスタあたりのデータベース・サーバー数 | 1~2 | 2~10 | 1~32 |
| CPU | 1~64(OCPU) | 16~2000(ECPU) | 4~4032(OCPU) |
| メモリー(GB) | 8~1024 | 44~5500(2.75GB/ECPU) | 720~44480 |
| データベース・ストレージ | 256(GB)~ 80(TB) | 100(GB)~ 99(TB) | 29(TB)~ 3242(TB) |
| データベース・ストレージ(RECOやOS領域を含む) | 712(GB)~ 100(TB) | 300(GB)~ 100(TB) | 73(TB)~ 4864(TB) |
| 利用可能なDB数 | 1CDB 複数PDB | 複数CDB 複数PDB | 複数CDB 複数PDB |
| オンライン・スケーリング | ストレージのみ | CPU、VM数、ストレージ | CPU、VM数、ストレージ |
| 備考 | ・RAC構成の場合VM.Standard.A1.Flexシェイプは不可 | ・Exadata特有の機能有り ・ECPUは4の倍数でスケーリングが可能 |
・Exadata特有の機能有り |
前述したとおり、ExaDB-XSはOCIの利用者全体で物理的なインフラ基盤を共有する共有インフラストラクチャを採用しているため、高い柔軟性とコスト効率が特徴です。BaseDBはシンプルな利用に適している一方、ExaDB-Dは専有環境で大規模なシステムに特化したサービスです。
例えば、BaseDBではリソースが限られ、要求の高いワークロードに対応できない場合があります。一方で、ExaDB-Dのような専有リソースは必要以上にコストが高くなることやオーバースペックである場合もあります。
ExaDB-XSはこれらのギャップを埋め、共有インフラストラクチャの特性を活かしつつ、Exadataの高性能機能を活用できるため、BaseDBとExaDB-Dの中間に位置するようなサービスであることがわかります。
ExaDB-XSは、以下のようなニーズを持つ企業やプロジェクトに適しているといえます。
共有インフラストラクチャの利用により必要なリソースを最適化することで、コストを抑えながらも、高可用性と高いパフォーマンスを享受できます。
ExaDB-XSは必要最低限のリソースから開始し、将来的な成長に応じてリソースを拡張できるため、新規システム導入時やテスト環境としての利用などの場合に、低コスト運用からスタートできます。また、スケールアップが容易であるため、無駄なコストを発生させず、必要に応じたスケーリングが可能です。
複数のデータベースを1つの環境に集約することで、分散されたデータベースの管理が効率化され、管理負荷が軽減されます。また、全体の運用コストやライセンス費用の最適化にもつながります。前述の比較表にも記載したとおり、ExaDB-XSでは複数CDB/複数PDBの作成が可能なため、こうしたデータベース集約の要件にも適しています。
つまり、OCI環境への移行先として、OCI上でも高い性能と可用性が要求される場合やBaseDBやExaDB-Dではスペックや費用感が合わない場合、分散したデータベースを一つに統合する場合などに最適な選択肢となる可能性のあるサービスなのではないでしょうか。
また、現在オンプレミス環境でOracle Database Applianceを利用している場合にも、ワークロードの規模感から考えて最適な選択肢になるかと思います。
今回は待望の新サービスExaDB-XSの概要とメリットをご紹介しました。
BaseDBとExaDB-Dの中間に位置するようなサービスとして、柔軟性やコスト面でのメリットが大きく、スモールスタートやオンラインスケーリングを重視する企業にとって理想的な選択肢と言えるでしょう。
今後はより技術的な面のExaDB-XSのメリットをご紹介する予定です。

|
|---|
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
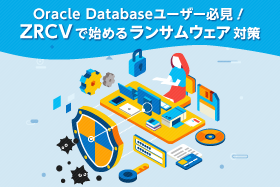
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。

本記事では、お客様の自己解決率向上のために注力したFAQ作成、および、そのFAQ作成をエンジニア育成に活用した当社ならではの取り組みをご紹介します。