
- Oracle Database
もう迷わない!SYSAUX表領域の肥大化の原因と対処法を徹底解説!
本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
|
|
Oracle Database@AWSについてご案内するセミナーの開催が決まりました!
詳細はこちら からご確認ください。
前回のブログ記事では、Oracle Database@AWSに関する現時点で判明している情報について、利用可能となるデータベースサービスの説明を中心にご紹介しました。
そして2024年12月1日、ついにOracle Database@AWSがLimited Previewにて提供されました!
※Limited Preview : 希望者向けのプレビュー公開。また、現時点(本記事公開時点)ではUS Eastリージョンのみで利用可能。弊社でも申し込みを実施しています。
Oracle Database@AWS is now in limited preview
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/12/oracle-database-aws-limited-preview/
サービス公開に合わせ、オラクル社及びAWS社のドキュメントページに本サービスの説明が掲載されています。また、既にサービス提供されているOracle Database@Azureの各種ドキュメントでは、詳細なアーキテクチャにも言及されています。
そこで今回は、これらのドキュメントを読み解き、Oracle Database@AWSのアーキテクチャについて予想も交えながらお伝えします。東京リージョンでの提供はしばらく先になりそうな予感もしていますが、ぜひ参考にしていただければと思います。
※一部、2024年12月時点の発表情報をもとにした考察が含まれます。閲覧いただいている時期によっては、サービス内容がアップデートされている場合がありますのでご了承ください。
「Oracle Database@AWS」に関する続編記事は以下よりご参照ください。
Index
Oracle Database@AWSが利用可能となったことに合わせて、AWS社及びオラクル社のいずれのドキュメントも公開されています。
| ドキュメント | URL |
| Oracle Database@AWS User Guide (AWS社ドキュメント) |
https://docs.aws.amazon.com/odb/latest/UserGuide/what-is-odb.html |
| Oracle Database@AWS (オラクル社ドキュメント) |
https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/database-at-aws/oaaws.htm |
| Deploy Oracle Database@AWS (オラクル社リファレンスアーキテクチャページ) |
https://docs.oracle.com/en/solutions/deploy-oracle-db-aws/index.html |
これらのドキュメントに掲載されているアーキテクチャ図を元に、Oracle Database@AWSに関する基本的なアーキテクチャ構成を作成したものが以下になります。
Oracle Database@AWSのアーキテクチャはおおよそ以下の内容であると理解が出来ます。
・ODB Network = Oracle Database@AWSで利用されるネットワークであり、内部的にはOracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)のネットワークサービス(Virtual Cloud Network/VCN)である。このネットワークの中に各データベースサービスが配置される。
・既存のVPCとODB Networkを接続ドキュメントではODBピアリングと明記)をすることでアプリケーションサーバーからデータベースへの接続が可能となる。
現在利用が可能なOracle Database@AWSは非常にシンプルな構成です。また、アーキテクチャ図の右にOCI VaultやOCI Object Storage、Control Planeがあることから、以下の操作や仕組みはOCIの仕組みを利用するイメージかと予想しています。
| 項目 | 概要 | 利用目的(予想含む) |
| OCI Vault | OCIで利用可能な鍵管理サービス | ExaDB-D(*)等で利用するデータベースの暗号鍵の管理 |
| OCI Object Storage | OCIで利用可能なオブジェクトストレージサービス | ExaDB-Dのデータベースバックアップの取得先 |
| Control plane | OCIリソース管理基盤 | ExaDB-D等のサービスおよびネットワークリソースの管理作業/DataSafeによるデータベースセキュリティ管理など |
(*)ExaDB-D・・・Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure
Oracle Exadataの詳細は こちら よりご確認ください。
ただし、確認を進める上で気になる箇所もいくつかありました。
AWSのドキュメントでは「ODB NetworkはAWS管理」という記載があり、ここだけを読むとODB Networkはユーザーにて全く触れられないような印象を抱きました。一方、OCIのドキュメントリファレンスアーキテクチャにはネットワークセキュリティグループ(OCIのFW機能)やロードバランサーに関する記載があり、ユーザーでも利用できるのではないか?とも感じました。
また、オンプレミス環境からOracle Database@AWSへの接続方法についても言及はされておりません。一方、Oracle Database@Azureではオンプレミスからのアクセスも可能ですので、こちらも今後のアップデートにて対応されると思われます。
他にもいくつか気になる点はありますので、このような不明点については今後のドキュメントのアップデートや実際に検証を進めていく中で確認していきたいと考えています。
Oracle Database@AWSは現在プレビュー版でのリリースですが、Oracle Database@Azureは既に東京リージョンでも利用が可能な状況です。
そのため、@Azureのドキュメント等に記載がされている各種アーキテクチャや運用内容は、今後の@AWSでも採用される、アップデートがある内容だろうと考えています。
そのため、ここからはOracle Database@Azureのドキュメントの中でも、高可用性アーキテクチャに関するドキュメントである『Oracle Maximum Availability Architecture for Oracle Database@Azure』の内容(ゴールド構成)を元に、Oracle Database@AWSの将来像についてお伝えしつつ、検討ポイントとなりそうな箇所についてお伝えします。
※Maximum Availability Architecture(以下、MAA)
High Availability Overview and Best Practices - Oracle Maximum Availability Architecture for Oracle Database@Azure
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/haovw/oracle-maximum-availability-architecture-oracle-databaseazure.html
High Availability Overview and Best Practices - Oracle Maximum Availability Architecture for Oracle Database@Azure ゴールド構成 MAAアーキテクチャ図
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/haovw/oracle-maximum-availability-architecture-oracle-databaseazure.html#GUID-7A38AFBF-0184-46EA-ACB1-1188BBAA2B67
上記がOracle Database@AWSのOracle MAAゴールド構成に準拠した、アシストオリジナルのアーキテクチャ予想図です。以下の3点がポイントになると予想します。
ExaDB-Dでは、Oracle Databaseの高可用性構成で採用されるOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)が利用可能です。ただし、Oracle RACはあくまでも1つのAZ内での可用性構成を実現するものです。そのため、マルチAZ構成を採用するためにはExaDB-Dを2つ利用したDataGuard構成を採用する必要があります。
上記の内容はOracle Database@Azureに関するマイクロソフト社のドキュメントにも「データベース、データベース クラスター、または可用性ゾーンの障害に対する高可用性とDR保護を確保するには、Oracle Database@Azure 上の Oracle RAC と、別のゾーンにある対称スタンバイ データベースを使用します。」という内容で、Oralce RACと別にスタンバイデータベースを採用することについて言及されています。
そのため、Oracle Database@AWSでもおそらく同様の構成が必要になると予想します。従来のAWSに合わせてマルチAZ構成とするためにExaDB-D 2セットを利用した構成とするか、AZ障害は考慮しないExaDB-D 1セットの構成とするかの検討が必要になりそうです。
Oracle Database@Azureのドキュメント記事の中では「Peering Networks Between Primary and Standby」で触れられている内容です。以下、Oracle Database@Azureを前提に説明を実施します。
①で述べたようなプライマリ環境とスタンバイ環境を利用したData Guard構成を取る場合、データのやり取りを実施する経路として「Microsoft Azureのネットワーク」と「OCIのネットワーク」のいずれかの経路にて通信が可能との記載があります。実はこの2つには以下のような違いがあります。
| 項目 | Microsoft Azure | OCI |
| 単一プロセスにおけるネットワークスループット | 最大3Gbit/s | 最大14Gbit/s |
| レイテンシー | OCIよりも20%高い | 低い |
| データ転送料金 | 発生する | 発生しない |
こういった違いは当然AWSとOCIでも同様に発生するため、ネットワーク構成は上記のような比較も必要になるでしょう。
そのため、Oracle Database@〇〇を採用する際には、該当のクラウドサービスプロバイダ(以下、CSP)に詳しいメンバーだけでなく、OCIの仕様や仕組みにも詳しいメンバーを用意して検討を進めることが重要になりそうです。
Oracle Database@〇〇を利用する場合、該当のCSPだけでなくOCIの各種サービスやリソースも利用することになります。そのため、メンテナンス等の発生に伴う検討がOCIでも必要になります。
実際に以下のOracle Database@AzureのページにてExaDB-Dに関する計画メンテナンス及び計画外の停止時で予想される影響について言及されています。
High Availability Overview and Best Practices - Expected Impact During Unplanned Outages(計画外の停止時に予想される影響)
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/haovw/db-azure1.html
High Availability Overview and Best Practices - Expected Impact During Planned Maintenance(計画メンテナンス中に予想される影響)
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/haovw/db-azure1.html#GUID-21D97CC2-CCB6-4D6C-9AE8-81BF826479F2
このようにこれまでCSPでは考慮していなかった事項への対応が必要になるため、構築メンバーのみならず運用チームも巻き込みながらの検討が必要になるでしょう。
いかがでしたでしょうか?
ついにLimited Previewでリリースされた「Oracle Database@AWS」。弊社内での注目度も非常に高く、またお客様からご質問やご紹介の機会をいただく機会も早速増えてきております。
これからも本サービスの最新情報や利用するための準備事項、詳細なメリットなど様々な情報を発信していきますので、ぜひご期待ください!
では、次のブログ記事でお会いしましょう!
|
|
~アーキテクチャから運用・使い分けポイントまでご紹介~
2024年に発表され、限定プレビューが開始されているOracle Database@AWSについて、現時点で公開されている情報を整理して、サービスの概要や基本アーキテクチャ等をご紹介します。
さらに、Amazon RDSやOracle Database on EC2等他のOracle Database利用方法との使い分けポイントもご紹介。クラウド環境でのOracle利用を包括的に学べますので、ぜひご参加ください!
【日時】 2025年4月24日(木) 14:00~15:00
【プログラム】
1.Oracle Database@AWSのサービス概要の紹介
2.アーキテクチャ&運用検討ポイントの紹介
3.Oracle Database利用における他の方法との棲み分けポイントの紹介
4.Q&A

|
|---|
2015年にアシストに入社後、Oracle DatabaseやOracle Cloudを中心としたフィールド技術を担当。
導入支援だけではなく、最新機能の技術検証も積極的に実施。社内外のイベントにて発表も行っている。...show more
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
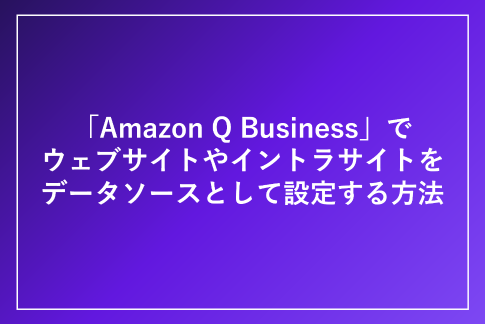
この記事ではAmazon Q Businessでウェブサイトやイントラサイトをデータソースとして設定する方法についてご紹介します。
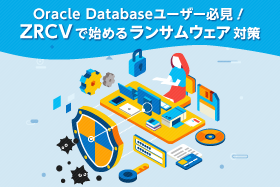
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。