
- Oracle Database
もう迷わない!SYSAUX表領域の肥大化の原因と対処法を徹底解説!
本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
|
|
Oracle Database@AWSについてご案内するセミナーの開催が決まりました!
詳細はこちら からご確認ください。
前回のブログではOracle Database@AWSのアーキテクチャについて、予想を含めてご紹介させて頂きました。
一方、Oracle Databaseの利用において安定稼働を実現するためにはデータベース観点における『運用管理』、つまり『バックアップや監視をどう実施していくのか?』という点の検討は欠かせません。
そしてOracle Database@AWSにおけるバックアップや監視についても、オラクル社及びAWS社のドキュメントページに少しづつ情報が掲載され始めています。
そこで今回は、これらのドキュメントを読み解きながらOracle Database@AWSにおけるバックアップ/監視にフォーカスして情報をお届けいたします。ぜひ参考にしていただければと思います。
※一部、2025年3月時点の発表情報をもとにした考察が含まれます。閲覧いただいている時期によっては、サービス内容がアップデートされている場合がありますのでご了承ください。
連載1回目のブログ記事はこちらからご確認ください。
Index
まず初めにOracle Databaseにおけるバックアップの仕組みについて、おさらいがてら紹介します。
Oracle Databaseのバックアップは、大きく分けて『論理バックアップ』と『物理バックアップ』の2種類に分類されます。
論理バックアップは、データベース内のオブジェクト(表、索引、ビューなど)を論理的な形式でエクスポートし、必要に応じてインポートできるようにする手法です。ツールとしては一般的に『Data Pump Export(EXPDP)/ Import(IMPDP)』を利用します。
物理バックアップは、データベースの物理ファイル(データファイル、制御ファイル、REDOログファイルなど)をコピーする手法です。ツールとしては一般的に『Recovery Manager(RMAN)』を利用します。
| バックアップ種類 | 主な用途 | 代表的なツール |
| 論理バックアップ | データ移行、部分復旧、特定オブジェクトのバックアップ | Data Pump(EXPDP/IMPDP) |
| 物理バックアップ | システム全体の復旧、障害対応、災害対策 | RMAN |
Oracle Database@AWSで提供されているExaDB-DおよびAutonomous Databaseのバックアップ方法についてAWS社のドキュメントでは言及されておりませんが、オラクル社ドキュメントには以下の記載があり、現時点(2025年3月時点)では「OCI上のObject Storageにバックアップを実施する」という機能が提供されています。
バックアップ
専用インフラストラクチャ上の Oracle Exadata Database Serviceにプロビジョニングされたデータベースの自動バックアップは、
OCI リージョンのOCI オブジェクト ストレージにバックアップできます
。自動バックアップ プロセスは、毎日のバックアップ ウィンドウ内の任意の時点で開始されます。オプションで、自動バックアップ プロセスが開始される 2 時間のデータベース スケジュール ウィンドウと、それらのバックアップの保持ウィンドウを指定できます。
こちらのバックアップは『物理バックアップであるRMAN』を利用したものです。また、以下の考慮ポイントを抑えておく必要があります。
| 考慮ポイント | 内容 |
| 開始時間の指定方法 | バックアップの開始時間については、任意の2時間より指定する方法になります。 ※「0:00丁度に開始したい」や「バッチ処理終了後に開始したい」という要件には非対応 |
| AWS上のストレージへのバックアップ | 本記事を記載している時点(2025年3月)では、AWS上のストレージ(Amazon S3)へのバックアップは実装されておりません。 ※将来的なロードマップとして、Amazon S3へのバックアップは対応予定 |
また、Oracle Cloudで実装されているバックアップのサービスとして「Zero Data Loss Autonomous Recovery Service(以下ZRCV)」が提供されています。
ZRCVはデータベース領域におけるランサムウェア対策を重視したバックアップサービスであり、Exadata等の大規模システムのバックアップ運用においても非常に注目すべき内容です。また、こちらのサービスがOracle Database@Azureにおいて、Azure上に存在するストレージへのRMANバックアップを実施する手段として提供されております。
リンク① : Zero Data Loss Autonomous Recovery Service サービス概要
https://speakerdeck.com/oracle4engineer/zrcv-overview
リンク② : Zero Data Loss Autonomous Recovery ServiceがOracle Database@Azureで提供開始
https://blogs.oracle.com/oracle4engineer/post/ja-zero-data-loss-autonomous-recovery-serviceoracle-databaseazure
そのため、Amazon S3へのバックアップ取得の仕組みとしても本サービスが利用されるのではと推察しています。
Oracle Database@AWSにおける監視手法についてはAWS社のドキュメントにおいても言及されています。監視手法としては主にAmazon CloudWatchの利用に言及されています。
また、監視を実施するにあたっては、Oracle Database@AWSの構成要素についても理解したうえで検討を進める必要があります。まずはOracle Database@AWSの構成要素について紹介します。
Oracle Database@AWS(ExaDB-D)の構成要素は主に以下の3要素が存在し、各要素事に監視を検討する必要があります。
◯構成要素
| 構成要素 | 説明 |
| クラウド VM クラスター | データベースが稼働する仮想マシン(VM)の集合体 |
| コンテナ・データベース(CDB) | Oracle Databaseのコンテナ構成において、データベース全体で共有するオブジェクトやメタデータ情報が格納されている場所 |
| プラガブル・データベース(PDB) | Oracle Databaseのコンテナ構成において、CDB内に格納される自己完結型のデータベース領域 |
Oracle Database におけるコンテナ構成自体は2013年にリリースされたOracle Database 12c R1(12.1.0.1)に登場しました。
従来型の非コンテナ構成は、現在Oracle Databaseのバージョンとして主流である19cでは非推奨 / 21c以降は非サポートとなっており、これまで非コンテナ構成で利用していたOracle Databaseシステムについても、今後はコンテナ構成を採用していく必要があります。
※また、Amazon RDS for Oracleにおいても2023年11月より19c / 21cにおいてマルチテナント構成がサポートされるようになりました。
CDB/PDBの詳細について知りたい!という方は以下ブログにてご説明をしておりますので、必要に応じてご一読頂ければと思います。
マルチテナントはトラブル調査をどう変えるのか
https://www.ashisuto.co.jp/db_blog/article/oracledb-mt-for-troubleshooting.html
マルチテナントのPDB数はどう見積もる?最適なエディション選択と検討のヒント
https://www.ashisuto.co.jp/db_blog/article/howto-estimate-number-of-pdb.html
話を戻し、Oracle Database@AWSにおいて、Amazon CloudWatchを利用した監視が可能な主なメトリクスを紹介します。詳細はドキュメントをご確認下さい。
| 構成要素 | メトリクス例 |
| クラウド VM クラスター | CPU使用率/メモリ使用率/ストレージ利用率/スワップ領域の使用率など |
| コンテナ・データベース(CDB) | CPU使用率/ストレージ利用率/ログオン数/ブロック変更情報など |
| プラガブル・データベース(PDB) | CPU使用率/メモリ使用率/ストレージ利用率/IOPS・スループット情報/プロセス数・セッション数など |
Monitoring Oracle Database@AWS with Amazon CloudWatch
https://docs.aws.amazon.com/odb/latest/UserGuide/monitoring-cloudwatch.html
上記のようにAmazon CloudWatchを利用したOracle Database@AWS監視においては、CPU使用率やメモリ使用率といったメトリクス情報は確認ができるものの、現時点ではトラブルシュートやチューニングに役立つ情報(特定SQLの負荷状況など)については取得ができません。
トラブルシュートやチューニングに役立つ情報を取得する方法としては、将来的な観点も含めると以下が対応方針に上がると想定しております。
Enterprise Manager Cloud Control(EMCC)はOracle Databaseの純正機能として利用が可能な管理ツールであり、データベースの監視や管理、システムの問題検出/原因分析、パフォーマンス分析等、非常に多くの管理機能が提供されています。
また、Webベースで提供されており、使いやすいユーザーインタフェースを備えたシステム管理ツールとして一般的に広く利用されています。
最新バージョンであるEMCC24aiについても以下ブログにて紹介をしておりますので、興味のある方はぜひご覧下さい。
EMCCの新バージョン24aiがリリースされました!
https://www.ashisuto.co.jp/db_blog/article/oracle-emcc24ai.html
Amazon RDSを監視する手法としては、以前より「Performance Insights」が提供されておりましたが、該当サービスの機能などが統合された新たなサービスとして、「CloudWatch Database Insights」が2024年12月にリリースされています。
リリース時点ではAmazon Auroraのみが対象でしたが、2025年2月にOracle含めたAmazon RDSにも対応しています。
AWS が Amazon CloudWatch Database Insights を発表
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2024/12/amazon-cloudwatch-database-insights/
CloudWatch Database Insights、RDS データベースのサポートを追加
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2025/02/cloudwatch-database-insights-rds-databases/
本サービスを利用することで、通常のAmazon CloudWatchだけでは難しい、詳細なDB情報を取得することが可能になります。現時点ではOracle Database@AWSには対応しておりませんが、将来的に対応した場合有力な選択肢の1つになると思われます。
いかがでしたでしょうか?
オラクル社やAWS社のイベント/セミナーでもOracle Database@AWSの話題が取り上げられ始められており(筆者も参加しました)、多くの参加者が参加しているのも目の当たりにしました。やはり本サービスの注目度は高く、国内リージョンでの提供が始まったタイミングでは大きく盛り上がるのではと想像しています。
これからも本サービスの最新情報や利用するための準備事項、詳細なメリットなど様々な情報を発信していきますので、ぜひご期待ください!
では、次のブログ記事でお会いしましょう!
|
|
~アーキテクチャから運用・使い分けポイントまでご紹介~
2024年に発表され、限定プレビューが開始されているOracle Database@AWSについて、現時点で公開されている情報を整理して、サービスの概要や基本アーキテクチャ等をご紹介します。
さらに、Amazon RDSやOracle Database on EC2等他のOracle Database利用方法との使い分けポイントもご紹介。クラウド環境でのOracle利用を包括的に学べますので、ぜひご参加ください!
【日時】 2025年4月24日(木) 14:00~15:00
【プログラム】
1.Oracle Database@AWSのサービス概要の紹介
2.アーキテクチャ&運用検討ポイントの紹介
3.Oracle Database利用における他の方法との棲み分けポイントの紹介
4.Q&A

|
|---|
2015年にアシストに入社後、Oracle DatabaseやOracle Cloudを中心としたフィールド技術を担当。
導入支援だけではなく、最新機能の技術検証も積極的に実施。社内外のイベントにて発表も行っている。...show more
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
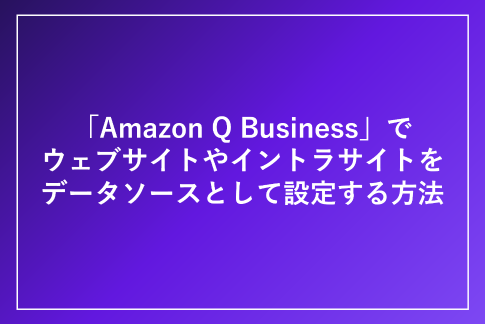
この記事ではAmazon Q Businessでウェブサイトやイントラサイトをデータソースとして設定する方法についてご紹介します。
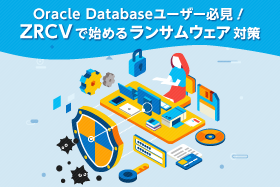
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。