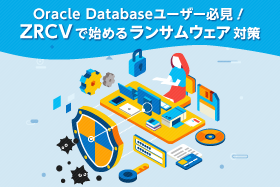
- Oracle Database
- Oracle Cloud
Oracle Databaseユーザー必見!ZRCVで始めるランサムウェア対策
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。
|
|
Oracle Cloud Infrastructureでは、コンピュート・インスタンスなどのリソースに対して、モニタリング機能がデフォルトで有効となっており、例えばコンピュート・インスタンスのCPUやメモリの使用率、ディスクI/O、ネットワーク転送量などがグラフ表示されます。
今回は、モニタリング機能のしくみと、コンピュート・インスタンスの簡単な監視方法を紹介します。
モニタリング機能は、監視項目をあらかじめ定義した「メトリック」を使用してリソース監視を実施します。
メトリックを使用することで、ユーザーは「どの項目をどのように監視すれば良いか」という点を考慮する必要がなく、すぐに監視を実行できます。
サービス・メトリックのページから、メトリックをグラフ形式で確認できます。
※サービス・メトリックのページを開くためには、コンソールメニューから、
[モニタリング]→[サービス・メトリック]をクリックします。
対象のコンパートメントを選択し、メトリック・ネームスペースで
「oci_computeagent」を選択します。
|
|
グラフは、[開始時間]と[終了時間]を変更することで表示範囲を変更することが可能です。また、[QUICK SELECTS]から過去または未来90日分のデータを確認することも可能です。
|
|
アラームの定義を作成することで、メトリックの値がしきい値に抵触した場合にアラームを発行して、APIから通知、またはメールから通知を行うことが可能です。
ここからは、一例として、CPU使用率が90%以上となった場合にメール通知する設定方法を紹介します。
まずは、メール通知先の設定を行います。
1.コンソールメニューから、[アプリケーション統合]→[通知]をクリックします。
|
|
2.[トピックの作成]をクリックすると、作成ページが開きますので、[名前]と[説明]を入力して[作成]をクリックします。
※今回は、名前に「Monitoring_Topic」、説明に「Monitoring_Test」と入力しました。
|
|
|
|
3.作成したトピック名のリンクをクリックし、[サブスクリプションの作成]をクリックすると作成画面が開きますので、[プロトコル]の選択と[電子メール]を入力し[作成]をクリックします。
※プロトコルはデフォルトの「電子メール」を選択し、通知先の電子メールのアドレスを入力します。
|
|
|
|
4.設定したメールアドレスにOracle Cloudから確認メールが届きます。
メール内のURLをクリックすると、Subscription confirmed のページが表示されます。
ここまでが、メール通知の設定です。
続いて、アラーム通知の設定を行います。
1.コンソールメニューから、[モニタリング]→[アラーム定義]をクリックします。
|
|
2.[アラームの作成]をクリックすると、作成ページが開きますので、設定に必要な項目を入力して[アラームの保存]をクリックします。
※今回は、以下のように選択および入力しました。
アラーム名:Monitoring_Alarm
アラームの重要度:デフォルトの「クリティカル」
メトリックの説明
- コンパートメント:メトリックのあるコンパートメント
- メトリック・ネームスペース:oci_computeagent
- メトリック名:CpuUtilization
- 間隔 - 1m
- 統計 - Mean
メトリック・ディメンション
- ディメンション名:resourceId
- ディメンション値:監視対象インスタンスのOCID
トリガー・ルール
- 演算子:次より大きい
- 値:90
- トリガー遅延分数:5
宛先
- 宛先サービス:Notification Service
- コンパートメント:作成した通知トピックのあるコンパートメント
- トピック:作成したトピック名
ENABLE THIS ALARM:チェックを入れる
|
|
|
|
|
|
|
|
3.作成したアラームが有効であることを確認します。
ここまでが、アラーム通知の設定です。
今回の例では、CPUの使用率が90%以上となった場合、以下のようなメールが5分おきに設定した通知先に届きます。
メール内容の表示が、HTML形式とプレーンテキスト形式で少し異なります。
どちらの形式の場合においても、上段にはアラームの設定内容が記載されます。
■HTML形式メール
|
|
■プレーンテキスト形式メール
|
|
今回は、モニタリング機能について紹介しました。
モニタリング機能を使用すれば、監視ツールの導入やツールの初期設定など不要で、CPUやメモリといったリソース監視や、ディスクI/Oやネットワーク帯域といったハードウェア観点の監視が、どなたでも簡単に実施できます。
以下マニュアルも併せてご参照のうえいただき、モニタリング機能を活用いただければ幸いです。
モニタリングの概要
https://docs.oracle.com/cd/E97706_01/Content/Monitoring/Concepts/monitoringoverview.htm
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
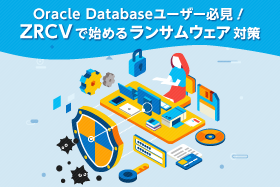
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。

今年もオラクル社の年次イベント「Oracle AI World 2025」が開催され、アシストからも11名の社員がラスベガス現地で参加しました。 本記事では「Oracle AI World 2025 視察記」として「Oracle AI World 2025のハイライト」と「アシストの注目ポイント」を、Oracle AI World 2025全体の雰囲気とともにお伝えします。

データベースの環境準備に時間を要していませんか?OCI BaseDBのクローン機能なら、検証環境を30分未満で作成可能です。本記事では、実際の操作手順から開発・テストでの活用法、コストやIP変更などの注意点までを画像付きで徹底解説します。