
- Oracle Cloud
これで安心!OCVS環境とオンプレミス/OCIリソースを繋ぐための必須ネットワーク設定ガイド
OCVSのネットワーク設定はこれで完璧!初心者でも分かりやすいよう、OCIリソース、オンプレミス、Oracle Services Network、インターネットへの接続をステップバイステップで解説します。
|
|
以前の記事で、Oracle Exadata Database Service on Exascale Infrastructure(エクサスケール。以下、ExaDB-XSと表記)の小規模利用、スモールスタートが可能、柔軟なスケーリングといった特徴とメリットについて紹介しました。
本記事でも引き続き、ExaDB-XSを利用するメリットをご紹介します。
今回はデータベースのストレージ領域およびI/O削減効果のあるHybrid Columnar Compression(以下、HCC)に焦点を当て、オンプレミスと比較した際のコスト優位性をご紹介します。
Index
HCCとはOracle Exadataなどで利用できる、オラクル独自の圧縮技術です。HCCには以下の特徴があります。
HCCはOracle Exadataの他に、Oracle ZFS Storage ApplianceやOracle Database Applianceなどで利用することができます。
HCCは、圧縮単位Compression Unit(以下、CU)という単位で圧縮されます。CUは複数ブロックにまたがって構成されます。圧縮は列ごとに行われるため、データの重複を効率的に削減しながら圧縮することができ、その結果として高い圧縮率を実現できます。
高い圧縮率によるストレージコストの削減に加えて、圧縮された特定の列を読み込むことによるI/O性能の向上がHCCの特徴です。
また、Oracle Exadataの機能であるSmart Scan(※)と組み合わせて利用することで、圧縮したままデータを扱うことが可能です。
HCCには以下の4つの圧縮レベルがあり、用途に合わせて選択できます。
| 圧縮レベル | CPU 負荷 |
説明 | 対象例 |
|---|---|---|---|
| Query Low | 低 | 圧縮率は一番低い。 クエリ実行時に発生する圧縮・展開のCPU処理を優先した圧縮レベル。 |
頻繁にアクセスされるようなデータ (当日売上のデータなど) |
| Query High | 中 | 圧縮レベルの中で性能と圧縮率のバランスが取れた圧縮レベル。 | 一定の期間にアクセスされるようなデータ (月次や四半期分析のデータなど) |
| Archive Low | 高 | 圧縮率に優れた圧縮レベル。 ほとんど参照されないような表に適している。 |
長期保存を目的に保存されたデータ (数年前のログやトランザクション履歴など) |
| Archive High | 高 | 圧縮率が最も優れた圧縮レベル。 まったく参照されないような保存データが適している。 |
法的な保存要件で保存されたデータ (数年前のログやトランザクション履歴など) |
これら4つの圧縮レベルを見ると、圧縮率が高くなればなるほど、CPUの負荷も大きくなります。Archive LowとArchive Highの圧縮レベルはストレージ削減を重視した圧縮レベルです。これらの圧縮レベルを使用する表やパーティションでは、更新処理時には圧縮されたデータの展開処理によるCPUの負荷が高くなり、データベースの性能に大きく影響します。
次は、前述の内容も踏まえてHCCの利用に適したケースをご紹介します。
圧縮単位と圧縮レベルの項目で述べたとおり、以下のような特徴を持つケースがHCCの活用に向いています。
HCCで圧縮したデータに対して、Oracle Exadata固有の機能であるSmart Scanを直接利用できます。その結果、ストレージコストとI/Oの削減を同時に実現できます。つまり、HCCとSmart Scanを同時に利用できるOracle Exadata上で稼働しているワークロードが適しています。
これにはOracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)上のExadata Database Service on Dedicated Infrastructure(以下、ExaDB-D)やExaDB-XSも含まれます。
圧縮レベルの説明でも触れたように、圧縮率が高くなるにつれて、データ更新時に圧縮されたデータの展開処理が発生し、CPU負荷が相対的に高くなります。このため、更新処理が少なく、主に保存や読み取りが中心となるワークロードがHCC圧縮方式の採用に適しています。
ここまで、HCCの機能と適するワークロードをご紹介しました。
最後に、ストレージコストが削減できるという、クラウド環境でHCCを利用する大きなメリットをご紹介します。
このメリットの恩恵を最も受けることができるサービスが、ExaDB-XSです。
ExaDB-XSは共有インフラストラクチャであり、クラウド環境で最も低コストでExadataのインフラストラクチャを利用できます。また、ExaDB-XSのストレージはGB単位の従量課金制(※)です。そのため、筐体を購入するオンプレミス環境やストレージサーバーを専有するExaDB-D環境と比べて、データ圧縮によるストレージ容量の大幅な削減によってコストメリットが得られます。以下がそれぞれのストレージの課金体系と特徴です。
| 環境 | ストレージサイズ | 課金体系 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Exadata
・X11M ・Quarter ・HCモデル |
396TB~ | 定額 | ストレージの利用状況に関わらず
定額のストレージコストが発生。 |
| ExaDB-D
・X11M ・最小構成 |
240TB~ | ||
| ExaDB-XS | 300GB~ | 従量
(GB単位) |
利用GB単位の従量課金制。利用した分だけが課金されるため、 初期コストが極めて少なく、 スモールスタートと必要に応じた拡張が可能。 |
その他にも、ストレージのスケーリングや運用管理の面でもExaDB-XSを利用するメリットがあるといえます。
本記事ではHCCによる高度な圧縮機能をご紹介しました。
あわせて、オンプレミスのExadata環境やExaDB-Dと比較して、ExaDB-XSならではの優位性があることをご紹介しました。
次回はExaDB-XSのスケーリングに焦点を当て、ストレージを含めた各HWリソースのオンラインスケーリング操作と検証結果をご紹介予定です。

|
|---|
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

OCVSのネットワーク設定はこれで完璧!初心者でも分かりやすいよう、OCIリソース、オンプレミス、Oracle Services Network、インターネットへの接続をステップバイステップで解説します。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
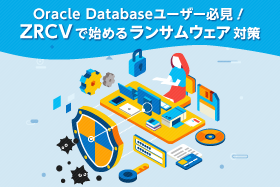
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。