
- Oracle Database
Oracle Trace File Analyzerのススメ!導入すべき理由を徹底解説!
Oracle Trace File Analyzer(TFA)は、障害時のログ収集を効率化するツールです。複数ログの一括取得や時間指定、シングル環境での導入手順まで、現場目線でわかりやすく解説します。
|
|
今回解説するのは、Oracle Exadata Database Machine(以下、Exadata)です。
Exadataは2008年に初代モデルがリリースされ、世界中でデータベース基盤として活用されています。オンプレミスだけでなくクラウドでも利用可能で、新バージョンがリリースされる度に進化を遂げています。
今回はExadataブログの第1回として、「Exadataって結局何?」という方に向けて、概要を3分でお伝えしていきます。
Index
ExadataはOracle Databaseに最適化された”Engineered Systems”です。
Oracle Databaseソフトウェアとハードウェアを組み合わせたデータベース基盤として提供されています。
ハードウェアを含めて最適化設計されており、まさにOracle Databaseに特化したデータベース・マシンに仕上がっています。ハードウェアやOSの選定が不要なので、導入期間を短縮できるメリットもあります。
Exadataのハードウェアは大きく分けて3つの要素で構成されています。
なお参考までに、2021年7月現在の最新バージョンであるX8M-2の最小構成は以下の通りです。
|
図1. X8M-2 Eighth Rackの構成 |
Exadataのポイントは「ストレージ・サーバ」です!
ストレージ・サーバは単なるストレージとは異なり、CPUやメモリが搭載されています。言い換えれば、演算処理ができるストレージです。
そしてExadataは、
データベース処理の一部をストレージ・サーバ側で実行
できるということが、本記事で押さえていただきたい一番の内容です。
Exadataのストレージ・サーバーには、”Exadata Storage Server Software”というソフトウェアがインストールされています。
一般的なデータベースでは、データベース・サーバがストレージのデータを読み込んで処理します。
しかしExadataはストレージ側でも、データを処理することが可能です。
例えばデータ検索処理の場合、ストレージ・サーバが検索結果をフィルタリング処理して、必要なデータだけがデータベース・サーバに送信されます(Smart Scan機能)。
図2を見ると、データベース・サーバ側の処理が削減され、ディスクI/Oも減少していることが分かると思います。
|
図2.Smart Scanを使用した検索処理 |
データベースにおけるパフォーマンス劣化の一因としてディスクI/Oのボトルネックが挙げられます。ExadataはこのディスクI/Oと、データベース・サーバ上の処理を削減することで高速なパフォーマンスを実現しています。
Exadataにはこの他にも、唯一無二の高性能データベースシステムを支える様々な高機能が搭載されていますが、あえてポイントをひとつに絞ってストレージ・サーバをご紹介しました。
データベース処理をストレージ層と分散処理するコンセプト
がExadataと他サーバの決定的な違いなのです。
ここまでで、以下の2点を説明しました。
- ExadataはOracle Databaseに最適化されたデータベース基盤
- ストレージ・サーバに一部処理をオフロードして性能向上
では実際、どれくらいパフォーマンスに優れているのか気になる方に少し事例をご紹介します。
| 事例① | 検索処理が、数分から2,3秒に! 数億件のデータからの検索処理が驚異的に短縮され、 サービス品質が向上。 |
|
| 事例② | 6時間以上かかっていたバッチ処理が、30分以内に! パフォーマンスの劣化に伴い、DB基盤をExadataに切り替え、 また10DB統合にもかかわらず大幅な性能改善。 |
|
| 事例③ | データ抽出処理が、半日から数分に! データ活用基盤をExadataに刷新したところ、10億件以上もの データからの抽出時間が短縮。 |
いかがでしょう、目を見張る事例ではないでしょうか。ハードウェア自体の性能向上も一因ですが、Exadataはストレージ・サーバを融合したコンセプトによって、これほどまでに驚異的なパフォーマンスを実現できるのです。
今回は「Exadataはストレージ・サーバに処理を分散することで高速処理を実現している」という点をフォーカスしてご紹介しました。
実はExadataには性能面以外にも、拡張性や可用性の面でも優れた特徴があります。その他の特長については今後のブログ記事で発信していく予定です。次回ブログにもご期待ください!
以下の記事でも、Oracle Exadataの情報を提供しています。本記事とあわせてお読みいただくとOracle Exadataの理解が深まります!
オンプレミスでもクラウドでも、Oracle Exadataの導入や弊社が提供する支援サービスに関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Oracle Trace File Analyzer(TFA)は、障害時のログ収集を効率化するツールです。複数ログの一括取得や時間指定、シングル環境での導入手順まで、現場目線でわかりやすく解説します。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
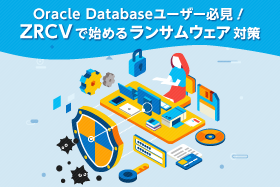
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。