
- Oracle Database
もう迷わない!SYSAUX表領域の肥大化の原因と対処法を徹底解説!
本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
|
|
前回の記事で、Oracle Cloud VMware Solution(以下、OCVS)でVMware HCX(以下、HCX)を利用するための前提となる、ネットワーク設定からサイトペアリングまでの手順をお伝えしました。
今回は、後続の手順であるサービスメッシュ作成・L2延伸手順を記載し、仮想マシンを移行できる状態、つまりHCX環境の構築完了までを説明します。
Index
前回の記事でも記載しているとおり、HCXの機能を検証する目的で、2つのOCVS環境での手順を前提としています。
環境構成図は以下のとおりです。
それでは、以下の流れでHCX環境構築手順を説明します。
1. サービスメッシュ作成
2. L2延伸
前回記事で実施したサイトペアリングの完了後は、サービスメッシュを作成します。
サービスメッシュとは移行に関するタスクや機能を管理するためのアプライアンスのことです。
移行元と移行先との接続やL2延伸の構成のためなど、HCXによる移行を実現するためにはサービスメッシュを作成する必要があります。
サービスメッシュ作成時には、事前に以下のプロファイルを設定しておく必要があります。
ただしOCVS環境では、上記プロファイルなど移行に必要最低限のものはデフォルトで用意されています。今回はデフォルトのプロファイルを利用する手順を説明します。
2-1-1. HCX Managerの管理コンソールへログインし、Infrastructure内のInterconnect > Service Meshタブ > CREATE SERVICE MESHを選択します。
2-1-2. 移行元のHCXサイト、移行先のHCXサイトが正しく設定されているかを確認し、CONTINUEを選択します。
2-1-3. 移行元、移行先のコンピュートプロファイルを選択します。今回はOCVS環境デフォルトのプロファイルを指定します。
2-1-4. 利用するサービスを選択しCONTINUEを選択します。今回は機能検証の目的で、以下のサービスを指定しています。
※Replication Assisted vMotion(以下、RAV)は複数仮想マシンをオンラインで短時間で移行する際に利用しますが、デフォルトではコンピュートプロファイルに含まれていません。そのためRAV検証時には、コンピュートプロファイルでRAVを含めるように事前に構成しておく必要があります。
コンピュートプロファイルにおけるRAVの構成手順を説明します。
1. 管理コンソールのInterconnect > Compute Profilesから対象のプロファイル内のEDITを選択します。
2. サービス選択画面で、RAVにチェックを入れて画面を進めます。それ以外のウィザードはデフォルトのままで問題ありません。
2-1-5. Uplinkネットワークプロファイルを選択します。Uplinkネットワークプロファイルは、デフォルトでHCX用VLANを利用するように指定されたプロファイルで、"[クラスタ名]-vds01-hcx”のような名前となっています。
2-1-6. NSXリソースが配置されるネットワークコンテナとアプライアンス数を選択します。ネットワークコンテナはデフォルトのOverlay-TZで問題ありません。今回はL2延伸するネットワークは1つであるため、アプライアンス数は1としています。
※アプライアンス数は、L2延伸を管理するHCX-NEというアプライアンスの数を指します。1つのHCX-NEで延伸できるネットワークは最大8つですので、オンプレミスの10環境のネットワークを延伸するなど、8つ以上のネットワーク延伸を検討している際にはアプライアンス数を増やします。
2-1-7. 追加設定画面へ遷移します。今回は何も選択せずに画面を進めます。
2-1-8. プレビュー画面へ遷移します。今回は何も選択せずに画面を進めます。
2-1-9. サービスメッシュ名を指定します。今回はInterconnect-1を指定し、FINISHを選択します。
2-1-10. サービスメッシュが作成されたことを確認します。AppliancesタブのTunnel Statusが「Up」と表示されている場合、正常に作成されたことを示します。(約20分ほどで作成が完了します)
以上でサービスメッシュの作成が完了です。
サイトペアリングの完了後、L2延伸を設定します。
L2延伸を実施することで、同じIPアドレスのままで仮想マシンの移行が可能になります。OCVSでのHCXの環境構築手順(前編)と本記事(後編)の手順を実施している場合、L2延伸を容易に設定できます。
2-2-1. HCX Managerの管理コンソールへログインし、Services内のNetwork Extension > CREATE NETWORK EXTENSIONを選択します。
2-2-2. 延伸するネットワークを選択します。OCVS作成時に"クラスタ・ワークロードCIDRオプション”で指定したネットワークは"workload-1”という名前で作成されています。今回はこのネットワークを利用します。
OCVS作成時のクラスタ・ワークロードCIDRオプションは、以下から指定します。
OCVS作成時にあらかじめCIDRを指定しておくと、後ほど手動で作成する手間を省くことができます。
2-2-3. ネットワーク設定を以下のとおり入力し、SUBMITを選択します。
2-2-4. Statusに緑色のチェックマークがついていることで、L2延伸の完了が確認できます。(約10分ほどで作成が完了します)
L2延伸したネットワークは、"L2E_[元のネットワーク名]-xxxxxx-xxxx”というような名前となります。
以上でL2延伸も完了です。
前編・後編の手順を実施することで、HCX環境の構築が完了しました。
クラスタ・ワークロード・ネットワーク設定など、L2延伸を行うための設定がOCVSでは容易であることがお分かりいただけたかと思います。
次回は構築したHCX環境を利用し、仮想マシンの移行手順を記載予定です。
どうぞお楽しみに!
\ OCVSの全体像を知りたい方はこちら /
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
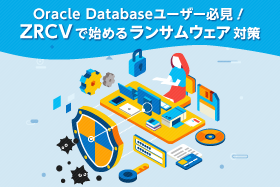
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。

本記事では、お客様の自己解決率向上のために注力したFAQ作成、および、そのFAQ作成をエンジニア育成に活用した当社ならではの取り組みをご紹介します。