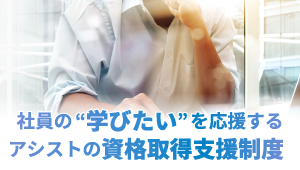
- 取り組み紹介
社員の“学びたい”を応援するアシストの資格取得支援制度
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。
~業務の合間にちょっと「教習所」に通って、ステップアップを~
「経理・法務・人事管理分野」勉強会(通称「若井教習所」)
|
|
アシストでは、語学研修補助制度、IT系の資格取得支援や自己啓発のための通信教育、各種スキル研修等含め、外部研修を採り入れながら、社員のスキルアップを支援しています。
一方、外部研修だけでなく、「社員の社員による社員のための勉強会」も盛んです。IT系企業ですから、もちろん取り扱う製品の勉強会は欠かせませんが、それだけではありません。
その一つが、「経理、法務、人事管理の担当者」が社員向けに開催している勉強会。通称、「若井教習所」です。
「今日から使える知識の習得」「社会人としての基礎力の底上げ」 を目的に2016年夏から開始し、早4回目を迎えました。参加社員からの評判も上々です。
今回はその取り組みの仕掛け人である二人に話を聞きました。
|
|
伊藤 有紘(Arihiro Ito)
|
|
|
岡 晋吾(Shingo Oka)
|
――「教習所」開催の発起人である伊藤さんに伺います。教習所開催に至ったきっかけ(経緯)、背景などについて教えてください。
伊藤:日頃、社員と業務上のやり取りをする中で、現場では「契約、経理、労務知識の不足」「社内ルールの理解不足」が原因で、「お客様との交渉にストレスが発生」「事故発生、法令抵触、契約違反リスク」「工数増大」などの課題があるのでは、と感じる場面にしばしば遭遇することがありました。そこで
・「社会人としての常識、基礎力」の底上げ
・「営業力強化、技術の品質向上、情報セキュリティ・契約違反リスク」の低減
を目的とした定期的な勉強会開催を提案した次第です。
――外部講習ではなく、社員による教習に踏み切ったわけは?
伊藤:外部講習の場合、どうしても汎用的なものになりがちです。アシストにもっと寄り添った身近な内容にしたいという思いもありました。また工数はかかりますが、社員が講師となることで、「スキル向上、価値向上」「ノウハウの創出と継承」が可能となります。何より「経営企画本部のイメージ向上、価値向上」によって、「現場のフォロー役だけではなくスポットライトを浴びる場に立ち、社員から直接フィードバックを受けることで、経営企画本部スタッフの意識を改革して、主体的に動くメンタリティを養成すること」がもう一つ真の目的でもありました。
|
|
――なるほど。この勉強会では、市ヶ谷の社内では「若井教習所」として親しまれていますが、命名の由来などあれば教えてください。
伊藤:「勉強会」だと当たり前で面白みがないので、その言葉自体がブランド力を持つといいな、と思い、旧本部統括在籍時の私の上司でもあった若井さんというネームバリューのある方の威光を利用して社内浸透を狙いました。若井さんは本部統括部の前は技術、営業と永年活躍され、社内で知らない人がほとんどいないですから。現在では、「教習所」という名前で市ヶ谷オフィスでは通じるようになったかなと思います。
――はい。すっかり「若井教習所」で浸透しています。さて、社内ですべて社員の手作りというわけですから苦労も多いと思います。運営上で配慮している点、心がけていることはありますか?
岡:教習所は、自主参加形式を取っており、社員は、タイムテーブルから、希望の講座を選んで申し込みを行います。ですので、参加する社員のモチベーションは高いです。その期待に応えるためにも、一方的な説明になってしまってはつまらないし、聴いている側も飽きてしまうので、講師と受講者双方で対話しながら進めていくやり取りができるような形の講義を心がけています。また、できる限り多くの方にご参加いただけるよう、講義の時期や時間帯については、繁忙期を避けたり、昼と夜の時間帯をバランスよく取ったりなど考えています。
|
教官のイラスト入り「カリキュラム」と経理、法務、人事の3分野にわたる豊富な「講義内容」。 |
――確かに小さなお子さんを持つ営業アシスタントさんにとっては、日中開催のプログラムはとても参加しやすいと思います。講義内容で工夫されている点はありますか?
岡:「誰にでもわかりやすく」という観点で、初学者でも理解できるような平易な説明をするようにしています。講師陣はそれぞれの専門分野の知識を持っていて、それを社員の方と共有するわけですが、無意識に専門用語を使ったり、知識がある前提での説明をしてしまいがちになるので。講義資料の概案を作った後、全体の流れの整理をして、受講者の立場で無理なく理解できるかをチェックするようにしています。
伊藤:法務の契約系の講義は難しい内容になりがちなので、例えば、前半にクイズ形式でできるだけ楽しく契約のことを知ってもらえるプログラムにしています。今まで誤解していたり、間違えて覚えていたことに気付くきっかけにもなります。後半は、アシストの契約類型各契約の「まずはここだけ確認しよう!」というポイント、実際に起きた社内外の事例を紹介するなど、工夫をしています。また講義後に、講義内容に関するアンケートに加え、今後受講してみたいテーマを聞くなど、次回以降の講義内容含め要望を可能な範囲で反映するようにしています。また今回から案内資料に講師のイメージ・イラストを加えるなど、より親しみを感じてもらえる工夫もしています。
|
|
|
|
単なる講義タイトルだけでなく教官のイラストを会場入り口に添付することで、親近感が増すから不思議です。講義も手作りのパウチ資料も活用し、わかりやすく解説。 |
――参加社員からの反響はいかがですか?
岡:参加された社員の反応は上々です。過去のアンケートより、主なものを抜粋しますと、以下のとおりです。
|
|
――実施しての効果はいかがでしたか?
岡:教習所を始めたのは、私が中途入社して1年程の頃でしたが、講義を通じて顔と名前を知っていただけた社員の方が多くいます。そういう方とは、別の業務で協力をお願いしたり、情報交換できたりなど、社内でのネットワークを広げる上でも良い効果が得られたと思います。
――素敵な副次効果ですね。他に何かエピソードやご苦労話などありますか。
伊藤:講義資料の作成では苦労しました。講師たちは皆、短い講義時間内でたくさんのことを伝えたいという気持ちの表れからか、資料内に盛りだくさんの情報を埋め込もうとするため、資料の文字がどうしても小さくなりすぎてしまって大変でした。また読む資料と見る資料の違いを意識してもらうことに苦労しました。PCで見るのではなく、モニターで見ることを意識するために、資料レビューでは、本番と同じ環境で行い、文字が多いスライドは「漢文」とか「お経」とか散々言われ、ダメ出しの嵐でしたね。
|
今期の教習所プログラム内容について、振り返りミーティング中の教官たち。真剣な面持ちで次回のプログラムに向けての打ち合わせを実施しました。 |
――今後の展開や予定などあればぜひお願いします。
伊藤:現在は本社のある市ヶ谷限定で行っていますが、各地区にも展開できたらと考えています。社員の要望があれば各地へ出向いて、出張講義を実施してもよいかもしれないですね。
――最後に若井教習所に対するお二人の熱い想いを是非お願いします。
伊藤:回を進めるごとに、全体の参加申込者数は増えており(今期は延べ100名を超え)、アンケートによる満足度も上がっています。毎回参加くださるリピーターもついており、今後も経営企画本部のサービスとして、社員とその先にいるお客様の満足度向上のために続けていきたいと思っています。
岡:教習所を始めてみて、アシスト社員の学習意欲は予想以上に強いと感じました。今の分野やメンバーにこだわらず、社員同士で知識やノウハウを共有する取り組みがどんどん拡がっていけばよいと思います。
――アシスト社員のスキルアップのため、今後も教習所を是非、継続していただくことを切に希望しています。次の教習所講義内容も楽しみにしています。
|
――(若井教習所所長より一言)教習所開催への期待と教官の皆さんへのメッセージをお願いします。
|
経営企画本部共通サービス統括部 若井 久晴 |
|
|
|
|
|
今期の教習所も無事終了。教官の皆さん、本当にお疲れ様でした。 |
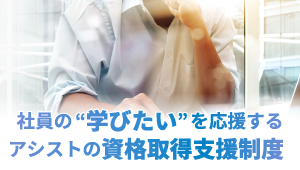
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。

アシストは、2024年2月よりオンライン学習プラットフォーム「Udemy」を技術者向けに導入しました。今回は、導入の目的や利用者の声をご紹介します!

アシストは社員の貢献を「業績報奨金」などのインセンティブ制度で還元し、社員旅行や食事会を通じてチームワークや組織の一体感を醸成しています。「個人よりチームプレーヤー」を重視し、社員主体で運営される交流施策が特徴です。