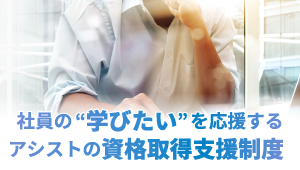
- 取り組み紹介
社員の“学びたい”を応援するアシストの資格取得支援制度
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。
|
座談会開催日時:2017年2月10日 |
前回の記事「コンタクトセンター検定とはいったい何?合格した社員にいろいろ訊いてみた」に続いて「サポートセンター(略記:サポセン)の知られざる裏側」をご紹介しますす。
期初※1に開かれるサポセンのキックオフミーティングでは、高い功績を上げたチームには「貢献賞」が、個人には「敢闘賞」が贈られ、その栄誉が讃えられます。今回は2016年3期の活躍により「敢闘賞」を受賞したJP1サポートチームの若手ホープに、なぜ多くの問い合せ対応をこなしつつ、お客様からの高い評価をいただいたのか、色々訊いてみました。
※1 アシストは1~4月、5~8月、9~12月の3期制
JP1サポート担当 引間(ひきま)
2013年入社。Oracle Databaseの技術担当を経て、2014年10月にJP1サポートチームに異動。約半年間にわたって統合運用管理ツールJP1やサポートの知識習得を行い、2015年4月から資産管理ツールであるJP1/NETMおよびJP1/ITDMのサポートを担当。
学生時代は経営学部でビジュアル・マーチャンダイジングを学び、バスケサークルではセンタープレイヤーを務めた。現在の趣味はバイクツーリングで、昨年、念願だった大型二輪免許を取得。
JP1サポートチーム 技術部長 矢農(やのう)
引間を敢闘賞に推薦したメンバの一人。市ヶ谷JP1サポートチームの責任者。
──まず始めに、どのような功績に対して敢闘賞が贈られたのか、矢農さんからお聞かせください。
矢農:
引間さんはJP1のサポート担当になってわずか2年ですが、前期(2016年3期)に対応したサポート件数がチーム最多だったことに加え、引間さんが対応したお客様からのアンケート結果がすべて「100%満足」という高評価をいただきました。また、日々のサポート対応だけでなくAWSC※2の活用推進活動を積極的に行っていることや、AWSC上に公開する技術資料を数多く作成したことが主な表彰理由です。
※2 AWSC:Ashisuto Web Support Center
アシストの全取扱製品についての問い合わせや、1万1千件のFAQおよび技術情報の検索がワンストップで行えるサポート専用サイト。年間で3万5千件を超えるサポート対応の大部分がAWSCを介して行われている。
──担当されたお客様からのご評価がすべて「100%満足」とはすばらしいですね。お客様から高いご評価をいただくために、何かの工夫や日ごろ心掛けていることはありますか。
引間:
サポセンではメールやWebでもお問い合わせを受け付けていますが、私が対応する際には、必ず電話でお客様と直接会話をして、実際に望まれていることやお問い合わせの背景、他にお困りのことはないかを確認するようにしています。
──メールやWebで寄せられた内容と、実際のお客様のご要望が違っていたことがあったのでしょうか。
引間:
はい。例えば、メールで「管理対象であるクライアントPCの情報を手動で登録したい」というお問い合わせをいただいたのですが、電話で詳細をお聞きしたところ、「実はクライアンPCの情報を自動で収集/登録する機能がうまく動かないので、仕方なしに手動で登録しようとしている」ということがわかったケースがありました。お客様が確認されたかったことは「手動の登録手順」ではなく、実は「自動の情報収集/登録機能のトラブル解決」でした。もし、メールだけで判断して、手動の登録手順をお伝えしていたら、お客様が抱える課題の根本的な解決はできませんでした。
|
JP1サポート担当 引間 |
──毎回必ず電話をするようになったのには、何かきっかけがあったのですか。
引間:
私はメールなどの文面からその背景を読み取ることがどうも苦手で、サポート担当になったばかりの頃、お客様とのやりとりで認識が噛み合わず、お客様にご迷惑をおかけしてしまったことが何度かありました。お客様にご負担をおかけしただけでなく、自分自身の心理的な負担も大きくなる一方でした。そこで、なんとかしなければと考えた末に、お客様に直接電話を差し上げて「この認識で合っていますか」「実際にお困りのことはどのようなことでしょうか」とお聞きするようにしたところ、認識のずれに関する悩みがかなり解消されたのです。
矢農:
引間さんのサポート対応を見ていると、お客様との認識合わせや、これから調査する内容について1つひとつきちんと合意形成をしていることがわかります。そのこともあってか、お客様からのアンケート回答では「サポートが丁寧」と評価いただくことが多いです。
──お客様からいただいたお言葉で印象に残っているのはどんな内容でしたか。
引間:
1年ほど前まで私がサポートを担当していて、トラブル収束後にいったん担当を外れたお客様がいらっしゃいまして、今年に入ってから再び私が担当することになりました。1年ぶりにご連絡を差し上げた際に、そのお客様から「ずっと引間さんに対応してもらえるのが一番助かる」とおっしゃっていただきました。これ以上のお褒めの言葉はないと思い、本当に嬉しかったですね。
──それはとても嬉しい瞬間ですね。では次に表彰理由の2つ目であるAWSCの活用推進活動についてお聞かせください。
引間:
サポート専用のWebサイトであるAWSCを活用することで、わざわざサポセンにお問い合わせいただかなくても、お客様が必要な情報をすぐに取得できるという大きなメリットがあります。より多くのお客様にAWSCをご利用いただくために、私に何かできることはないかと考え、お問い合わせをクローズするタイミングで「お客様の業務でお役に立ちますよ」とAWSCをご案内することを始めました。
──クローズのタイミングだとお客様とも打ち解けているので、付加価値のある情報をご案内し易いですね。
引間:
そうですね。あるお客様からは「AWSCのFAQで知りたいことがわかるので、問い合わせる手間が省けて助かる」というお言葉をいただきました。また、AWSCのID登録手順を電話で積極的にご案内し、その場でご登録いただいたお客様も何名かいらっしゃいます。
矢農:
引間さんは、積極的にお客様にAWSCをご案内することに加え、AWSCへの技術情報の登録にも積極的に取り組んでいます。これらはお客様の満足度向上につながる手本となる活動ですので、今期からチーム活動として広めていく予定です。
──サポート業務のコアとなる「技術スキル」の習得について、工夫されていることや、心掛けていることはありますか。
引間:
先輩方が対応されたサポートのログなどを参照し、自分で実際に検証作業を行って技術的な知識を取り込むようにしています。試験の過去問を研究するようなイメージです。この検証作業を通して知識の幅が広がったと実感でき、サポート対応の際に「当たりがつく」という経験が多くなってきました。
また、上長からよく言われる「振り返りが大事」ということを実践するよう心掛けています。サポセンに異動したての頃は、仕事に不慣れだったため、1つの問い合わせが終わったら、振り返る余裕もなく「やって終わり」という感じでした。でも今は、後から振り返って「どうすればもっと早く回答できたのか、工数を減らせたのか」ということを考える余裕が出てきました。
また、仕事の振り返りは、自分1人で行うのではなく先輩方に協力を仰ぎ、「先輩だったらどのような対応をしたか」を聞いて、それを自分の次の対応に活かしていくということを実践しています。
矢農:
先輩社員を巻き込んだ仕事の振り返りについては、誰かに言われたからではなく、引間さんが自ら先輩社員にお願いして始めています。各人のスキル習得にも非常に有効なので、チーム全体に取り入れてはどうかと考えています。
──最後に、今後もっとお客様へのサポート対応を良くしていくために、何かアイデアや考えがあれば教えていただけますか。
引間:
サポセンメンバーの場合、お客様とのやりとりは通常電話やメールが中心で、直接対面でお話しする機会がありません。そこで、例えばサポセンを利用されているお客様が来社する際にご挨拶させていただくなど、直接お会いできる機会ができるともっと良くなると思います。一度でもお会いしたことがあれば、お互い親近感がわき、コミュニケーションがよりスムーズになるのではないかと思います。
──矢農さんから引間さんに、何かアドバイスはありますか。
矢農:
ぜひ、このまま突き進んでいってください。
|
JP1サポート担当 引間(左)、JP1サポートチーム 技術部長 矢農(右) |
後日、改めてお客様からのアンケート回答を確認したところ、引間さんのサポートに対して「大変丁寧な対応」「環境に合った細かなアドバイスが助かる」「気軽に問い合わせができてありがたい」といったコメントをいただいています。メールだけでなく直接会話すること、1つひとつきちんと意識合わせを積み重ねていること、これらシンプルですがコミュニケーションの根幹となる活動を愚直に続けることが、お客様からの高い評価につながっているようです。
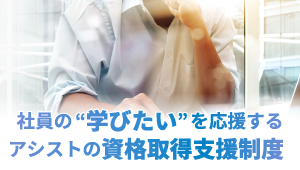
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。

アシストは、2024年2月よりオンライン学習プラットフォーム「Udemy」を技術者向けに導入しました。今回は、導入の目的や利用者の声をご紹介します!

アシストは社員の貢献を「業績報奨金」などのインセンティブ制度で還元し、社員旅行や食事会を通じてチームワークや組織の一体感を醸成しています。「個人よりチームプレーヤー」を重視し、社員主体で運営される交流施策が特徴です。