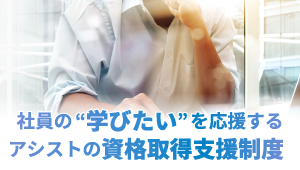
- 取り組み紹介
社員の“学びたい”を応援するアシストの資格取得支援制度
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。
|
|
アシストは、2024年2月よりオンライン学習プラットフォーム「Udemy」を導入しました。現在は新人の技術研修に活用されているほか、多くの技術系社員が自己研鑽の手段として利用しています。
今回はUdemyの導入プロジェクトをリードした谷津さんへのインタビューを実施し、Udemyの活用イメージや導入背景、運用ルール、導入後の効果などをお聞きしました。
また、普段からUdemyを活用している大濵さんと中島さんの二人にもお話を聞き、日頃のUdemyの活用方法、役に立った講座、さらには学びを重視するアシストのカルチャーについて、日頃から感じていることを語ってもらいました。
|
谷津 宏和
|
|
|
大濵 杏菜 |
|
|
中島 えみ |
|
── まずは、アシストにおけるUdemy活用の全体像を教えてください。
谷津:
アシストでは2024年2月からUdemyを導入しています。現在もヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルに関する研修は人事部主導で実施していますが、テクニカルスキルを習得するための技術研修についてはUdemyを入り口にしています。イメージとして、まずはUdemyで基本的な技術を学習してもらい、それ以上の知識・スキルを学びたい際には個別の研修を提供する流れとなります。
実際のUdemyの運用については、8つのコース(ラーニングパス)を設計し、技術分野ごとに学ぶべき講座を分かりやすい形にして提供しているほか、初級・中級などレベル別のコース設計も行っています。新人・若手は、Udemyのコース受講を各自の目標設定に組み入れ、上長とすり合わせながら学んでいきます。中級者・上級者については、自己研鑽の一環として自らコースや講座を選択し、自分の業務やキャリアに必要なテクニカルスキルを学ぶことができます。
ちなみにアシストでは、会社のデバイスだけでなく、PCやタブレット、スマホなど個人のデバイスでもUdemyを利用できる設定にしているため、場所や時間を選ばずに学習することができます。
── アシストがUdemyを導入した背景についても教えてください。
谷津:
Udemyの導入背景は大きく3点あります。1点目は、中期経営計画で掲げられた「社員の育成と成長」の実践。2点目は、技術スキル習得への危機感。3点目は、研修費の肥大化と研修機会の不公平感です。
1点目については、アシストの技術管掌役員が中心となって「技術のスペシャリストを目指す」というスタンスを打ち出し、それが中期経営計画にも組み込まれ、会社全体としての注力ポイントとなりました。それに応える形で「社員の育成と成長」の実践につながる様々なツールを検討し、常に新しい研修やコースが更新されているUdemyを選びました。また、ヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルに関する研修は人事部主導で実施していたものの、テクニカルスキルの研修については配属先の部門任せになっていたので、まずはここを支援したいと考えていました。
2点目の技術スキル習得への危機感ですが、ここ数年で生成AIが一気に普及するなど、技術革新のスピードが上がり続けており、経営陣や技術者は「今後は製品中心のビジネスだけでは立ち行かなくなる可能性がある」という危機感を持っています。また、経営陣自らが「モノからコトへ」と言っているように、「単なる製品技術者ではなく、プロの技術者として今後のキャリアを考えてもらいたい」というメッセージを発信しています。このような危機感に基づく新しいスキルの習得意欲に応えることも、Udemyの導入背景の一つとなっています。
3点目の研修費の肥大化と研修機会の不公平感ですが、新しい技術が次々に生まれる中、必要な研修一つひとつを社員に個別受講してもらうには多大なコストが掛かります。また、マネージャクラスやベテラン社員が研修を受けたいと考えても、費用の関係で受講しづらい状況がありました。このようなコスト面での課題解決にもついても、Udemyが効果的であると考えて導入を決めました。
|
|
── Udemyの活用により、どのような状態を目指しているのでしょうか。
谷津:
生成AIをはじめ、ITやテクノロジーが進化するスピードは年々加速していますが、技術で遅れをとることはアシストにとって致命傷になります。しかし、会社主導による技術者育成にも限界があります。
そのため会社としては、社員に対して「ITの進化に対応できるよう、自ら学んで、自ら成長できる技術者になってほしい」というメッセージを発信しています。Udemyはそのような成長の機会を社員に対して公平に提供するツールの一つという位置付けです。このような考え方をベースに、Udemyの導入によってアシストを自ら学ぶ人にあふれている状況にし、技術者一人ひとりがプロフェッショナルな技術者として活躍できる状態にすることが、私たちの目標であり、会社としての目標です。
── Udemyの導入に際して工夫したことがあれば教えてください。
谷津:
導入当初は「盛り上げ隊」というチームを編成し、Udemyの活用ルールやFAQ、Tips、講座情報などをまとめた社内ページを作成したり、社内メルマガでの発信、使い方の勉強会、使用者が感想を共有する場を企画したりするなど、様々な施策を実施しました。
運用面について、社員のUdemy利用には3つの原則を設けています。1点目は、Udemyは自己研鑽の手段として利用し、原則業務外での利用とすること。ただし、業務に直結するUdemyの利用であれば、業務時間内の利用も認めています。2点目は、業務の優先度は「お客様対応」>「MTG・検証等社内業務」>「Udemy」とすること。3点目は、Udemyはその視聴自体が成果ではなく、成果創出のためのプロセスとして活用すること。簡単に言えば、「Udemyを視聴しただけで評価されるわけではない」ということです。
── 大濵さんにお聞きします。普段はUdemyをどのように活用されていますか?
大濵:
資格取得のために一つの技術を最初から最後までしっかり学びたいときに活用しているほか、興味がある分野について「まずは大まかな概要を知りたい」と思ったときにも気軽に活用しています。資格対策本などは高価ですが、Udemyは無料で使えるのでコスト的にも助かっています。また、私は普段の業務でクラウド製品を扱っており、Udemyではアニメーションやイラストで分かりやすく解説してくれるので、理解を深めやすいと感じます。
|
|
── 特に役立った講座・コースがあれば教えてください。
大濵:
私自身の業務と直結しているOCIやアマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)などのクラウド関連講座は全体を通して視聴しました。初心者向けの内容も多く、業務で使用する公式ドキュメントを読み解くための基礎知識が得られたほか、自分が担当する製品だけでなく別製品についても効率よく学べるので、各製品の強み・弱みを理解する上でも役立ちました。
また、「アシストテクニカルフォーラム」というお客様向けに技術情報や現場事例をお伝えするイベントに登壇した際には、UdemyでPowerPointの使い方を学びながら資料を作りました。Udemyは、技術系だけでなく資料作成やファシリテーションに関する講座も充実している点がありがたいです。
── Udemyを活用する上での工夫や、自分なりの使い方はありますか?
大濵:
PCで視聴することもありますが、スマホやタブレットといった私用のデバイスでも視聴できるので、ラジオ感覚で何か別の行動をしながら気軽に聞いています。防水ケースに入れたスマホをお風呂に持ち込んでUdemyの講座を流したり、料理をしながら講座を聞いたりすることもあります。
── Udemyを活用する中で、部署内で工夫している取り組みはありますか?
大濵:
私の部署では「今週の推しUdemy」という取り組みがあり、メンバーが週替わりでオススメの講座を紹介しています。講座ごとの概要や対象者はもちろん、実際に講座を受けた人の感想や「推しポイント」も共有してもらえるので、自分が知らなかった新しい講座と出会うきっかけにもなっています。
── 中島さんにお聞きします。アシスト入社以降、学び直したい・深めたいと感じ、Udemyを活用した場面はありましたか?
中島:
GitHubの使い方や仕組みについて解説した講座を視聴し、社内プロジェクトの活動に活かす事ができました。使い方や仕組みの概要は実践を通して理解しましたが、講座を視聴することでサービスが生まれた背景や仕組み、注意点などに関する理解を深めることもできました。サービスやツールが生まれた背景まで知っていると、キャッチアップの速度が上がりますし、応用の幅も広がるので、効果的な学びにつながると思います。
|
|
── 日頃からよく活用しているコースや、効果を実感したコースはありますか?
中島:
普段は資格試験の対策講座を利用することが多いです。実際に利用したのはSnowflakeのSnowPro Core認定試験やAWS関連など、クラウド関連の資格講座です。これまでもSnowflakeやAWSを活用する機会はありましたが、業務で触れる機会が少ない機能についてもキャッチアップすることができました。その後、AWSサービスを使った検証業務に携わる機会がありましたが、必要な設定・構成についてのイメージが湧き、作業もしやすかったです。
── Udemyを活用する上での工夫や、自分なりの使い方を教えてください。
中島:
Udemyの試験対策講座には対策コースと演習モードがあります。対策コースは時間内に全ての設問を解き切るコースですが、演習モードは1問ずつ解答や解説を確認できるため、通勤中の隙間時間を利用して学んでいます。
―― Udemy活用について、ほかの社員の取り組みを参考にしたことはありますか?
中島:
社内の情報共有ツール(Confluence)に書かれた「合格体験記」を、とてもありがたく活用しています。資格取得の試験に合格した方々が「どのように勉強したか」「どのような問題が出たのか」「Udemyのどの講座を利用したか」といった情報を自発的に記載し、合格体験記の形で社内共有しているので、試験を受ける際の参考になりました。
── Udemy導入後、全社的な効果・変化について実感されていることがあれば教えてください。
谷津:
Udemy導入後、資格取得にチャレンジする社員が大幅に増え、AWSの資格取得数が延べ400を超えました。新人・若手はもちろんですが、今まで研修を受けづらい立場にいたマネージャ陣やベテラン社員からも「Udemyの講座を受けて資格が取れた」という声が挙がってきています。
また、大濵さんの部署で実施されている「今週の推しUdemy」や、中島さんが話してくれた「合格体験記」など、各部門や社員一人一人が自主的にUdemyの講座や活用方法を共有し合う取り組みを進めてくれています。導入当初は社内でのこのような広まり方を想定していなかったので、とても嬉しく思っています。
── Udemyに関して伺う中で、アシストには学びを共有し合う環境があることも伝わってきました。学びを重視するカルチャーがあると言えますが、大濵さんと中島さんはその点、どのように感じていますか?
大濵:
会社全体に「学びたい」「成長したい」という気持ちを尊重し、応援してくれる風土があると感じます。アシストの新入社員のほとんどが情報系以外の学部の出身者ですし、私自身も文系出身です。私たちのようなIT未経験者を温かく迎え、基礎の基礎から教え、育てていく伝統も、学びと育成を重視するアシストの魅力の一つだと思います。周囲の方々のサポートも手厚く、入社4年目の今でも「放置されている」と感じたことは一度もありません。
中島:
前職では「学習して共有する」という文化を感じる機会は少なかったですが、アシストでは皆が学習し、皆が共有しているので、自然と「自分も学んだことを共有しよう」という気持ちになります。社内に共有されている情報も多いですし、複数のツールを横断して検索できる「社内情報検索プラットフォーム(Glean)」もあり、アクセシビリティも高い環境です。勉強会なども定期的に開催されており、会社全体に新しい知識・スキルを学ぶことや、有益なノウハウの共有を大事にするカルチャーが根付いていると感じます。
── 学ぶ姿勢を尊重する文化と学びを後押しする取り組みがかみあって、Udemyが高い導入効果を発揮できているのですね。
谷津さん、大濵さん、中島さん、インタビューへのご協力、ありがとうございました!
IT業界の変化のスピードは加速し続けており、今後は「学び続ける姿勢」がさらに重要になってくるはずです。「学びたい」「成長したい」という思いを互いに尊重し、支え合うアシストのカルチャーは、アシストの強みの一つですね。
アシストの「学びを共有し合うカルチャー」とUdemyの活用を通じて、技術者一人一人が自分らしく成長し続けられる環境がこれからも広がっていくことに、心から期待しています!
|
|
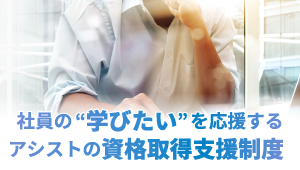
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。

アシストは社員の貢献を「業績報奨金」などのインセンティブ制度で還元し、社員旅行や食事会を通じてチームワークや組織の一体感を醸成しています。「個人よりチームプレーヤー」を重視し、社員主体で運営される交流施策が特徴です。

2025年3月15日~16日、アシストがゴールドスポンサーとして協賛した「ICTトラブルシューティングコンテスト2024」の本戦が行われました。アシストがなぜ本イベントに協賛をしたのか、またどんなイベントなのかをご紹介します!