
- Oracle Database
もう迷わない!SYSAUX表領域の肥大化の原因と対処法を徹底解説!
本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
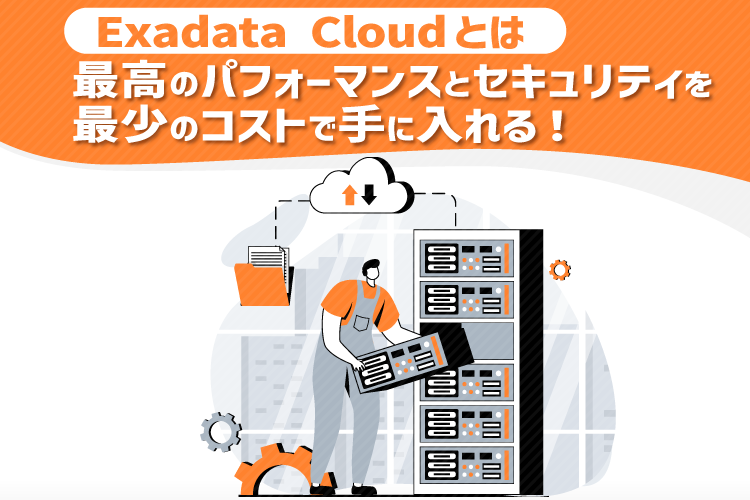
最高峰のデータベース基盤として名高いOracle Exadata Database Machine(以下、Exadata)は、クラウド上でも高速大容量なデータベースとして利用可能なことをご存じでしょうか?
本ブログではクラウド版Exadataである"Oracle Exadata Database Service(以下Exadata Cloud)"を、オンプレミスのExadataと比較しながらご紹介します。
Index
Exadataは、Oracle Databaseに最適化された超高速なデータベース基盤で、ハードウェアを含むアプライアンス製品として提供されています。
独自の機能により、他のサーバとは一線を画す驚異的なパフォーマンスを実現できる点が特色で、業種を問わず世界中のミッションクリティカルなシステムで利用実績があります。
Exadataの概要は「Exadataとは?3分で押さえるExadataのポイント」、その他、Exadataの構成、機能の詳細やパフォーマンスについての検証結果などは、ぜひ過去のブログ記事をご参照ください!
さて、今回の本題です。
アプライアンス製品として提供されるExadataをクラウドで使うとはどういうことか、イメージがつきにくい方もいらっしゃると思います。
まず、”Exadata Cloud”を利用する場合、オンプレミスと同様に筐体はお客様専用です。ただしハードウェアはオラクル社に管理され、ユーザーはハードウェアの管理を意識する必要はありません。
ユーザーはデータベースサーバを、仮想マシンのゲストOSやRAC(※)データベースとして利用することができます。詳しくは「管理範囲」で後述します。
(※)Oracle Real Application Clustersの略称
次にオンプレミスのExadataとの大まかな違いを見ていきます。
実は"Exadata Cloud"と一口に言っても、大きく2通りの利用形態があります。
|
オンプレミス
|
プライベート・クラウド
|
パブリック・クラウド
|
|---|---|---|
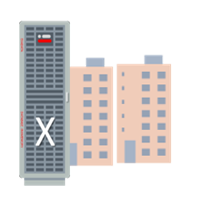
Oracle Exadata Database Machine
|

Oracle Exadata Database Service on Cloud@Customer
|

Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure
|
図1.Exadataの利用形態
ExaDB-Dは一般的なパブリック・クラウドのイメージに近い利用形態です。オラクル社のデータセンターに設置されたExadataマシンを、クラウドサービスとして利用します。
プライベート・クラウドのExaDB-C@Cを利用する場合、サーバはお客様のデータセンターに配置される点が最も大きな違いです。オンプレミスと同様に機密データを自社の管理下に置きながら、クラウドサービス固有のメリットを享受したいというニーズに応えたサービス形態です。
続いて、オンプレミス版とクラウド版のExadataを「コスト」「拡張性」「管理範囲」の3点で比較してみます。
オンプレミス版は本体価格+使用権+保守料金という料金体系のため、予算の見通しが立てやすい点が特徴です。また、有効なコア数のみをライセンスの対象とする「Capacity-On-Demand」制度があり、ビジネス拡大に応じてコア数を増やしていく、ライセンスコストのスモールスタートが可能です。
一方クラウド版はサブスクリプション型の料金体系で、使用するコア数に応じて料金が変動します。なお、ハードウェアはオラクル社の資産のため、本体価格はかかりません。
オンプレミスではコア数を増やすことしかできませんが、”Exadata Cloud”は動的なコア数の増減が可能で、例えば夜間のコア数を下げたり、繁忙期は増やしたりすることで、ランニングコストを最適化できる点が"Exadata Cloud"の特色です。
|
|
図2.”Exadata Cloud”のコア数増減
Exadataはオンプレミス版でもクラウド版でも同様に下記のような拡張が可能です。
いずれもビジネスの伸長に伴って機器を増強できる点がポイントです。
※サーバモデルによって異なる点が一部あります。
なお、前項でも述べておりますが、"Exadata Cloud"では有効コア数を増加させるだけでなく、減少させることができる点が大きな差異です。
ユーザーの管理範囲はオンプレミスとクラウドで大きく異なります。
オンプレミスはソフトウェアのみならず、ハードウェアや内部ネットワークなど、全てお客様の管理範囲です。
"Exadata Cloud"は、OS以上のソフトウェアレイヤーがお客様の管理範囲となります。ハードウェアはオラクル社の管理となるため、インフラの運用負荷を軽減し、データベースの運用に集中できる点がメリットです。
|
|
図3.”Exadata Cloud”の管理範囲
ところで、クラウドと聞くとやはり気になるのはセキュリティですよね。
クラウドシフトが難しい要因として「セキュリティの懸念」が挙げられますが、"Exadata Cloud"はセキュリティも万全です!
例えば、データベース内のデータの透過的暗号化がデフォルトで有効になっていたり、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」に登録されていたりと、非常に機密性の高いシステムになっています。
なお、セキュリティについては別の記事で詳細をお伝えする予定ですのでご期待ください!
いかがでしたか?本ブログで「"Exadata Cloud"とは何か」を少しでもお伝えできていれば幸いです。
オンプレミスの”Exadata”と"Exadata Cloud"のどちらが優れているということではなく、それぞれ適した用途・環境があります。
次回ブログではExadataのオンプレ版とクラウド版の使い分けについて着目していく予定ですのでお楽しみに!
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
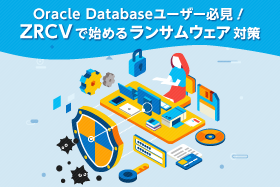
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。

本記事では、お客様の自己解決率向上のために注力したFAQ作成、および、そのFAQ作成をエンジニア育成に活用した当社ならではの取り組みをご紹介します。