
- Oracle Cloud
これで安心!OCVS環境とオンプレミス/OCIリソースを繋ぐための必須ネットワーク設定ガイド
OCVSのネットワーク設定はこれで完璧!初心者でも分かりやすいよう、OCIリソース、オンプレミス、Oracle Services Network、インターネットへの接続をステップバイステップで解説します。
|
|
オラクルの年次イベントである「Oracle CloudWorld」が、2023年9月18日から21日にわたりラスベガスにて開催されました。
アシストからもOracle Database、Oracle Cloudの技術者など9名が参加し、様々な最新情報をキャッチアップしてきました。
本記事では、基調講演での発表内容と注目のトピックをOracle CloudWorld全体の雰囲気とともにお伝えします。
Index
関連するブログ記事もぜひ併せてお読みください。
今年も昨年に引き続き、ラスベガスのホテルに併設されたコンベンションセンターでの開催でした。世界中から多くの関係者が集まるという、日本ではなかなか見られない規模のイベントです。
ビジネスイノベーションを推進する立場の方やオラクルのテクノロジーを活用する技術者が一堂に会し、その数約16,000名と、コロナ禍が落ち着いた影響からか2022年よりも増加が見られました。日本からもユーザー企業、パートナー企業から約250名が参加していました。期間中にJapan Sessionと題した日本からの参加者向けセッションが開催され、参加者同士の情報交換も行うことができました。
4日間の会期中は5つの基調講演をはじめとして約1,200のセッションが行われ、展示コーナーにも数多くのブースが出展しており、オラクル製品に関わる最新情報を存分に入手できる機会となりました。
|
|
オラクル社CEOのSafra Catz(サフラ・キャッツ)氏の基調講演では、様々な業種の企業から5名のエグゼクティブ(Uber社、Aon社、Loblaw社、TIM Brasil社、Emerson社、First Sola社)が登壇し、イノベーションへの挑戦について語りました。その中でも日本の皆様にも馴染みのあるUber社の取り組みをご紹介します。
「Uber社は配車サービスから始まり、食品デリバリーサービスへの拡張、さらにはモノの配送へと事業を展開している。このロジスティクス事業は翌日配送どころか当日配送を実現する。そのトランザクションは四半期あたりに20億。今後それをさらに倍にしていく。エンドユーザー向けサービスだけではなく、ドライバーに対するサービス提供も重要だと考えており、600万ものドライバーを事業主と見立てて、ドライバーが働きやすくなるサービス改善を繰り返している。これらのシステムを収益性を維持した状態で支えているのがOracle Cloudである。」(Uber社CEOダラ・コスロシャヒ氏)
当日配送の物流の仕組みが日本でも開始されることを期待してしまいます。
次にご紹介するのは、創業者であり、会長兼CTOのLawrence J. Ellison(ラリー・エリソン)氏の基調講演です。会場は人が入りきれないほどの満員で、その雰囲気からも注目度の高さ、ラリー・エリソン氏いまだ健在!ということが伝わってきました。
|
主なトピックは以下の2つです。
「AI は私たちが行っているほとんど全ての中心になるだろう。」
「AIにおけるOracle Cloudの優位性は、その圧倒的な処理スピードである。」
「Oracle Cloudでは、NVIDIA H100を積んだ1万6000台のコンピュータがRDMAネットワークで接続されている。Oracle Cloudの大きな利点は、どのクラウドよりも高速にデータを移動できること。データの移動に特化したRDMAネットワークをオラクルはこれまでもデータベースで使ってきた経験があり、その経験が役立っている。」
「クラウドのコンセプトは『時は金なり』。2倍速く処理できればコストは半分になる。3倍速く処理できればコストは3分の1で済む。高速処理が可能なOracle CloudでAIを構築する方が、はるかに速く、はるかに安く、はるかに経済的だ。だからこそ、NVIDIA社や、今回オラクル社がパートナーシップを結んだエンタープライズ向けAIプラットフォームのリーディングカンパニーであるCohere社は、 Oracle CloudでAIトレーニングを行っているのだ。」
ラリー・エリソン氏はこのようにOracle Cloudのスーパークラスターの強みをアピールし、低コストでより早くAIを構築できることを繰り返し強調していました。
また昨年に続き、医療分野(一昨年買収した電子カルテ(EHR:電子健康記録)大手ベンダー「Cerner社」)での取り組みや農業分野でのテクノロジーの利用、社会貢献や環境への配慮を意識した発表がありました。
マイクロソフト社とのサービス連携は数年前に始まっていましたが、Oracle CloudWorld開催直前の9月14日(日本時間9月15日午前5時)にマイクロソフト社とオラクル社から衝撃的な共同発表がありました。
Oracle Cloudが掲げる「分散クラウド(Distributed Cloud)」戦略のひとつで、Oracle Database ServicesをMicrosoft Azureで提供する「Oracle Database@Azure」(北米および欧州のAzureデータセンターから提供を開始)の内容です。
「Azureのデータセンターに『Oracle Exadata』のハードウェアを配置することで、お客様は最高のデータベースとネットワーク・パフォーマンスを享受できるようになる。」
「先週、私はワシントン州レドモンドに行き、マイクロソフトのSatya Nadella(サティア・ナデラ)CEO と素晴らしい話をした。その大きなアイデアとは、クラウドはオープンであるべきで、壁に囲まれた庭であってはならない。クラウドは相互につながっているべきだ。」
オラクル社とマイクロソフト社は、ひとつのクラウドサービスに囲い込まれることなく、オープンに複数のクラウドを使えるようになる世界を目指していることがわかりました。このOracle Database@Azureの詳細については後述します。
Oracle Cloudに関して注目すべき発表から3点お伝えします。1つ目は、ラリー・エリソン氏の発表でも言及されていた「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)Generative AI」です。
Oracle Cloud Infrastructure開発責任者のClay Magouyrk(クレイ・マグワイク)氏は、基調講演「クラウドのインテリジェントな未来を想像する(Building the More Intelligent Future of Cloud)」にて、以下の内容を発表していました。
「Rieka社、Mosaic社、NWorld社などの顧客はOCIのスーパークラスターを使用して生成AIに自社のデータをトレーニングさせ、大規模言語モデルを構築している。一例として、Mosaic社は、これをOracle Cloud上で実行することにより、パフォーマンスが50%向上し、コストが80%削減された。一般的に企業が生成AIを活用する上で、3つの障壁があり、オラクルにはその解決方法がある。」
①アクセスコントロール:
「AIがデータにアクセスするようになったら、どのようにしてテクノロジーを制御するのか?データの行き先と使用方法をどのように確認するのか?この問題を解決するためにCohere社と提携し、生成AIサービス『OCI Generative AI』を提供する(間もなくリリース予定)。分散クラウドモデルはどこでも利用でき、なおかつ顧客が自社データをどこに置くか、どの地域内で利用可能かを完全に管理することができる。つまりデータがどこでどのように使用されているかを正確に管理・把握できる。」
②経験不足:
「AIに限ったことではなく、新しいテクノロジーのトレンドが起きたとき最初は誰にも経験がない。大事なのは、それに触れてみることだ。オラクルは安全に生成AIを使える環境を用意している。」
③統合:
「生成AIを既存のアプリケーションやワークロードにどのように統合するかということ。Oracle DatabaseにおいてはCohere社と協力し、大量のデータから学習し多様なタスクに適応可能なAIモデルである「ファウンデーションモデル」と、特定の情報検索に特化したAIモデルでありテキスト生成を得意とする「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」を組み合わせることで、簡単に統合できる。」
実際に、大規模言語モデルを利用したアプリケーションを、ユーザー情報、ナレッジベース、在庫システムを始めとする多くのバックエンドシステムに接続して、対話形式で問題を調査、特定し、解決方法を導き出すデモンストレーションが披露されました。
Oracle Cloudが掲げるアプリケーションとインフラストラクチャを組み合わせた「統合クラウド(Unified Cloud)」のメリットがわかり、具体的なイメージが湧きました。今後が非常に楽しみです。
|
2つ目は「Oracle Database 23c」です。生成AI時代、どう変わったのでしょうか。
今回のOracle CloudWorldに合わせて、Oracle Databaseの最新バージョンOracle Database 23cが、Oracle CloudのBase Database Serviceにて正式リリースされたことが発表されました。この23cの大きなテーマとして「アプリケーションと開発の簡素化(App Simple)」が掲げられていました。
|
ミッションクリティカル・データベース・テクノロジー責任者のJuan Loaiza(ホアン・ロアイザ)氏による基調講演「データとアプリケーション開発の未来について(The Future of Data and App Dev)」のポイントは、「生産性の根本的な向上を可能にすること」です。
「23cでは、データソリューションを手動でコーディングするのではなく、生成することになる。これが非常に大きな全体像だ。我々はイノベーションを起こすために生成を行っていく。データ専門家(データサイエンティスト)や開発者、エンドユーザーは意図した結果を宣言するだけで、簡単にデータを取り扱えるようになるだろう。」
「非構造化データのベクトル検索とビジネスデータのリレーショナル検索を組み合わせることで、ビジネス上の問題を解決できるようになる。そのための最適な解決策として、Oracle Database 23cではデータ型のひとつとして「ベクトルデータ型」が追加される。その結果、AIの専門家でなくても通常のSQLでビジネスデータベースをベクトル検索できるようになる。これは画期的なことだ。ベクトル検索と生成AIを活用することで、エンドユーザーはデータベースに対して、自然言語で問い合わせできるようになるのだから。」
と、生成AIはOracle Databaseにも大きな影響を与えているという内容でした。
Oracle Database Server Technologies責任者のAndy Mendelsohn(アンディ・メンデルソン)氏は、Solution Keynote「オラクルデータベースの方向性(Oracle Database Directions)」にて、「コンバージドデータベース(Converged Database)」について語っていました。この講演から、運用面だけなく、開発者も扱うプラットフォームが単一になり、まさにシンプルなデータプラットフォームが実現する未来が見えました。
主に開発者向けの機能やAI関連の機能など、300を超える新機能や拡張機能の提供が予定されていますが、最も注目される新機能は以下の3点です。
・JSON Relational Duality View(JSONとリレーショナルの二面性ビュー)
・Property Graph View
・AI Vector Search
3つ目は、これもラリー・エリソン氏の発表にもありました「Oracle Database@Azure」です。
|
オラクル社のページには、Oracle Database@Azureの動作として、
「選択したAzureサービスと、Microsoft AzureデータセンターでコロケーションされたOracle Cloud・インフラストラクチャ上で実行されるOracle Databaseサービスを組み合わせます。Azureのお客様がAzureポータルとAPIを使用してOracle Database@Azureを購入、導入、使用することが可能になります。」
と書かれており(※1)、Oracle Cloud Infrastructure開発責任者のClay Magouyrk(クレイ・マグワイク)氏は、
「オンプレミスのデータセンターに行けば、マイクロソフト社のテクノロジーやオラクルのテクノロジーがたくさんあることから分かるように、マイクロソフト社とオラクルには多くの共同顧客がいる。そうした背景の中、両者の連携は4年以上前にOracle CloudとAzureの間の相互接続から始まった。それ以来、全世界の12以上のリージョンで相互接続サービスを提供し、約500社のお客様にご利用いただいている。」
とコメントしています。ユーザーにとってAzureおよびOracle Databaseを利用する上で選択肢が広がることは、マルチクラウドを活用する企業にとっては魅力的なサービスのため、展開が加速することが予想されます。
今回発表されたOracle Database@Azureは、マイクロソフト社とオラクルの協力関係を一歩進めたものであり、まさに「お客様のためのマルチクラウド」をさらに推し進めたものと言えます。
※1 出典:オラクル社「Oracle Database@Azureの動作」
https://www.oracle.com/jp/cloud/azure/oracle-database-at-azure/
|
|
※出典 オラクル社作成「Introducing Oracle’s Managed PostgreSQL Service with Database Optimized Storage」(Oracle CloudWorld参加者への配布資料)
この「OCI Database with PostgreSQL」は、フルマネージドのPostgresデータベース サービスです。
Oracle Cloud上で年内に正式サービスとして提供開始すると発表がありました。
まず初めにSenior Product ManagerのMichael Sorola(マイケル・ソノラ)氏より、オープンソースの利点とオラクルのオープンソースへの投資理由として、
「オープンソースには多くの利点がある。軽量で柔軟性があり、機敏性が高く、利用に際しユーザーがライセンス費用を負担することなく、コスト効率が高い。ただし、クラウドでの管理には専門的なスキルとリソースが必要なため、社内のリソースに関連するコストがかかる可能性がある。したがって、オープンソースサービスをマネージドサービスにすることで管理工数を削減し、コスト効率を高めることができる。企業は常に革新性と競争力を維持する方法を模索しており、オラクルはお客様のビジネスミッションを支援するために、様々な方法でオープンソースと連携してきている(筆者注:Oracle Linux、Java、MySQL、Apache Kafkaなど)。」
「オラクルはTCOの削減に重点を置いており、お客様がOCIで可能な限り低コストで最高のエクスペリエンスが得られるように、Oracle Cloudをゼロから再構築した」
と、オラクルがパブリッククラウドのあり方をどのように再考したのか、の説明がありました。
その上で「OCI Database with PostgreSQL」について、Software Development責任者のPrasad Bagal(プラサド・バガル)氏は、
「オラクルはパッチ適用、重要な修正、セキュリティ修正などのソフトウェアの自動化されたライフサイクル管理を担当する。しかし、重要なポイントは、データベースに最適化されたストレージを使用する共有ストレージ アーキテクチャだ。これにより、新しいブロックを使用してデータベースを複数の可用性ドメイン間で複製できるようになる。コストを削減しながら、実際に使用したストレージ分だけ支払えばよい。ミッションクリティカルなアプリケーションに必要な可用性と耐久性のレベルでサービスを提供するためにデータベースの実行に重点を置いている。現在ベータ版であり、初期テストの結果、Postgres SQLコミュニティバージョンのDatabaseよりも高いパフォーマンスが得られている。」
とアピールしていました。
Oracle CloudとPostgreSQLを両方サポートしているアシストとしては興味深いサービスになりそうです。
※本サービスは2023年11月14日に正式リリースされました。
※参考:OCI Database with PostgreSQLのご紹介: あらゆるニーズに対応するクラウドデータベース・スイートの完成
https://blogs.oracle.com/oracle4engineer/post/oci-database-with-postgresql-ga
4日間の慌ただしい参加ではありましたが、その中でもラスベガスの雰囲気や、世界中からオラクル製品に期待する人々が集まり、ワクワクしながら楽しんでいる姿に刺激を受け、自分自身もいつの間にかワクワクしていることに気づきました。
どの時代でもトレンドがありますが、どの時代もインフラは普遍であり、データをストックしておく場所「データベース」であり、オラクルは長年にわたりそのデータベース市場を牽引してきました。そして今、AIをこれほどまでにスピーディーかつ使いやすい形でオラクルの世界に取り込むことにより、Oracle Database、そしてOracle Databaseユーザーがこれまでにないステージへと進化するのだと感じたイベントでした。
本記事でご紹介した機能は、既に提供されているものもありますが「提供予定」のものもあります。
アシストでは、新機能が実際に提供され次第、日本のお客様に有用な機能から検証し、具体的にご紹介してまいりますので、ぜひご期待ください。
|
|

|
|---|
1999年入社後、市ヶ谷本社・札幌営業所にて幅広い製品の営業を経験。豊富な営業経験をいかし、現在はデータベース技術統括部にて全社のデータベース事業を推進する役割を担う。
趣味は「海外旅行」、好きな言葉は「ありがとう」
。 ...show more
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

OCVSのネットワーク設定はこれで完璧!初心者でも分かりやすいよう、OCIリソース、オンプレミス、Oracle Services Network、インターネットへの接続をステップバイステップで解説します。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
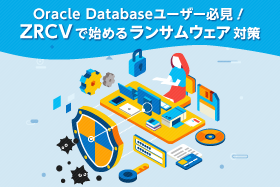
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。