
- Oracle Database
もう迷わない!SYSAUX表領域の肥大化の原因と対処法を徹底解説!
本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
|
|
オラクルの年次イベント「Oracle OpenWorld 2019」が米国サンフランシスコのモスコーニセンターで開催された。
これまでは赤を基調とした会場が特徴的であったが、今年からはお客様やパートナーとの繋がりを強調したデザインにコーポレートカラーが変更され、会場は落ち着いた雰囲気に包まれていた。
|
|
|
|
その雰囲気とは対照的に世界各国から6万人規模の人が参加し、オンラインで配信された動画の視聴を含めると10万人規模の人が参加するという大規模なイベントであった。
今年も開発者向けイベントの「Oracle Code One」が同時に開催され、会場内では2800ほどのセッションが行われ3600人ほどのスピーカーが登壇し、300社以上のパートナー企業によるデモやハンズオンが行われた。
また、会場の各所で「Think Autonomous」というメッセージが見られ、これからもAutonomousの進化を目指す姿勢を強く感じるイベントであった。
本稿では、世界最大規模のITイベントであるOracle OpenWorld 2019に参加した所感を紹介する。
Larry Ellison氏が登壇するKeynote Sessionに筆者も参加するため、1時間半前には会場に向かったが例年通りすでに長蛇の列ができており、改めて注目度の高さを実感することになった。
セッションが開始すると、「Gen 2 CloudとOracle Autonomous Infrastructureについて話す」と発表が始まった。発表された新サービスや新機能について記載する。
人的エラーを無くすことを目的とし、今年はさらに真のAutonomousを実現するために最新の機械学習を取り入れ、これにより完全なAutonomous Cloudを提供すると語った。
1つの例として、車の事故も人の運転によって起きてしまっている。自動運転になれば人によるミスが無くなり、交通事故による被害が無くなると述べ、システムも同じであり、人間が設定するとミスは起きるが、システムが監視、設定、チューニングをすることで人の操作によるエラーは無くなると語った。
今回のセッションでは終始「human error」や「pilot error」という単語を何度も耳にし、自律化(Autonomous)することで人的エラーが無くなること、それによって管理者は別の業務に着手できるという利点を今回の発表では1番強調したいのであろうと感じた。
|
|
|
2018年までもAutonomous DatabaseなどAutonomousな機能は提供されていたが、ソフトウェアの場合はどうしてもOSコードも影響してくる。そこで、OS側もカバーできる世界初、世界唯一の自律型 OSである「Autonomous Linux」が発表された。オラクルはこれまで20年以上、OSの開発に取り組んでいたが完成までに大きな苦労があったと語る。
Autonomous Linuxは高い可用性に加えて、ダウンタイムなしで自動的に脆弱性に対するパッチを適用するため、何もしなくても常に安全な状態が保持される。また、Autonomous Linuxは Oracle Cloudに無償で導入されており、もしOracle Cloudを利用中ではないユーザでも、Redhat Linuxで動作するアプリケーションの変更やダウンタイムなしでOracleに移行できると語った。
|
|
|
AutonomousなOSが発表されたことに驚いたが、今回の発表の中でLarry Ellison氏が「最も驚きのスライドだ」と前置きをした発表がある。それがリージョンの拡大に関する発表であった。現在、全世界に16のリージョンが設置されているが、2020年にはなんと36のリージョンを設置すると発表し、会場内に大きな拍手が沸き起こった。もし実現することになれば、AWSのリージョン数を上回ることになる。オラクルがどれほどCloudに力を入れているかが明確になる衝撃の発表だと感じた。
なお、日本では2019年5月に開設された東京リージョンに続き、今後大阪にも設置予定である。
|
※ 上記のみ別のセッションから抜粋 |
|
|
オラクルはMicrosoft Azureとの提携を発表していたが、今回のリージョンの拡大に加え、Microsoft Azureとの連携も強化する。
現在はアメリカの一部とロンドンで Microsoft Azureと Oracle Cloud間の相互接続が可能だが、グローバルでサービスを稼働させるために今後はアメリカの西側、ヨーロッパ、アジアと世界中で Microsoft Azureとの相互接続を加速すると語った。これにより全世界でAzureの強みとしているサービスと、Oracle Exadata Database Machine(Exadata)やAutonomous Databaseを組み合わせてシステムを構成可能になる。
また、Oracle Cloud Infrastructure (OCI)上にMicrosoft SQL 2016 EnterpriseとStandard Editionの稼働をサポートすることも発表され、OCI上にSQL Serverを稼働させることもできると語った。これまでは全てのサービスをオラクルで完結する方針と筆者は感じていたが、OCI上にOracle Database以外のデータベースを稼働することが可能になったということもあり、これまでには無いオラクルの変化を感じた。
|
|
|
VMwareとの協業も発表されているが、今回のセッションではVMware on Oracle Cloud Infrastructure が発表され、VMwareの管理ツールでOracle Cloudのリソースを管理可能で、オンプレミスのVMware環境からオラクルの最新のサービスであるAutonomous Databaseや、Oracle Analytics Cloud、Exadataの連携も可能と語った。
また、既存のVMwareワークロードをほとんどの変更なしで簡単にCloud上にLift-and-shiftできると述べた。
|
|
Gen2 CloudのAutonomous Databaseではこれまでの自動運転に加え機械学習を取り入れており、運用やチューニングといった作業は自動化され、高性能で高可用性のデータベースを利用できる。これにより、これまで管理に費やしていた時間を、別の業務に費やすことができることが利点だが、一番重要視される点はやはりセキュリティである。
このセキュリティに関する機能やサービスについてもいくつか発表され、他のクラウドよりも優れていると強調した。
● Autonomous Database Dedicated
パブリッククラウドで専有のExadata環境上でAutonomous Databaseを稼働できるプライベート・データベース・クラウドの提供が発表された。
他のCloudは基本的にコンピュータを共有しており、そのコンピュータでコードを共有している場合、同じコンピュータ上に制御コードが存在することになる。
Oracle Cloud InfrastructureではDedicated Serverは安全な分離されたゾーンにあり、制御コードなどは別のメモリを備えた別のコンピュータ上にあるため、悪意のあるアクセスがあったとしても境界にあるコンピュータがそれらをブロックでき、「分離されたゾーンには侵入できない」とセキュリティに対する自信を語った。
|
|
|
● Gen 2 Exadata Cloud@Customer
これまで、Oracle Cloudをお客様のデータセンターに配置できるCloud@Customerが提供されていたが、今回は次世代版である「Gen 2 Exadata Cloud@Customer」が発表された。
Gen 2 Exadata Cloud@Customerでは最新のExadata X8が導入されており、最新の機械学習をベースにした多くの機能を備えている。さらにExadata X7よりも高速で、より多くのcoreとストレージを利用可能だ。具体的には、Exadata X7よりCPU時間が28%、Smart Scansは140%高速になり、加えて使用可能なストレージは40%増えると発表された。また、パブリッククラウドと同じようにAutonomous Linux やAutonomous Database で簡単に開発が可能になる。
Gen 2 Exadata Cloud@Customerは、Gen 1 Database Cloud@Customerを利用中であれば簡単に、無料でアップグレードできるとのこと。
● Exadata X8M
セキュリティ関連ではないが、新モデルのExadata X8Mについてもここで紹介する。Exadata X8Mでは 100Gb Ethernet + RoCE(RDBMS over Converged Ethernet)が搭載されており、Exadata X8よりもネットワークの速度は2.5倍になる。
また、ストレージサーバでは世界初となるPersistent Memory(PMEM)が搭載され、これまでも最高のパフォーマンスを誇るデータベースとしていたが、さらに「信じられないほどのパフォーマンス」と表現されるほどの究極のパフォーマンスを手に入れた。
Persistent Memoryの採用によりこれまで時間を要していた処理に拘束されていた時間を他の作業に費やすことができ、IT業界にさらなる変化が生まれる可能性を秘めていると感じた。
|
|
|
|
|
● Oracle Data Safe
新たなセキュリティソリューションとして、Oracle Data Safeが提供された。既に提供は開始しており、追加コストなしでOracle Cloud上の各種Database Serviceで利用可能である。
Oracle Data Safeでは、セキュリティ管理簡略化のため1つのコントロールセンターでデータ、ユーザ、構成などのリスクを即時に可視化することができる。管理可能な機能としていくつか紹介された。
他のクラウドと比べても、あらゆる面においてOracle Cloudのほうがセキュリティが優れていると強調して語られた。
|
|
発表の最後で、「もう1つ(One more)」と何度も前置きをしてOracle Cloudの無料トライアルにAlways Freeが追加されることが発表されると、会場に大きな拍手が沸き起こった。
Always Freeは、規模は小さいがAutonomous Databaseなど最新のOracle Cloudに触れることができる。開発者や企業、学生などに触れてもらうことを目的としており、誰でも期限無く使っている間永遠に無料で利用できるサービスと語った。
利用できる機能は制限されているが、Oracle Cloudに気軽に触れることができるため、OracleのCloud事業を広める1つの手段であると感じた。筆者はまだAlways Freeを利用していないが、一技術者としてはこの機会を見逃さず検証、開発、学習を行い、Oracle Cloudをさらに知りたいと思わせてくれる発表であった。
|
|
|
Always Freeの発表やリージョンの拡大など、今後もCloud事業の拡大は加速していく。今後も成長を続けていくこのAutonomous(自律的)なサービスが、どこまでDatabaseやCloud業界を進化させていくのか、ITに変化をもたらすか、ヒューマンエラーは本当に「0」になるのか、今後の動向に注目したいと感じた。
この日もKeynote Sessionが行われたため、筆者も参加した。尚、Mark Hard氏が登壇予定だったが、急遽講演内容の変更が行われていた。
このセッションではまずアクセンチュアの Senior ExecutiveであるAnnette Rippert氏が会社の成長には何が必要かについて語った。事例として、一度低迷してしまったもののその危機を打開して大きく成長したとある企業を紹介し、その企業がブレイクスルーを果たすまでの要素として3つのピボット「INNOVATION PIVOT」、「INVESTMENT PIVOT」、「PEOPLE PIVOT」が重要であると述べた。低迷をブレイクスルーするためには、今まで通りではなく大きな「変革」が必要で、それに「投資」する決断も必要である。また、それらを実行に移すのは「人」であり、企業として人を大切にすることが重要であると語った。最後に、この低迷から立ち上がることができた企業は、アクセンチュア自身であると締めくくった。
「何かを変えるためには、徐々の変化ではなく大きな変革が必要」と語られる場面もあり、小さくコツコツではなく時には大胆な変革を選択することも必要であると感じた。また、企業の成長には必ず「人」が必要であり、企業として人を大切にすることも非常に重要であると再認識することができた。
また、その後はオラクルのClay Magouyrk氏が1日目に発表された機械学習やAutonomous Linuxなど、真のAutonomousについて改めて語り、パートナーであるMicrosoft社のMary Williamson氏やVMware社のJohn Gilmartin氏も登壇し、オラクルとコラボレーションすることで今後さらなる成長、拡大していくと語った。
印象的だった場面として、登壇してすぐClay Magouyrk氏とMary Williamson氏、John Gilmartin氏それぞれが携帯電話のインカメラで2ショット写真を取るユーモアな場面があり、お互いの関係性がよいことを感じられた場面であった。
筆者はデータベースに関する「Oracle Database What's New,What's Next」のセッションにも参加した。既存の18cや19cの内容もあったが、20cの大きな追加機能として、AutoMLという機械学習の実装や、不正なデータ改ざんを防止するためのブロックチェーンテーブルが実装される予定であると発表された。多くの新機能が紹介された内容ではなかったが、セキュリティの強化や機械学習の導入が徐々に進んでいる印象を受けた。
|
|
|
|
|
3日目のKeynote SessionでもLarry Ellison氏が登壇し、「Fusion Cloud Applications」の分野について語った。
始めに、オラクルはERPの分野で約25000の顧客を獲得しており、他にも過去5年間でFusion Appsの分野では約12000、Oracle Cloud Apps の分野では約32000の新規顧客を獲得したと語り、業界の中での優位性を示した。特に、ERP(salesforceと合わせて)やHCMの分野では圧倒的な1位であるとし、オラクルが業界をリードする立場であると語った。
さらにアナリティクスの新機能として、Oracle Analytics for Applicationが発表された。
Oracle Analytics for ApplicationはOracle Analytics Cloud上に構築される。アプリケーションのアナリティクスや、マシンラーニングでデータのパターンなどを自動で分析してパターン予測ができる。また、それらの分析結果をリアルタイムで情報共有が可能であり、他企業のアナリティクス機能と比べて最もエキサイティングであると語った。
ビジュアルデータや音声インタフェース、言語インタフェースなど様々な機能が実装されており、分析結果をスライドに表示して発表した。
|
|
|
このセッションの中で印象的だった場面としては、発表の途中で今回登壇できなかったMark Hard氏に対するねぎらいの言葉が語られる場面があり、会場の拍手が響き渡った。長年にわたりお互いパートナーとしてOracleに貢献してきた二人の信頼が伝わる感慨深い一面を目の当たりにした。
Oracle OpenWorld 2019ではセッション以外でも、様々なイベントが開催されていた。
野球観戦やヨガ体験、パーク内散策などのイベントが「Oracle Park」で開催された。この球場は旧AT&Tパークでサンフランシスコ・ジャイアンツが本拠地とする球場である。
オラクルは長年サンフランシスコ・ジャイアンツのスポンサー契約を行っていたが、なんと2019年1月にAT&Tパークの命名権を取得して「Oracle Park」と命名した。これは、IT企業以外に勤めている人や学生などの認知度を高めることが目的の1つであるとのこと。
筆者はそのイベントの1つであるOracle Park内でのミッション:インポッシブルの上映会に参加した。
普段は選手たちがプレイしている球場内で絶対に入れない場所だが、今回のイベントでは外野の芝生に座って大画面モニターで映画鑑賞することができた。大画面で迫力のある上映に加え、普段メジャーリーガーがプレイしている場所にいるという実感が、とても感動的だった。ただ、9月のサンフランシスコは昼と夜の寒暖差が大きく、筆者は比較的薄着であったこともあり、座ったまま長時間映画鑑賞することは厳しい環境であった。もし、今後こういったイベントに参加する予定がある方は、厚着のセーターなどの準備をおすすめしたい。
また、3日目の最後に行われたOracle CloudFest.19にも参加した。これまではOracle Park(旧AT&Tパーク)で行われていたが、今回は2019年9月に完成したばかりの「CHASE CENTER」で行われた。
この「CHASE CENTER」とは、NBAのチームで世界最高峰のスリーポイントシューターのステフェン・カリーも所属している、2017年、2018年と連覇を成し遂げたゴールデンステート・ウォリアーズの新拠点地になる場所である。
今回のOracle CloudFest.19ではジョン・メイアーやフロー・ライダーという例年通り豪華な顔ぶれであり、今回は開催地が屋内でかつアルコールも相まって、大きな盛り上がりを見せた。新しい会場で、コーポレートカラーを変更した新しいオラクルの幕開けを飾る、よい締めくくりであった。
尚、スポーツ好きの筆者としては、命名したばかりのOracle Park内の芝生に足を踏み入れたことやウォリアーズよりも先にCHASE CENTERに入場できたことなど、非常に胸が熱くなるイベントの連続で、オラクルの規模の大きさを改めて実感できた。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今回のOracle OpenWorld 2019の発表はデータベースより圧倒的にCloud関連が多い印象であった。また、オラクルはGen 2 CloudとしてAutonomous 化を加速しており、目指している「ヒューマンエラーを無くす」ことが実現する日も、遠い未来ではないのではないかと感じた。もし本当に管理面が自動化されれば、その分別の業務に投資ができ、IT業界に大きな変化をもたらすと予想される。
現在はまだオンプレミスが多い印象だが、今後はオラクルに限らずCloudやAIなど進化していくIT業界に、アシストとしても一人の技術者としても学びを止めてはいけないと感じた。
猛スピードで進化していくIT業界に不安を覚えながらも、自動化によってどういう世の中になるのか期待が高まる部分もあり、今回の渡米、Oracle OpenWorld 2019の参加はとてもいい刺激をうけることとなった。
|
|
山口 一晟
|
最後までご覧いただきありがとうございました。
本記事でご紹介した製品・サービスに関するコンテンツをご用意しています。また、この記事の他にも、IT技術情報に関する執筆記事を多数公開しておりますのでぜひご覧ください。
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
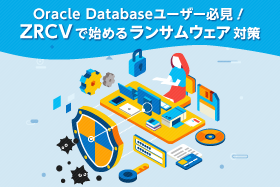
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。

本記事では、お客様の自己解決率向上のために注力したFAQ作成、および、そのFAQ作成をエンジニア育成に活用した当社ならではの取り組みをご紹介します。