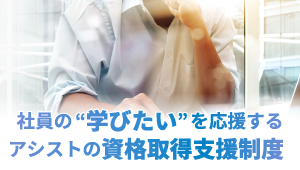
- 取り組み紹介
社員の“学びたい”を応援するアシストの資格取得支援制度
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。
|
|
某大手企業が週休三日を検討し始め、既に新幹線通勤などを認めているところもあります。また別の企業では介護休業を2年に延長するなど、介護離職ゼロや社員の生活に寄り添った制度を検討する企業が増え始めています。政府も、現在最長でも1年半の育児休業を2年に延長することを検討し、「1億総活躍社会」に向け、雇用継続のために必要な施策への取り組みが加速しています。
今回、アシストの中日本支社でも週一での在宅勤務を利用しているメンバーや、育児のため時短勤務等を活用しているメンバーがいるので柔軟な勤務体系の実態についてお伺いしてみました。
前編では、在宅勤務の利用について語ってもらいました。
|
|
大橋 寛(サービス事業部 中日本サポートセンター 課長)
|
|
|
川東 健吾(サービス事業部 中日本サポートセンター)
|
|
|
駒田 信人(サービス事業部 中日本サポートセンター)
|
|
|
大藪 日登美(サービス事業部 中日本サポートセンター)
|
|
|
小笠原 宏幸(サービス事業部 教育部 2課 ※中日本勤務)
|
──まずは、在宅勤務利用者にお話しをお伺いします。中日本のサポートチームでは、メンバー6名の内、半数のメンバーが週一の在宅勤務や時短勤務を利用されています。名古屋勤務で教育部に在席する小笠原さんも、在宅勤務を利用されていますね。在宅勤務を利用し始めたきっかけについてお伺いできますか。
川東:元々は市ヶ谷のサポートセンター勤務だったのですが、家庭の事情で静岡県浜松へ転居することになったんです。現在は名古屋のサポートセンター勤務となっていますが、やはり通勤に片道2時間以上かかるため、通勤負荷の軽減のために週一での在宅勤務を利用し始めました。
駒田:私の場合も、同様に通勤に片道2時間近くかかっています。そのため、平日は家族での時間がほとんどとれませんでした。そのためワーク・ライフ・バランスを考え、在宅勤務を申請しています。元々は市ヶ谷勤務でしたが、私も家庭の事情で三重県に転居することになり、遠距離通勤になりました。市ヶ谷勤務の時は都内に住んでおり、通勤は1時間弱だったので大分通勤時間が延びました。
小笠原:これまで幕張→市ヶ谷→名古屋と勤務地は変わっていますが、入社後ずっと教育部配属です。教育部は市ヶ谷のみにある部署ですが、家庭の事情で浜松市の隣りの磐田市に転居したことで、2015年からは私一人が名古屋支社で活動しており、OracleやPostgreSQLの研修講師、テキスト作成、執筆活動、後輩育成、販促活動などを担当しています。また、過去にはJP1の講師も担当していました。在宅勤務は東京在籍時から利用おり、その時も今ほどではないにしても通勤時間が長かったため、1日を有効活用するために利用していました。
──川東さんと駒田さんは通勤時間に片道2時間・・・往復で1日に4時間も通勤にかかっているということですね。通説では、通勤時間が長ければ長いほど幸福度が下がる、通勤時間の平均は58分で限界は86分なんていうことも言われますが、実際のところどうでしょう。
川東:そうですね、通勤時間にかけられるのは2時間が限界だと思います。通常勤務の場合、朝は6時半の電車に乗って、会社に着くのは9時前。定時の17時半にオフィスを出ても、帰宅は20時前になります。残業をして22時頃に家に着いた場合、起床時間は5時半なので、食事をしてお風呂に入って・・・ほとんどプライベートの時間がとれませんね。時と場合によっては週一の在宅勤務を利用しないこともありますが、通常勤務が5日間続くとへとへとになります。
|
|
小笠原:私は家から会社までは1時間40分程ですが、その内の40分が新幹線です。新幹線を使わずに在来線で行くと2時間半かかりますが、さすがにきついですね。新幹線は「こだま」なので座れないことは無く、机もあるので仕事をする環境としてはかなり良いです。オフィスではちょっと時間が勿体無いと感じてしまうメール対応やタスク整理なども落ち着いてできるので、通勤中の良い気分転換になっています。ただ、新幹線代は自腹なので金銭的には辛い面もありますね。
川東:私は、通勤の電車の中では座ることができるので、愛用の Mac Book Pro で趣味を楽しんでいます。2時間も片道にかかっていますから、少しでも短く感じるように趣味に費やしていますね。
──川東さんには、社内での動画作成などご協力いただいていますね。あれは、もしかしたら通勤時間に作成いただいていたのでしょうか・・・。在宅勤務によって、体力面でメリットがあるようですが、他にはどんなメリットを感じられていますか?
川東:遠距離通勤という面だと一番大きいのが睡眠時間の確保ですが、家事の手伝いもできたりと、家庭で過ごす時間が増えるので助かっています。
──通勤にかかっていた4時間がそのまま家族との時間に使えるとなると、家族の皆さんにとっても嬉しいことですね!遠距離の方や育児のために週一在宅通勤を活用されている方が現状では多いように感じていますが、特に通勤や家庭事情がない方でも利用されるメリットはあると思いますか?
駒田:色々あると思いますよ。思いついたところで挙げさせてもらうと、
とかでしょうか。これからの季節、インフルエンザは切実な問題ですからね・・・。働ける状態ではあるけれど、会社のルールで出社できない場合、在宅勤務などでカバーできると嬉しいです。
|
|
──インフルエンザ等は、家庭内で発症した人がいた場合、出勤の考慮をするようにとされていますが、そういう時にも活用できますね。震災時に関しては、交通機関の乱れなどもあるので、安定したサポートを提供するのに在宅勤務を利用するのはいいですね。最近では、地震だけではなく大雨の影響などもありますから・・・。逆に在宅勤務のデメリットはいかがでしょう。
川東:仕事の面では、周りの景色に変化がなく、チャイムの音もなかったり、場合によっては電話もかかってこないことがあると、気づいたら2時間ぐらいじーっとPCの画面だけを見ていることがありますね。そのため、適度に息抜きをしないと疲れる・・・という位でしょうか。チーム内でのコミュニケーションを心配される方がいますが、電話やチャット、メールの利用で円滑にできていると思っています。在宅勤務はチームの理解と協力が必要だと感じますが、アシストは皆さん協力的で助かっています。後は、ネットワークのスピードがとても重要だと思いますが、会社が用意しているネットワークのスピードには満足しています。
駒田:そうですね、実際に会って相談やミーティングができないという点はありますが、携帯電話やチャットで密に連絡をとれば、週一の在宅勤務でも問題ない範囲ですし、距離感は感じませんね。Web会議等もありますから。ネットワークが遅いと容量の多いファイル転送等に時間がかかるということもありますが、ファイル転送用のサーバ(仮想サーバ等)があれば、問題ありません。どのような業務を実施したかについては、在宅勤務の終了時にメールで、上司やチームメンバーに作業報告をし、作業内容の見える化を行っています。サポート業務という点に関しては、オフィス出勤時と変わらないパフォーマンスを発揮することが可能です。
──週一の在宅勤務であれば、メンバー間で密に連絡を取り合い、作業の見える化をすることでコミュニケーションの課題は特に感じられないということですね。では、もう少し制度がこうなれば・・・と思うことはありますか?
小笠原:私の場合、切実です。在来線代は会社から支給されていますが、新幹線は自己判断で利用しているため、特急券代は自分で支払っています。新幹線通勤に関しては大きな負担なので、その点がカバーされると非常に嬉しいですね。
駒田:在宅勤務の可能日数が増えると嬉しいですね。実は、私は元々派遣契約だったんです。正社員に切り替わる前は約2年フルで在宅勤務をしていました。フルでの在宅勤務の場合、オフィスでの座席や交通費自体も不要になるので、会社としてのコスト削減にもつながるかと思います。契約の形態や評価制度なども考えていかなくてはなりませんが、介護等の家庭の事情で遠方への転居を余儀なくされる場合や育児等の関係でオフィスへの出勤が難しい場合でも、会社を辞めずに仕事を続けてもらうことは、会社にとっても新規人材への教育コスト削減になります。
|
|
──在宅勤務に関しては、以前の座談会でも曜日固定ではなく柔軟に利用できれば、という声もありました。同様に日数に関しても、会社としてのメリットや、個人の働き方を考えてさらに使いやすい制度になっていくといいですね。
後編では、育児休暇&短時間勤務について、上司として柔軟な勤務体系をどう捉えるか、ご紹介します!
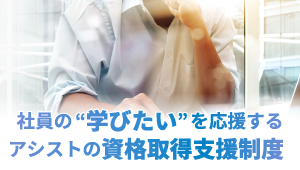
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。

アシストは、2024年2月よりオンライン学習プラットフォーム「Udemy」を技術者向けに導入しました。今回は、導入の目的や利用者の声をご紹介します!

アシストは社員の貢献を「業績報奨金」などのインセンティブ制度で還元し、社員旅行や食事会を通じてチームワークや組織の一体感を醸成しています。「個人よりチームプレーヤー」を重視し、社員主体で運営される交流施策が特徴です。