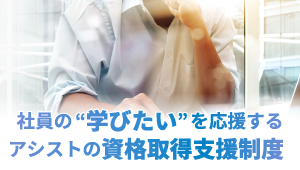
- 取り組み紹介
社員の“学びたい”を応援するアシストの資格取得支援制度
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。
|
|
「お客様の潜在的課題を発見する」「新しい製品を発掘する」「新しいソリューションやサービスを開発する」。この三つの機能を併せ持った新しい組織がアシスト内に生まれました。その名も『ビジネスソリューション本部』。ポイントはなぜその3機能を集結させたのか。そして、なぜ今なのか。リーダー2名へのインタビューを通じて、新組織発足の目的や今後の展望などについて探ります。
|
|
ビジネスソリューション本部 |
|
|
ビジネスソリューション本部 |
営業活動、ソフトウェアのご紹介&導入支援、アフターフォロー。これまでアシストは、「営業」「フィールドエンジニア」「サポートエンジニア」という主に3職種の社員を通じて、お客様に各種サービスを提供してきました。しかし、ビジネスの様々なシーンでITが活用されるようになると、初期段階から営業と技術が密接に連携してお客様に向き合う必要がでてきたのです。そこで「プリセールス」という役割の営業的な視点や俯瞰的な視点を持つ技術者が、営業とともにお客様先に同行し、ヒアリングを通じて課題を発見、その解決につながる製品やサービスを提案するようになりました。シンプルに言えば、お客様の近くで、より良い提案をスピード感を持ってお届けし、さらにそれをフィールドエンジニアへつなぐ、お客様とアシストのハブ的な役割です。今回、新たに発足した『ビジネスソリューション本部』は、全国のプリセールスを「顧客支援部」として一つにまとめ、その機能を強化するという意味合いを持っています。
ではなぜ今、そのハブ機能を強化する必要があるのでしょう。統括部長に就任した谷津宏和が解説します。「プリセールスの技術者を集めた最大の理由は、お客様先におけるソフトウェアの選び方・使い方が変わってきた点にあります。従来からアシストでは、お客様の情報システム部門(以下、情シス)と継続的に接点を持ってきましたが、この数年、急速にビジネス部門(以下、BU)の方々とも接する機会が増えてきました。プロダクトアウトで製品を売り込むのではなく、現場の生の声を聞き、潜在的な課題を捉え、お客様のビジネスの成功のためにITで何ができるかを考え提案していく必要が強まっているわけです。また、クラウドに代表されるように『ツールを買う』ことよりも『提供される機能を使って効果を出す』ことに主眼を置くBUのユーザーが増えています。そうした背景の中で、技術的知見と顧客視点を持った人が営業の最前線でも求められるようになってきたのです」。
ITリテラシーがあれば製品を指名買いすることもできますが、BUで働く方はITではなく各領域における業務のプロ。そこでアシストとしても、特定の製品を担当せず、ITトレンドとビジネストレンドの両方に精通し、技術的視点に加えお客様のビジネスの成功のための提案ができるエンジニアを育成してきたのだと谷津は語ります。
さらに、全国組織として統合したもう一つの狙いは、お客様ニーズを全国で素早く共有するためです。営業の現場では、スピード対応と幅広い発想がますます求められるようになってきており、お客様対応の中でキャッチした情報を素早く全国横断で共有し、他のお客様へのフィードバックや情報提供、提案に役立てたり、同種のニーズにまとめて対応できるソリューション企画につなげるためです。
|
|
「ただし言うは易しで、それを実践することは至難でもあります」。そう告白するのは東日本顧客支援部を率いる秋月潤。「もちろん業界や領域などによる傾向はありますが、現実には各社各様、BUごとに課題は異なります。目に見える製品を売るのではなくソリューションを提案するということは、全ての案件で毎回ゼロから試行錯誤するということ。フレームワークやフォーマットのような『型』はありません」。
そうだとしても、実際にITツールに触れることになるBUのユーザーから直接話を聞けることは、とても有益なことなのだと秋月は強調します。「情シスのお客様からも、『BUと直接会話してもらえて助かった』といわれるケースも多いのです。同じ会社にいても、変化の著しい現場の実情を全てフォローすることは困難です。その意味で、アシストのプリセールスはお客様社内の情シスとBUどちらも支援できる、橋渡しができるポジションにいます。そこにメンバーのやりがいもあります」。
|
|
案件の上流から携わり、様々な視点で製品やサービスの提案をする。確かにプリセールス部隊には、社内外から大きな期待が寄せられています。一方で、今回の新組織発足では「新事業共創推進室」「データ活用支援室」「GTONE推進室」という、また別の役割を背負ったセクションも『ビジネスソリューション本部』内に設置・移管されました。それぞれについては、何が期待されているのでしょう。
再び谷津が説明します。「この3チームが行っていることは『新ソリューションの開発や新製品の発掘』、『ソフトウェア活用の新しいシナリオやサービス開発』、『新製品の立ち上げ』とバラバラなんです。一見するとなぜプリセールスを司る『顧客支援部』と同じ本部内に同居しているかわかりづらいですよね(笑)。でも共通項はあります。それは、どんな課題に対応していくべきかを考え、社内外のリソースを起点にソリューションを生み出すこと。だからこの布陣は、実は将来を見据えた体制でもあるんです。つまり、営業と連携してプリセールスがより早い段階からユーザーのニーズを汲み取り、既存の製品やサービスを提案するだけでなく、新たな製品やサービスまで自前で開発できる体制を築いているということです」。
|
|
未来を開拓し、文字通り他社にはないソリューションを生み出すことを背負った『ビジネスソリューション本部』は、まだまだ50人程度の少数精鋭のスタートアップセクション。谷津も秋月も「社内の優秀な人材をもっと集めたい」と口を揃えますが、当面は今いる選ばれしメンバーで局面を打開していく覚悟だと言います。
アシストでは「めげない、逃げない、あまり儲けない」という3つの約束を掲げていますが、プリセールス部隊では提案そのもので報酬を得るビジネスモデルは採用しておらず、また他の3チームもアウトプットがすぐに直接的な収益を生むわけではありません。まさに「儲けない」を地で行く『ビジネスソリューション本部』。だからこそ、お客様やアシストの仲間を「支援」することに邁進できるのだと、リーダー2人は自信を持って語ります。
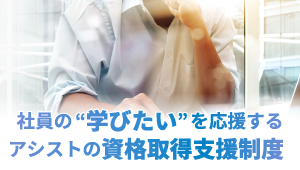
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。

アシストは、2024年2月よりオンライン学習プラットフォーム「Udemy」を技術者向けに導入しました。今回は、導入の目的や利用者の声をご紹介します!

アシストは社員の貢献を「業績報奨金」などのインセンティブ制度で還元し、社員旅行や食事会を通じてチームワークや組織の一体感を醸成しています。「個人よりチームプレーヤー」を重視し、社員主体で運営される交流施策が特徴です。