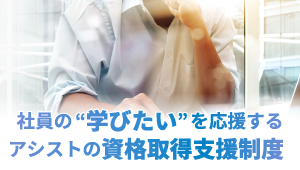
- 取り組み紹介
社員の“学びたい”を応援するアシストの資格取得支援制度
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。
|
|
2019年1月に「JP1 Version 12」がリリースされました。JP1は、国内トップシェアを誇る統合システム運用管理ソフトウェアです。システムの自動化や稼働性能監視、資産管理等を統合的に行うことができます。
バージョンアップのたびに様々な機能拡張がなされているJP1ですが、今回はその進化の裏側を取材してきました。
JP1のメーカーである日立製作所と、販売代理店のアシストは年に1回、2社間で「JP1エンハンス会議」という会議体を運営しています。
その会議では、次のバージョンで実装される機能拡張について、アシストから意見や要望を挙げる場になっているそうです。
具体的にどんなことをしているのか、日立製作所の伊藤啓多氏と、アシストの佐野、布施に話を伺いました。
--「JP1エンハンス会議」って何をしているのですか?
|
|
「JP1エンハンス会議」は、お客様の声を製品に反映させるための場です。つまり、お客様から挙げられている問題やリクエストをアシストでまとめ、優先度などを検討した上で、日立製作所に製品の改善要求として上げていく場です。もう10年くらい続けているんですよ。 |
|
アシストの佐野弘明 |
|
JP1はお客様の課題に合わせて進化し続けています。お客様が求める機能や、問題解決を何よりも大事にしたいと考えているからです。 |
|
|
|
改善事項の優先度を変えてもらうというのが重要なポイントです。お客様の状況をアシストがしっかりキャッチし、より多くのお客様に喜んでいただけるように取り組んでいます。 |
--そこまでお客様中心の思想で開発されているのですね!このJP1エンハンス会議を通して、例えばどんな機能改善がなされたのですか?
|
特に印象に残っているのは、日本語版と英語版を1本に統合したことです。以前は日本語版と英語版が別々のパッケージとして提供されていたため、導入においても運用においても煩わしさがあり、お客様にご迷惑をおかけしていました。それが1本に統合され、言語を選ぶだけで良くなりました。 |
|
|
日立製作所の伊藤啓多氏 |
--日立製作所から見て、アシストの取り組みはどう映っていますか?
|
私共としては、お客様と向き合って製品を作っていきたいと考えていますので、お客様の声を密に聞いているアシストと協力できるのは非常にありがたいと感じています。 |
|
|
|
アシストとしては、「お客様の求めるものを実現したい」「お客様の課題を解決したい」そして「JP1という製品をお客様と一緒に育てていきたい」という想いを強く持っています。そこにアシストならではの価値があると考えているのです。 |
|
アシストの布施裕貴 |
--最後に、JP1をお使いのお客様に伝えたいメッセージをお願いします。
|
|
アシストはメーカーではありませんが、製品を一緒に作っている感覚でやっています。もう、製品を作る側として見ていただいて構わないとすら思っているのです。だからお客様にはどんどん要望をあげていただきたいと思っています。 |
|
製品品質も、人としての品質も、上げていきたいと思っています。お客様に寄り添い、お客様と共に製品を育てているつもりです。私共ほどお客様と向き合って改善を繰り返している製品はないと自負していますよ。本当にそれくらい本気でお客様の声を重視しています。 |
|
|
JP1エンハンス会議の様子 |
実際に「JP1エンハンス会議」を見学させてもらいました。
広い会議室に40人弱のメンバーが集まり、製品カテゴリ毎にテーブルを囲んで情報共有や議論が行われています。ここで、お客様の声が製品に反映されていくのですね。
|
JP1エンハンス会議メンバー |
JP1をお使いのお客様へ
製品に対するご要望や、業務でお困りのことがありましたら、アシストに遠慮なくお申し付けください。アシストは日立製作所と一丸となって、製品改善に取り組んで参ります。
一緒にJP1という「みんなの製品」を育てていきましょう。
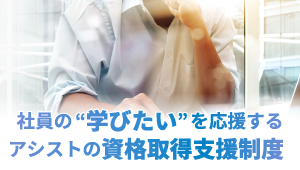
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。

アシストは、2024年2月よりオンライン学習プラットフォーム「Udemy」を技術者向けに導入しました。今回は、導入の目的や利用者の声をご紹介します!

アシストは社員の貢献を「業績報奨金」などのインセンティブ制度で還元し、社員旅行や食事会を通じてチームワークや組織の一体感を醸成しています。「個人よりチームプレーヤー」を重視し、社員主体で運営される交流施策が特徴です。