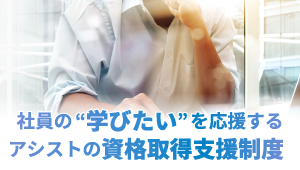
- 取り組み紹介
社員の“学びたい”を応援するアシストの資格取得支援制度
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。
|
|
新入社員の育成は、「優秀な人財に育てるにはどうしたら良いのか」「早期戦力化のためにはどういう育成が必要か」などと、どのような業界、職種でも悩み多き分野だと思います。社会人基礎や業界の基礎は新入社員研修で学ぶかもしれませんが、それだけで一人前になれるわけではなく、実務については配属先でそれぞれ教え、育てていかなければいけません。
アシストのサポートセンターでも同様に、毎年新入社員を迎える度に、入社した年の初冬にはお客様に一人前の技術者としてサポート提供ができるよう、試行錯誤を重ねながら新人教育を行っています。ありがたいことに、お客様から「アシストのサポートは質が高いね!どうやって技術者の育成をしているの?」とコメントをいただくことも!
ということで、今回はアシストサポートセンターで実施している新入社員育成の極意についてご紹介します!
サポートセンター配属の新人が実際のお客様対応を開始するのは、11月頃です※。入社後の4月から6月の3ヵ月間は新入社員研修で社会人基礎とIT基礎を学びます。その後、7月から部門配属となり、実務を学んで一人立ちとなります。
※製品チーム毎の差や個人差はあります。
お客様へのサポート提供に向けて、大きく三つの流れで実務の習得を目指します。
①座学と課題を通しての、知識や調査力の習得(7月)
②模擬サポートによるサポート力の習得(8~10月)
③手厚いフォロー体制のもと、サポートデビュー(11月)
それでは、それぞれの工程における育成の詳細をご説明します!
サポートセンターに配属された新入社員は、まず約1ヵ月に渡る座学の部門研修を受講します。
講師は配属先のチームの先輩社員が持ち回りで担当しており、先輩との関わりを持ちながら、仕事をしていく上で必要となる知識を習得してもらう形にしています。外部に委託しないことで、より現場で使える知識に的を絞って教えることができ、短期間で効率的に学ぶことが可能です。
座学といっても、途中で実機を使っての説明をしたり、演習問題を入れたりすることで、聞いて終わりではなく実際の経験につながるよう、各講師が工夫をしています。
1ヵ月に渡る部門研修の後は、担当製品の基本的な機能に関わる課題を、20問程度実施してもらいます。研修のテキストや製品のマニュアルを見ながら、各自で勉強して課題を解いてもらうことで、製品知識はもちろんのこと、自分自身で調査する力を身に付けることも目的としています。
座学や課題で製品について学んだ後は、すぐにお客様対応を開始するわけではなく、先輩をお客様に見立てた模擬サポートを実施します。
お問い合わせに対応するためには、製品知識だけではなく、お客様の状況を把握するためのヒアリング力、必要な情報を探し出す調査力、製品の動作を確認するための検証力、お客様に分かりやすく説明するための文章力などが必要になります。
これら全ては、先輩社員が説明するよりも実践の中で培う方が身に付くため、模擬サポート形式で実践から学びを得てもらっているのです。
模擬サポートは、2ヵ月以上の期間をかけて20問近くの課題を実施していきますが、調査開始から回答送付まで、全てのステップを先輩社員の細かいチェック付きで実施します。各ステップで考えるべきことや注意すべきことを、実践とフィードバックの繰り返しの中で身に付けていきます。
模擬サポート終了後、大体11月あたりに実際のお客様対応を開始します。
しかし、お客様対応を開始したからといって全てのお問い合わせを一人で対応するわけではありません。約半年間は先輩社員が全案件の内容をチェックします。
OJTL制度※があるため、基本的には一人の先輩が担当の新入社員の案件をチェックしますが、チームによってはチェックする先輩を交代し、様々な角度から案件をチェックするポイントを学べるよう工夫しているチームもあります。
※OJTL制度:配属された新入社員に対し、先輩社員が1対1で実務や環境への適応フォローなどを約2年間にわたり担当する取り組み
|
|
一人立ちに向けての育成フローとは別に、対象を新入社員に限らず定期的に研修を開催し、学びの機会を作ることにも力を入れています。すべての研修はアシスト独自で考案しており、なかでも毎年以下の二つの研修が新入社員たちに好評です!
◯サポート対応LIVE研修(先輩社員による解説付き)
先輩社員のお問い合わせ対応を解説付きで視聴する研修です。過去の対応履歴はいつでも確認できるため、自分で参照して学ぶことも可能ですが、先輩社員がどのように考え対応したかや、対応時に使用している細かなテクニックまでは対応履歴だけでは学べません。これらを吸収するための機会として用意されている研修です。
◯実践サポート力向上研修
②で紹介した模擬サポートを、先輩への相談なしで対応する研修です。新入社員たちの成長度合いを測るための一人立ちチェックも兼ねています。また、新入社員全員が同じ内容の模擬サポートに取り組むため、自分と他者の対応を比較できます。研修終了後は、先輩社員からの細やかなフィードバックがあり、自身の強みや弱みを把握し、今後のサポート対応に活かすことができます。
アシストサポートセンターの技術者育成について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
新入社員の育成には時間がかかりますが、どの担当者がどのお問い合わせの担当をしても、お客様にご満足いただけるサポートセンターであれるよう、今後も試行錯誤を重ねながら技術者の育成に力を入れていきたいと思います。
今年の新入社員は「変化を愉しむ」をテーマに採用されており、今のコロナ禍においても様々な工夫を取り入れ愉しみながら研修に取り組んでいます。新人たちの成長に、ぜひご期待ください!
|
|
|
インタビュアー:渥美 紀里子 |
私も新人育成に関わらせていただく機会がありますが、研修を担当すると感じるのは、新人さん一人一人の理解の仕方が違うという点です。同じ説明をしても伝わる新人さんもいれば伝わらない新人さんもいます。もちろん経験値によって変わる部分ではありますが、考え方や価値観に依存する部分も大きいと感じます。だからこそ、研修内容は毎年ブラッシュアップしつつ、ただ資料を読むだけではなく、新人さんの理解度に合わせて説明するよう各研修の講師が意識しています。 |
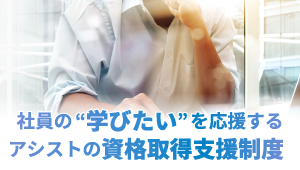
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。

アシストは、2024年2月よりオンライン学習プラットフォーム「Udemy」を技術者向けに導入しました。今回は、導入の目的や利用者の声をご紹介します!

アシストは社員の貢献を「業績報奨金」などのインセンティブ制度で還元し、社員旅行や食事会を通じてチームワークや組織の一体感を醸成しています。「個人よりチームプレーヤー」を重視し、社員主体で運営される交流施策が特徴です。