
- Oracle Cloud
これで安心!OCVS環境とオンプレミス/OCIリソースを繋ぐための必須ネットワーク設定ガイド
OCVSのネットワーク設定はこれで完璧!初心者でも分かりやすいよう、OCIリソース、オンプレミス、Oracle Services Network、インターネットへの接続をステップバイステップで解説します。
|
|
この記事は JPOUG Advent Calendar 2019 の20日目のエントリです。
Oracle CloudでOracle Databaseを利用する場合、大きくは2つのパターンが存在します。
①PaaSサービスを利用する(Autonomous DatabaseやOCI-Database)
②IaaSサービスを利用し、ユーザ側でOracle Databaseをインストールする
①のPaaSサービスはユーザ側の環境構築作業などを圧倒的に削減して利用できるため、クラウド化の検討ではPaaSの利用を前提とする方が多数です。
しかし、用途や要件によっては②のIaaSでOracle Databaseを利用する方法がベストな場合も存在します。
|
|
弊社にいただく相談で最も多いのは”現行環境でWindowsを利用しているため、Oracle CloudでもWindows OSを利用したい”です。PaaSサービスではOracle Linuxが前提ですので、Windows OSでOracle Databaseを利用するのであればIaaSを採用する必要があります。
他にも、”現行環境の監視ツールを移行先でも利用したい”という場合は、Autonomous Databaseはエージェント導入作業に必要なOSへのログインができないため、IaaS、もしくはPaaSの中でもOSへのログインが可能なOCI-Databaseを検討します。
Oracle Cloudのイチオシであり最新サービスのAutonomous Database。構築から運用(バックアップ/チューニング)に至る多くの作業を自律的に実施するという特徴があります。また、オンプレミスではExadataでしか利用できない19cのAutomatic Indexingなどの注目機能も利用可能です。
データベース側で多くのことを実現してくれる一方で、ユーザ側で実行できるコマンドや設定には制限が存在します。採用を検討する上ではAutonomous Databaseの特徴を理解しておく必要があります。
|
|
なお、Autonomous Databaseはアップデートが非常に多いサービスです。サービス開始当初は利用できなかった索引やパーティションなどの機能も現在では利用できるようになっています。2019年12月現在の上述の制限についても、いずれは解消される可能性もあります。
|
|
変化が激しいAutonomous Databaseを採用するのにあたっては、情報のキャッチアップが非常に重要です。
クラウドサービスへの移行を検討する際に、コストの検討は避けて通れません。Oracle Cloudと他社クラウドをコストメリットの観点で比較しました。
|
|
特筆すべきはDatabaseサービスよりもComputeサービスの方がコストメリットが大きいという点です。そのため、オンプレミス環境のクラウド化を検討する上ではデータベースサーバだけをクラウド化するのではなく、アプリケーションサーバなどのIaaSサーバも含めてシステム全体をクラウド化した方がコストメリットが大きい場合があります。
更に「IOPS課金がない」「アウトバウンド通信の無料枠が大きい」「サポート料がサービス料金に含まれている」といった特徴もあるため、コストの面では非常に優位性が高いと言えます。
次の図は、あるシステムをクラウド化した際のOracle Cloudと他社クラウドのコスト差を算出した例です。
|
|
データベース部分は他社クラウドと大きく変わりはありませんが、コンピュートやストレージ、サポート費用で大きく値段に差がつき、Oracle Cloudの方が40%ほどコストメリットがあるという結果が出ています。
既存システムのクラウド化を検討をする際に、コストを重視するケースは非常に多いです。しかし、コストのみを見てしまうと今回ご紹介したようなポイントの考慮が漏れてしまう可能性があります。
今回ご紹介したポイントの他にも、以下のような箇所にも考慮することで、より現実的なクラウド選定が可能です。
・バックアップや監視の仕組み
・可用性の担保
・他社クラウドとの性能比
一つ一つのポイントをしっかりと検討した上で、クラウド化をご検討ください。
2021年 18日目
Oracle Databaseのサポート対応で依頼することの多いファイルとコマンド
https://www.ashisuto.co.jp/db_blog/article/jpoug-oracledb-logfiles-command.html
2020年 17日目
Oracle Databaseバージョンアップ後の性能劣化で試したい暫定対処
https://www.ashisuto.co.jp/db_blog/article/jpoug-vup-temp-solution.html
2019年 24日目
【Oracle Database】DMLリダイレクションで一歩進んだ Active Data Guard の使い方(19c新機能)
https://www.ashisuto.co.jp/db_blog/article/20191224_ADG_REDIRECT_DML.html
2017年 14日目
Oracle Database 12cR2へのアップグレード後に発生するORA-01017
https://www.ashisuto.co.jp/db_blog/article/201712-ora-01017.html
2016年 9日目
【Oracle Database】2016年にサポートにお問い合わせをいただいたORAエラー TOP5
https://www.ashisuto.co.jp/db_blog/article/2016_oerr_rank.html
2015年 15日目
パフォーマンスダウンを「再現待ち」にしないための準備
https://www.ashisuto.co.jp/db_blog/article/20151215_oracle_pfmdwn.html

|
|---|
2015年にアシストに入社後、Oracle DatabaseやOracle Cloudを中心としたフィールド技術を担当。
導入支援だけではなく、最新機能の技術検証も積極的に実施。社内外のイベントにて発表も行っている。...show more
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

OCVSのネットワーク設定はこれで完璧!初心者でも分かりやすいよう、OCIリソース、オンプレミス、Oracle Services Network、インターネットへの接続をステップバイステップで解説します。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
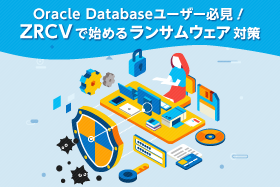
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。