
- Oracle Database
もう迷わない!SYSAUX表領域の肥大化の原因と対処法を徹底解説!
本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
|
|
Oracle Database Appliance(以下、ODA)とは、Oracle Databaseに最適化されたアプライアンス製品です。サーバ、ストレージ等のハードウェアとクラスタやOS、Oracle Database等のソフトウェアが一体になって提供されています。ODAにはクラウドや汎用サーバ(オンプレミス)にはない優れた点があり、さらにサポート面でのメリットもあります。本記事では、そんなODAのメリットを具体例を交えてご紹介します。
Index
汎用サーバでOracle Databaseを構築する場合、サーバやストレージ、OSを選定し、各ベンダーから見積もりを取って購入。ハードウェアが届いたら構築してインストールを進めるという流れが一般的です。このとき、どのサーバを選ぶべきか、ディスク構成をどのようにするのがよいか、各ハードウェアの相性は問題ないか、OSの設定はどうするべきか、など様々なことを検討する必要があり、時間と労力を要します。
ODAの場合、Oracle Databaseの動作に最適なハードウェア構成を長年の様々な実績と検証に基づいてオラクル社が選定、構築済であり、OSやソフトウェアも専用にカスタマイズされた形でインストールされるように作られています。そのため、サーバ構築時の選定作業や構築作業自体が簡素かつ短期間で済むようになります。また、Oracle Databaseの使用を前提に構成されているため、パフォーマンス面でもOracle Databaseに最適な形で構築できることが大きなメリットです。
最適な構成の例として、ノード間で行う通信=インターコネクトが行われるケーブルでInfiniBandやEthernet 25GBなど高速通信が可能なものが使用されている点が挙げられます。
インターコネクトとは、クラスタ内の全ノード間で情報をやり取りするプライベート・ネットワークです。Real Application Clusters(RAC)構成ではリモートノードの生死を確認するハートビートや、ノード間でデータ整合性保護などのためにデータブロックを転送するキャッシュ・フュージョン用として利用されます。インターコネクトの通信速度が遅いとキャッシュ・フュージョンの速度も遅く、Database処理のパフォーマンス劣化にも繋がります。そのためインターコネクトに優れた性能のケーブルを使用することは重要です。こういった点はOracle Databaseソフトウェアに精通した上でハードウェア構成を検討しないと出てこない観点だと思います。
以上のようにOracle Databaseに最適化されたセット品としてのODAですが、どのようなシステムに適した製品なのでしょうか。
ITシステムのクラウド化の波が強まる昨今ですが、汎用サーバ、クラウド、アプライアンスと大きく3つに分けるとすると、ODAはアプライアンスにあたる製品です。それぞれの特徴を簡単にご紹介しつつ、どのような方にとってODAが有力な選択肢となるかを説明します。
汎用サーバを選択する場合、サーバなどのハードウェア構成を自由に選択できることやデータを自社のデータセンター内に保有できるという点がメリットになります。お客様によっては、サーバ調達は特定のベンダーからにするなどの社内規定がある場合や、データベースと連携して使うアプリケーションとの互換性などで特定のハートウェアが適している場合、あるいは特定のベンダーロックインは避けたいという場合もあるかと思います。また、クラウドの時代とはいえ、やはりまだ自社の情報をクラウド上に配置するのはセキュリティなどの観点から抵抗があるといった場合は汎用サーバが適しているでしょう。
クラウドの選択メリットとしては、スモールスタートできるという点やOS、ハードウェアの管理工数が大幅に削減できるという点が大きいと思います。そのため、小規模からスタートしていきたいシステムや管理工数の削減を重視したい場合にはクラウドが選択肢として挙がってくるでしょう。
アプライアンスとは特定の用途に特化した専用機器を指します。ODAの場合はOracle Databaseに特化した専用機ということになります。
アプライアンスは、特に使用するハードウェアに指定がなく、ハードウェア選定工数や構築期間を短くしたい、かつ「汎用サーバ」の項目にも記載したような、データを自社のデータセンターで保有したい方に適しています。
また、ODAの概要でも述べたように、Oracle Database に最適な構成で設計されており、パフォーマンス面でもベストプラクティスで構築できるため、パフォーマンスが重要となるシステムの構築に適しています。
加えて、コスト面でも最適化が図られています。最新のODA X9-2 HAの本体価格は約1,200万円ですが、同程度のスペックのサーバを組み上げ式で構築した場合、一般的には約2,700万円かかると言われています。また、Capacity on Demand により、サーバ上で有効化するコア数の指定が可能であり、Oracle Database のライセンス費用を適切に抑えることができます。
オラクルのアプライアンス製品の主なものとして、ODA以外にOracle Exadata Database Machine(以下、Exadata)が挙げられます。ExadataはODAより上位の、よりパフォーマンスに優れた高級モデルで、かなり大規模なシステムの構築に適しています。ただ、ODAもスペックは非常に優れており、ODA X9-2 HAは2ノード構成でメモリが各ノード512GB、共有ストレージは標準構成でSSD 46TBが搭載されています。ある程度小さいシステムであれば複数統合することができるレベルのスペックと言えます。
以上のように比較してみると、ODAの位置づけとしては、例えば中~小規模のシステム統合により管理工数を削減したい場合や、ある程度パフォーマンスを求められるシステムを構築したい場合に適した製品と言えるでしょう。
対象となるシステムや社内のITポリシーがアプライアンスの特徴に適しており、ある程度ハイスペックなデータベース環境を求められる場合に、ODAは有力な選択肢となるのではないでしょうか。
そしてここからは、サポートエンジニアとしてODAのサポートに携わって7年以上の経験から思う、サポート目線でのODAのメリットをお伝えします。
まず、最大のメリットは、ハードウェア、OS、Oracle Databaseのワンストップサポートが受けられるという点です。これは単純に問い合わせが楽というだけの話ではありません。
サポートの現場で陥る問題として、ハードウェアやOS、データベースソフトウェアなど複数が関与する障害や不具合に遭遇した時に調査が難航するケースがあります。どのレイヤーが原因なのかを特定するのに労力を要しますが、特定のレイヤーではなくレイヤー間の連携部分に問題があるケースなどは特に、調査に時間を要することがしばしばあります。
ITソフトウェア、OS、ハードウェアは日々進化しており、各製品ベンダー内でもこれまで培った技術や経験を活かして安定稼働の維持や不具合の防止が進んでいます。実際にOracle Databaseでも、9iや10gの頃と比べると12c以降のバージョンではブロック破損などのメディア障害の発生事例が減ってきていることがわかります。
| バージョン |
弊社への問い合わせ全体に対する ブロック破損の発生率 |
|---|---|
| 19c | 0.05% |
| 18c | 0.15% |
| 12c | 0.16% |
| 11g | 0.27% |
| 10g | 0.40% |
| 9i | 1.58% |
このように各製品内だけで見ると、各ベンダーの製品品質や調査対応レベルが上がっており解決も早くなっていますが、これが異なる製品間での連携部分で発生した問題となるとどうでしょう。
ここで、弊社サポートで発生した具体的な例をご紹介します。
2ノード構成のReal Application Clusters(RAC)環境で片ノードのクラスタウェアが起動しないという問題がありました。前述のインターコネクトの説明の中で、RAC構成ではインターコネクトによりノード間で様々な情報をやり取りし、データの整合性保護を担っていると説明しました。インターコネクト通信が正常に行えないとノード間の整合性が担保できなくなってしまうため、インターコネクト通信に問題が発生したことで、この仕様動作により片ノードが停止してしまいました。
問題は、なぜインターコネクト通信に異常が起きたかという点です。Oracle Databaseとしてはインターコネクト用のNICからの応答がないことを検知しており、これが要因ということまでしかわかりませんでした。ではNICに異常があるのかというと、pingコマンドの実行では問題なく通信が行える状況にありました。
果たしてこれはOracle Databaseの問題なのか、NIC(ハードウェア)側の問題なのか、はたまたOSなのかと原因特定が難航しました。
結論としては、NICの物理的な劣化により、一定サイズ以上の大きな通信の時のみパケットロスが発生し、通信障害に至るという状況にあったのが原因でした。pingコマンドのデフォルトのパケットサイズは小さく、そのサイズではパケットロスは起きなかったため、ハードウェア観点の調査が後手に回り調査が難航したというケースです。
こういったケースでは、各ベンダーの調査結果を持ち寄って総合的に調査を進めていく必要があるため、調査の舵取りの工数も調査自体の難易度も高くなる傾向があります。
ODAでは、Databaseはもちろん、ハードウェアもOSも全てオラクル社から提供されており、サポートも一括で受けることができます。そのため、上述のような複数のレイヤーにまたがる問題も1ベンダー内で総合的に調査できる点が、サポート目線での最大のメリットであると感じています。
このような複数レイヤーにまたがる問題は頻繁に起きるものではありませんが、いざ発生すると調査が難航する可能性があります。トラブル発生時の業務継続や停止時間の短縮といった点でODAのようなアプライアンス製品が持つワンストップサポートというメリットは大きいと思います。
本記事では、ODAの概要とそのメリットをサポート目線を含めてご紹介しました。
ODAとは、Oracle Databaseに最適化されたハードウェア、OS、ソフトウェアが一体になって提供されたアプライアンス製品です。アプライアンス製品は有事の際のサポート体制という面でもメリットがあります。
ODAは対象となるシステムがアプライアンスに適した場合で、ある程度ハイスペックなOracle Database環境が求められる場合、また安心なサポート体制を求める企業にとって有力な選択肢になり得るでしょう。
ODAは実際に多くの企業で選ばれ、活用されています。他社事例もぜひ参考にしてみてください。
▶ ODA導入活用事例はこちら
本記事が次期サーバ選定の参考になれば幸いです。

|
|---|
2006年 株式会社アシスト入社後、サポートセンターにてOracle製品のサポートエンジニアとして重篤障害などのトラブル対応をメインに2000件以上対応。フィールドエンジニアへの出向を経て、サポートセンターに復帰。現在は問い合わせを対応するメンバーのバックフォローを担当。...show more
■本記事の内容について
本記事に記載されている製品およびサービス、定義及び条件は、特段の記載のない限り本記事執筆時点のものであり、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
■商標に関して
・Oracle®、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・Amazon Web Services、AWS、Powered by AWS ロゴ、[およびかかる資料で使用されるその他の AWS 商標] は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

本記事では、SYSAUX表領域の肥大化の主な原因と、現場DBAの方がいますぐ実践できる原因特定・対処・予防のステップを、具体的なSQL例とともに整理して解説します。
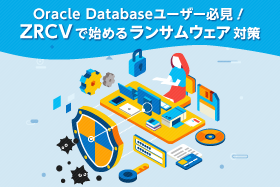
ランサムウェアの脅威からデータベースを守る!OCIのフルマネージドバックアップサービスZRCVは、3-2-1-1-0ルールに対応し、データ損失ゼロに近い復旧を実現します。本記事では堅牢な保護機能と、GUIで完結するわずか5ステップのシンプルな設定方法を解説します。

本記事では、お客様の自己解決率向上のために注力したFAQ作成、および、そのFAQ作成をエンジニア育成に活用した当社ならではの取り組みをご紹介します。