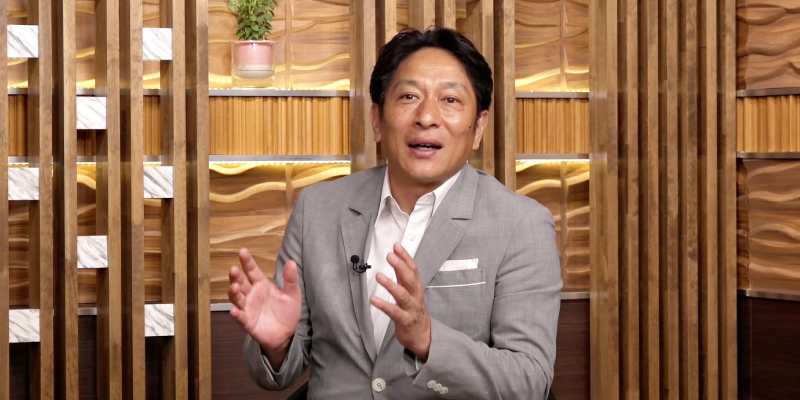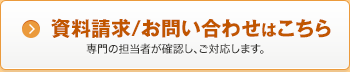FC町田ゼルビアを1年でJ1昇格に導いた黒田剛監督、箱根駅伝で7回目の総合優勝を果たした青山学院大学駅伝部の原晋監督、そしてアシスト社長の大塚辰男が、経営の最前線で戦うリーダーの皆様に、革新的な組織運営のヒントをお伝えしました。黒田監督の著書『常勝チームを作った最強のリーダー学』から、以下6つのテーマについてお話しいただきました。
● リーダーの仕事で最も大切なことは?
● リーダーにとって一番大切なスキルとは?
● 褒めないことも教育
● ティーチングとコーチング
● スピード感とは?
● 組織の感情をコントロール
青山学院大学
地球社会共生学部 教授 陸上競技部長距離ブロック 監督
原晋氏
リーダーの仕事で最も大切なことは?

大塚
リーダーの仕事で一番大切なことは何でしょうか。

黒田氏
組織とは、結果を求める集合体であり結果が第一です。組織が向かうベクトルを合わせ、結果が得られるよう組織の舵取りをすることが、リーダーの最も大切な仕事だと思います。

原氏
組織を作る上で一番重要なのは、理念の共有だと思います。組織に属する誰もが同じ理念を持てるよう意思統一を図ることが、リーダーの役割の一番大切なことだと考えます。理念の共有なくして組織はまとまりません。黒田監督の著書にも、同様のことが書かれていて、まさに共感した部分です。
リーダーにとって一番大切なスキルとは?

大塚
リーダーに必要なスキルで一番大切なものは何でしょうか。

黒田氏
30年以上指導者を務めてきた中で、多くの挫折を味わい、監督を辞めようと思ったことも何度もあります。自分が伝えようとしていることが選手に伝わっていない、理解されていないことが理由で、伝えていることを選手が実践できない場面が往々にしてありました。その経験から、選手に一瞬のうちに理解させ、判断させ、実践させられる「伝える力」が一番重要だと思うようになりました。選手の心に響かなければ、自分は何も伝えられていないと捉えるべきです。

原氏
京セラの稲盛和夫氏が大事にしていた「小善は大悪に似たり」という言葉があります。相手を喜ばせようと発せられる言葉は、時に相手をダメにすることがあるという意味です。この後に「大善は非情に似たり」と続きますが、本当に相手を心から思うのであれば、厳しい言葉や叱責、時には非情と思われるような言葉も必要で、それが後々大きな影響力を持つということです。言葉を慎重に選び、分かりやすく伝えていく力がリーダーには必要ですね。

大塚
メッセージを伝える際には、キャッチフレーズを使いますか。

黒田氏
電車の中で見かける大学の広告に良いフレーズをよく見かけ、その内容をスマホにメモしています。さすが一年かけてじっくり考えられた内容だと感心させられます。

原氏
そうした良いフレーズはその競技の中だけでなく、世の中の色々なところに存在しています。指導者はそれを感じ取れる嗅覚を持つことが大切です。テレビドラマや歌詞のフレーズ、野球やサッカーのヒーローインタビューなどから、選手のための「落ち着かせ語録」、「がんばらせ語録」などを私もスマホに登録しています。

大塚
アシストでは、「めげない、逃げない、あまり儲けない」というキャッチフレーズを活動基本方針に掲げています。お客様には、「めげない、逃げない、まったく儲けない、でしょ?」と言われることもありますが、正しくは「あまり」儲けないです(笑)。この方針のもと、お客様も、取引先も、社員も、みな良好な関係を築くことを目指しています。

原氏
講演をする日は、よくYouTubeを参考にモチベーションを高めるのですが、上手な話し手は誰もが、自分の経験談をもとに自分の言葉で話します。リーダーや指導者として偉大な人は、相手の心に火をつけることができる人。正しいことを理路整然と言っても、相手の心に火をつけられなければ意味がありません。

黒田氏
試合2時間前のミーティングでは、2枚のスライドを使って選手の心を掴むことを習慣にしています。この2枚のスライドを一週間かけて準備しています。FC町田ゼルビアの監督になって、昨年J2で42試合、今年はJ1で6月30日までに21試合、合計63試合を戦ってきましたが、同じフレーズを決して使わないよう常に新しい材料を探しています。選手たちのモチベーションを最高に押し上げるために何を伝えるべきか、一週間ずっと考えています。

原氏
箱根駅伝は一年に一度ですが、私も「○○大作戦」というフレーズを一年間ずっと考えぬいて、12月10日の記者会見で発表します。翌朝の新聞の見出しにそれが掲載されればしめたものです。記者さんにどう響くかも考慮して考えますが、これで選手、ファン、そして記者さんも含め、一体感が生まれると思っています。

大塚
サッカー、駅伝と競技は違えど、お二人とも、選手のモチベーションをいかに高められるかを毎日考えているということですね。

原氏
黒田監督の『最強のリーダー学』を読ませていただいて思うのですが、黒田監督も私も、たとえ競技が変わったとしてもチームを優勝させることができるのではないかと思います。それだけのメソッドがつまっています。私は大相撲の親方になって日本人横綱を育てたいとよく言っていますが、たぶんできると思うのです。
褒めないことも教育

大塚
育成に関連して、黒田監督は著書の中で「褒めないことも教育」とおっしゃられています。どのような理由からそういう考えに至ったのでしょうか。

黒田氏
褒めること自体を否定しているわけではありませんが、プロを目指す、海外を狙うと決めるような時期からは、70%、80%しかできていないのに褒めてしまってはその選手の可能性をつぶしてしまうことになります。指摘や否定をすれば、確かに選手と指導者の間にわだかまりができるかもしれません。ただ、それを避けて褒めてばかりいては、70%、80%で満足する習慣をつけてしまうことになります。残りの20〜30%をやりとげる力、さらには二倍、三倍へと成長する可能性を殺してしまいます。子どもたちの将来に関わる人たちは、自分が嫌われても、わだかまりができようとも、あえて可能性を伸ばすことを伝えてあげる必要があります。褒めることを前提に指導してはならない、ということかもしれません。

原氏
ダメなところはきちんとダメ出ししなければならないというのは同感です。ただ、褒めるときは徹底して褒めるべきではないでしょうか。良いことをしているのに、やかましいことを言う必要はない。褒めるときは、みんなの前で少し誇張してでも褒めてあげた方がいいというのが私の考えです。ただ、リーダーやマネジメントには「正解」はないので、指導者や選手の気質、組織の状態に合わせて、様々なアレンジを加える必要があります。黒田監督がおっしゃっていることも一理ありますし、私のやり方も適切な場合もあるでしょう。言うなれば、たくさんの引き出しを持っていることが重要ということだと思います。
ティーチングとコーチング

大塚
育成に関連して、ティーチングとコーチングの使い分けは意識されていますか。

原氏
何も分かっていない人には分からせなければならないし、ゼロベースであれば素地を作ってあげないといけません。義務教育レベルであれば、コーチング以前にティーチング、教える、しつけることが必要だと思います。特に、道徳的な部分、時間を守る、約束を守る、嘘をつかない、こうした基本的なことは徹底して指導していくべきです。ベースがあった上で、徐々にコーチング的要素が必要になります。しかし、知らない人には知らせ、できない人には教えないといけません。そうした使い分けが必要だと思います。

黒田氏
原監督がおっしゃられたとおりだと思います。幼少期、育成年代と、高校生・大学生・プロとそのステージに合わせた対応が必要です。ティーチングでも、コーチングでも、入り方はどちらが先でもいいのかもしれません。最終的には、きちんと理解し、より良い方向に進んでいくようにすること。結果から逆算して、どちらのアプローチが適しているかを選択するのがいいのかもしれません。ただ、知らない人にはかみ砕いて伝えなければならないというのは原監督がおっしゃったとおりだと思います。
スピード感とは?

大塚
世の中の流れがどんどん早くなってきている中、特にリーダーには色々な場面でスピード感が求められます。スピードについてどのような考えをお持ちでしょうか。

黒田氏
時間は有限、その使い方は無限とよく言われます。この本を執筆したときも、出版社からの内容確認依頼がちょうどランニング中に届きました。チェック自体は10分もあればできるのですが、ランニングから戻ってシャワーを浴びてからやるか迷いました。その頃には相手はもう席にはいないでしょうし、その後のやり取りを考えれば、今やれば10分で終わることが2〜3日はかかってしまいます。心がけているのは、できるだけ相手に合わせて仕事をすることです。そうすることで自分もその場で仕事が終わるし、相手も時間を有効活用できます。結局、道端でスマホでチェックして返信してからランニングを再開しました。一緒に仕事をするのであれば、そうした時間の使い方をする人と仕事をしたいと思います。LINEの返信なども忙しい人ほど早いし、忙しい社長さんほど暇そうに見えます。きっと仕事の仕方が上手なんだろうと思います。

原氏
少し違う観点から考えてみると、ボトルネックの部分を解決しないまま、枝葉の部分だけスピード感を持って対応しても、本当の意味での物事の解決にはならず、結果としてスピードが出ない、ということもありますね。中国の思想家の「飢えている人がいるときに、魚を与えるか、魚の釣り方を教えるか」という有名な言葉があります。魚を与えれば飢えはしのげても一生与え続けなければならないが、釣り方を教えれば自走していけるであろう、という考え方です。物事の本質を追及していくことこそが、スピード感を持って仕事をすることではないかと思います。

大塚
選手のスピード感はどうでしょうか。

黒田氏
サッカーの場合のスピードは、スキル的なものより判断で決まります。瞬時に適切な判断ができるかどうか。判断するためには情報が必要であり、ボールを持っていないときに、360度全方向についていかに情報を得られているかに左右されます。しかも、それを自分にボールが来るまでのコンマ何秒の間で判断しなければなりません。自分が把握しうる情報量を基に判断する能力が、サッカーにおけるスピードだと考えます。

大塚
そうした能力は訓練で得られるものでしょうか。

黒田氏
普通に練習しても習得することはできません。自分の中でそれを習得しようと、意識して日頃から鍛錬していくことで、必然的に無意識にできるようになる。そのレベルにならないとプロとして使えるスキルにはなりません。

原氏
陸上ではもちろん走る速度がスピードなのですが、他の視点から見ると、逆算思考を心がけています。ゴールから考えて今何をやるべきかを考えるという思考方法を取ることで、結果として物事の処理スピードをアップさせることになります。常に逆算思考、そして今何をやるべきかという本質を追及させます。
組織の感情をコントロール

大塚
黒田監督の試合前の2枚のスライドをまとめて本にすれば売れそうですね。

黒田氏
さっさと1日、2日でやってしまえばいいのですが、試合直前まで選手の面持ちが変わるので、不安もあるでしょうし、危機感と戦っている表情を観察しながら、最後に言葉として落とし込みます。

原氏
最近のスライドのフレーズをぜひ教えてください。

黒田氏
昨日(6月30日)、ガンバ大阪との首位攻防戦がありました。負けたら首位を奪われるという状況。同時に、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸の順位にも影響する試合でした。昨日、町田ゼルビアが負けることは、一気に四位以下に崖から転げ落ちることを意味していました。その悲劇感を選手に感じて欲しいと思い、ぎりぎりでもいいから首位を維持したい、そのためにはどういう心持ちで試合に望んで欲しいかを伝えようと、「首位から転げ落ちるという危機感をイメージさせながら試合に入らせること」、それがこの日の我々が持つべきモチベーションだと決め、スライドを用意しました。

原氏
駅伝でも、下位チームを一区間で20〜30秒ほど引き離すことで戦意を失わさせるという場面があります。10区間トータルで勝負するのではなく、この一区間で勝負をつけるんだ、というのがポイントです。2024年の箱根駅伝の例で言えば、4区の佐藤一世が7秒ぐらいの差で襷を受け取ったのを、最初の1キロで20秒ぐらいに広げました。残り20キロありましたが、この時点で勝ったと思いました。おそらく黒田監督にとって昨日の一戦は、そうした局面だったのではないでしょうか。

黒田氏
確かにターニングポイントだったと思います。向こうも躍起になって首位を取ろうとしてきますし、それに飲まれているようでは、自分たちが首位を維持することはできないと腹を括りました。

原氏
これは絶対勝たなければならないというタイミングはあるんでしょうか。

黒田氏
FC町田ゼルビアの監督になって、昨日までに63試合こなしましたが、ここまで連敗が一度もありません。春先に掲げたチームの基本コンセプトは、失点も敗戦もするだろうが、その時に必ず軌道修正して元に戻そう、ということでした。この基本コンセプトを皆で共有していたので、負けが続くことはありません。失点、敗戦したときには、優勝というベクトルに向かって軌道修正が図れるよう、皆にわかりやすく示しています。失点・敗戦時には、何が悪かったのか、その原因を皆で共有しています。運が悪かったで済ますのではなく、敗戦には必ず原因があり、それを突き止め、解決策を共有する。それが習慣になっているからこそ、連敗が一度もないのだと思います。

原氏
駅伝も、二区間遅れるともう首位には戻れない、1分30秒以上開いてしまうと挽回は不可能と言われています。相手にもプレッシャーを与えられなくなります。なので、1分以内でプレッシャーを与えられる状況を維持しよう、粘ろう、そうすればチャンスが出ると、選手には伝えています

黒田氏
敗戦だけではなく、勝利や成功の要因も、もちろん明確にします。これをやったら勝ったよね。こうだったから負けたよね、ということを選手がはっきり理解することが重要です。

原氏
今年の箱根駅伝では、昨年の12月10日頃、16人中、13人がインフルエンザでした。勝てるわけがない。そういう状態から3週間で仕上げました。このような状況でもなぜ諦めなかったかというと、青学の原メソッドという基本軸があったからで、一週間体調を崩しても戻ってくる場所がきちんと決まっていたからでした。チームとしての対応能力ができていたと思います。体調が整ったときには状況は好転しており、12月31日、1月1日には勝てるかもしれないという雰囲気が出ていました。ベースに基本軸があったからだと思います。

黒田氏
チームや組織というのは毎日姿や表情を変えますから、昨日よかったから今日もいいとは限りません。違和感や、ちょっとしたゆるみに気づいたらすぐに軌道修正しないとちょっとずつ崩れていきます。気づくこと、軌道修正をすることを毎日やっていないと組織はすぐにダメになります。

大塚
これからどのようなチームにしていきたいですか。

原氏
おかげ様で、10年間で箱根駅伝7度の総合優勝というトップ・チームになることができました。総合優勝8勝、9勝、10勝ともちろん続きますが、数字遊びだけはしたくありません。カッコいいチーム、影響力のあるチーム、スポーツ界を変えられるチームを目指していきたいです。輝く未来の実現に向けて、チャレンジし続けます。

黒田氏
幸いにも、J1首位で一年の半分を折り返しました。皆さんにゼルビアの試合を町田に見に来ていただけるよう、後半戦に向けてますますがんばります。優勝を目指したいと思いますので、ぜひ町田ゼルビアを覚えて応援してください。

大塚
本日はありがとうございました。