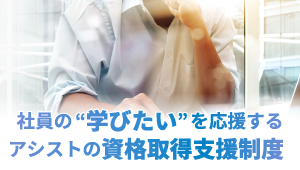
- 取り組み紹介
社員の“学びたい”を応援するアシストの資格取得支援制度
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。
|
|
毎年恒例となっている事例の祭典「アシストフォーラム」。今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で一旦中止が決まりましたが、急遽「アシストオンラインフォーラム2020」(AOF2020)に名称を変え、全145セッションをオンライン配信で8月24日(月)~8月28日(金)にわたり開催しました。
アシストでは、これだけ大規模のオンラインイベントを開催するのは初めて。このイベントを企画・運営したプロジェクトメンバーはこの初めての挑戦にどう取り組んだのか、その裏側に迫ります。
「アシストワールド」「アシスト博」など様々な名称でお客様をお招きしてのイベントを開催してきたアシストが、「アシストフォーラム」に名称を統一し、お客様事例中心の内容で開催し始めたのは2006年からです。「事例の祭典」として定着した「アシストフォーラム」の中止が決定されたのは、申込受付開始まで1ヵ月を切った4月6日のことでした。事例発表企業も、東京、大阪、名古屋、福岡の4会場で延べ47社が確定し、案内状もほぼ完成していました。
アシストフォーラムは、お客様各社がビジネスの課題にどう取り組んだかをお客様自身にご発表いただくイベントです。「他社の発表が非常に参考になったので、今年はそのお返しに自社が発表します」と手を挙げてくださるお客様も増えてきました。来場者数も4会場で3,000名を超えるようになり、事例発表終了後の懇親会では、発表者を交えてのお客様同士の交流の場としてご好評をいただいています。
「アシストフォーラム2020」(東京)のプロジェクトのリーダー、岸和田隆は、当初中止を決断した理由を次のように語ります。
「お客様の感染拡大防止を担保できないこと、コロナ禍による未曾有の状況により講演を辞退する企業もでてきたため開催は難しいと判断しました。アシストの都合だけを考えるとオンライン開催という選択肢もありましたが、事例を発表していただく企業のメリットがないことを理由にオンライン開催は見送りました。事例を発表していただく企業の上位役職者には、自社社員に、たくさんの聴講者を前に講演する機会としてアシストフォーラムを位置付けている方々も多くいらっしゃいます。オンライン開催だとPCの画面越しに講演するだけなので、そのような経験の場を提供することができません。また、オンラインでは当イベントの開催目的であるお客様同士の交流が促進ができないとも考えました」。
|
岸和田さん |
ではなぜ、5日間にわたる「アシストオンラインフォーラム2020」を急遽開催することになったのでしょうか。
「アシストフォーラム」としてはいったん中止を決断したものの、取扱製品のメーカーが、コロナ対策と経済を両立させるためのオンラインイベントを計画中との話を聞き、何か方法はないかと岸和田は探していました。そんな中、コロナ禍で在宅勤務の日課となっていた早朝ランニング中にポッドキャストを聞いていたら、WHOとレディー・ガガが、新型コロナ対策支援のチャリティコンサートをオンラインで開催するというニュースが流れてきたのです。
その時のことを岸和田は次のように振り返ります。
「これだ!と思いました。協賛金をコロナ関連の医療従事者への寄付とすれば協賛企業も参画しやすいでしょうし、事例発表企業も依頼を受けてくださるのではないかと思いました。チャリティのオンラインITイベントにすれば、コロナ対策とビジネスを両立させることができるのではないかと思いつき、さっそく企画書を準備しました」。
事例発表に特化したリアルのアシストフォーラムの中止が決定されたのが4月6日。岸和田が新たに用意した企画が承認されたのが5月19日です。今後のビジネス展開を見据えた情報発信により各社の経済活動に寄与することと、チャリティによる医療従事者への支援の両立をコンセプトに、事例だけではなく、IT企業各社による協賛セッションも組み込んだ提案が「アシストオンラインフォーラム2020」でした。
準備期間が限られていることもあり、事例発表企業も、協賛セッションもそれ程数が集まらないのではないかと心配されました。しかしそんな心配をよそに、事例発表41社、協賛企業はメディア協賛8社を含み42社と、多数の企業が当チャリティITイベントの開催趣旨に賛同してくださいました。協賛企業は当初は広くIT業界を巻き込んでITベンダー各社にお声がけする予定でしたが、アシストの取扱製品のメーカーとビジネスパートナーだけで5日間のセッションが全て埋まりました。
特別講演のTably株式会社 代表取締役 Technology Enablerの及川卓也 氏も、無償でコンテンツ作成を引き受けてくださり、それにアシストのテクニカルセッションも加えて、セッション総数は145本に膨らんだのです。
「及川氏の書籍を読み、事業やプロダクトの企画段階からソフトウェア活用を考慮すべきであるという『ソフトウェア・ファースト』の考え方は、アシストの主張やビジネスとも非常にマッチしていると思い、及川氏に特別講演を依頼しました。イベント趣旨にご賛同いただき、無償でお引き受けてくださった時は、とても感激し、嬉しく思いました」と岸和田は話します。
ソフトウェア・ファースト~ ニューノーマルを生き抜く ~
Tably株式会社 代表取締役 Technology Enabler 及川卓也 氏 特別講演 講演録
岸和田の企画提案が経営層に5月19日に承認された後、84社に賛同を得るところからスタートし、プログラム編成や案内状や申込サイトの準備を終え、7月27日の申込サイト・オープンまでに要した期間は68日です。通常半年以上かけて準備する内容を3分の1の期間で実現しました。
たくさんの関係者にご賛同いただき、145セッションものプログラムが用意できて喜んだのも束の間、それからがプロジェクトにとっての試練でした。ここでは、オンラインイベントの運営に不慣れなプロジェクト・メンバーが、何をどう工夫してこのイベントを開催したかを中心にレポートします。
一番の課題は、145セッションをお客様にどうご案内するかでした。145セッションの中から興味に応じたセッションをお客様に選んでいただくには、紙の案内状では紹介しきれず、セミナー申込システムに動的な絞込機能が必要なのはもちろんわかっていました。しかし、弊社が利用しているシステムは弊社用にカスタマイズされていたため、それには対応しておらず、また社内のSFAとの連携が間に合わないため、新規に構築もすることもできませんでした。
そこで、セミナー申込システムとは別に、イベント紹介用のWebページ側で、課題別、ITツール別、業種別などの切り口でセッション選択のガイドを用意するよう工夫しました。
その結果「イベント紹介ページで参加したいセッションを覚えておいて、申込システム側で再度チェックしなければならず、お客様にはご負担をおかけすることになりました」と岸和田は振り返ります。
今回のオンラインセミナーは、すべての動画コンテンツを事前に準備して当日はその動画を配信するだけの形で運営しました。
コンテンツの準備を担当した赤塚智之は、「これだけ大量の動画が果たして期日までに集まるのかが不安で仕方がありませんでした。事例発表企業も、協賛企業も、こちらからの無理なお願いに快くご対応いただけ、心より感謝します」と話します。「動画はとにかくファイルサイズが大きくなるため、トラック別につないだ動画ファイルをダウンロードするだけでも数時間かかり大変でした」。
|
赤塚さん |
動画視聴のプラットフォームには、ZoomとYouTubeの2つを選択しました。Zoom経由のYouTube Live 配信も行うことで、視聴できるお客様の数が大分増えたのではないかと思われます。コロナ禍の中、ウェビナー視聴にお客様も慣れていたせいか、特に視聴自体には大きな問題は出ませんでした。
セミナーの申込から、営業マンや社内への申込情報の連携、動画視聴の仕組みなどは、以下の通りになります。弊社取扱製品の動画管理基盤のPanoptoも、ちょうど全社での活用が始まったところだったため、過去の事例発表時の音声データとPowerPointのスライドをつないで事例動画コンテンツを内製するなど、アシスト社内でのコンテンツ準備はスムーズに進められました。
|
|
8月24日~28日の5日間の動画配信は、配信環境のバックアップ体制と新型コロナウイルス感染によるオフィス閉鎖リスクなどを加味してAWS WorkSpacesの仮想デスクトップを採用しました。一日3名で、毎日5トラックの動画をZoom配信し、配信状況のチェック担当者も、毎日10名ずつアサインして、お客様と同環境での動画配信状況を監視しました。
当日のウェビナー運営の責任者だった中村剛は、「本番で配信する動画が完成したのが、開催日から2営業日前で、テストも十分に行えない中、当日の運営体制も最低限の人数に抑えたため、うまくいくかヒヤヒヤものでした」と話します。
|
中村さん |
|
放送会場の様子 |
|
今回はオンラインで開催することが急遽決まったこともあり、申込受付期間はお盆を含んで19営業日と、例年のアシストフォーラムの申込期間の3分の1しかありませんでしたが、最終的には2,745名のお客様に申込をいただきました。
集客責任者だった岡部慎治は、今回のオンラインイベントの苦労を次のように語ります。「コロナ禍でのオンライン商談を想定してPowerPointの案内資料を用意しましたが、緊急事態宣言が解除された後、業種や地域によっては訪問が可能なお客様も増えてきたため、急遽、印刷できる案内状が必要になりました。また、セッション数が多いことから、営業担当がお客様の興味に応じてセッションを選んでお誘いしたり、メールを送った後に電話でもフォローするなど、丁寧な対応が集客につながったと感じます」。
また、いつものリアルイベントのお誘いと比べて、メールの案内からお申し込みされたお客様の割合が高かったこと、また、お客様社内での情報流通が促進されたようで、「自社の上司や同僚からの案内」をきっかけに申し込まれた方が多かったのも特徴です。さらに、リアルイベントと違って、各セッションの終了時間まで参加申込を受け付けることで、開催期間中にも700名を超える申込があったことも1つの発見でした。
|
岡部さん |
コロナ禍の不透明な状況の中、すべてが初めてずくしで開催された「アシストオンラインフォーラム2020」ですが、なんとか無事開催できてプロジェクトメンバー一同、ほっとしています。
今回はコロナ関連の医療従事者への支援を1つの目的に開催しましたが、協賛金は1300万円集まり、イベント運営費を除いた約928万円を、公益社団法人日本医師会に寄付することになっています。
実際にオンラインフォーラムを聴講されたお客様からも次のような嬉しいコメントを多数いただきました。
突貫工事で145セッションからなる5日間のオンラインイベントを運営してみて見えてきた課題も多数あります。
一番残念だったのは、他のイベントとの兼ね合いで、申込期間が19営業日しか取れなかったことです。ただ、メールやお客様社内での上司、同僚からの紹介、営業マンの協力も得て、通常のアシストフォーラムの2倍のペースで申込者数が推移していたので、もう少し申込期間が長ければ、もっと多数の方に視聴いただけたと思います。
また、コロナ禍におけるオンライン商談でのイベント周知方法についても、スライド一枚では多数のセッションの内容をお伝えすることができず、工夫が必要でした。
さらに、配信の課題としては、各社に用意いただいたプロモーションビデオなどの動きの多い映像は、配信時にフレームレートやビットレートが低下したためコンテンツの良さを伝えることができない箇所がありました。動画配信向けのコンテンツ作りとコンテンツに適した配信形態を考慮する必要があったと思います。
今年オンラインでやってみて、オンラインでも大規模イベントを内製で実施できることがわかりました。ただ、アシストでは、お客様同士の交流や、弊社社員がお客様と直接お目にかかれる機会を大切にしています。
当イベントの特別講演で及川氏が語っていたように、「オンライン」という新しい選択肢を手に入れることができましたので、2021年度はオンイランとオフラインのハイブリッド型でアシストフォーラムを開催し、アシストらしい「新たな『おもてなし』」にチャレンジしたいと考えています。来年も多数のお客様にお目にかかれることを楽しみにしています。
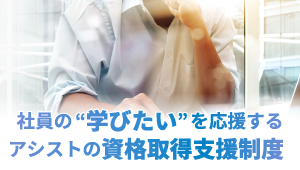
働きながらのスキルアップは簡単ではありません。時間や費用、学習の継続などの面から挑戦のハードルが高いのではないでしょうか。アシストでは、そんな挑戦を後押しするために「資格取得支援制度」を設けています。

アシストは、2024年2月よりオンライン学習プラットフォーム「Udemy」を技術者向けに導入しました。今回は、導入の目的や利用者の声をご紹介します!

アシストは社員の貢献を「業績報奨金」などのインセンティブ制度で還元し、社員旅行や食事会を通じてチームワークや組織の一体感を醸成しています。「個人よりチームプレーヤー」を重視し、社員主体で運営される交流施策が特徴です。