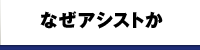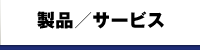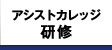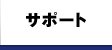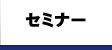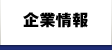- 宮田
- 今日集まった4人は所属部署は違うけど、実は共通点がありますよね。それは、イベント担当者であるということ。
- 西谷
- アシストは研修やワークショップが頻繁にあるので、社員の距離は近いけど、イベント担当者同士でこうして話をするのは珍しい気がします。
- 岸和田
- 確かに。ウチって本当に多くのイベントを開催しているから、名前しか知らないイベントも多いんですよね。
- 坂田
- じゃあ、それぞれが担当しているイベントについて話すところから始めましょうか。できれば、そのイベントの目的なんかも聞きたいです。
- 宮田
- 私はエグゼクティブ向けの大小様々なイベントを担当しています。中でも特徴的なのが、次世代経営幹部向け交流会です。
- 坂田
- エグゼクティブというと、どういう層の方々なのですか?
- 宮田
- 歴史的にも売上げ的にもアシストとのつながりが深いお客様が多く、いわゆる執行役員クラス、部門責任者の方を中心に20名程度です。都内ホテルの会議室を借りて開催しています。
- 岸和田
- アシストの一般社員は、なかなかお目にかかれないレイヤーの方ということですよね。
- 宮田
- 2019年は、流行りの「DX(Digital Transformation)」について、各社でどのような取り組みをしているのか発表いただきました。
- 坂田
- アシストが「エグゼクティブ交流会」を取り仕切る意味合いは何になるのでしょう?
- 宮田
- まさに、場づくりを通じて「アシスト」するということに尽きますよね。「エグゼクティブ交流会」はいわば、経営課題を共有するクローズドな場。書面には残せないけど、口頭ならお話しいただけることもあるんですね。メンバーの皆さん同士にも仲間意識が芽生えている印象です。2020年はさらに裾野を広げて、お客様社内の次世代ITリーダー層向け交流会もスタートさせる予定です。
- 西谷
- 私は「ソリューション研究会」の東日本事務局長です。アシストの製品やサービスを導入・ご利用いただいているお客様なら、誰でも参加ができます。講演を中心とした「定例会」と「分科会」があり、「分科会」には会員登録が必要ですが、どちらも無料です。
- 岸和田
- アシスト社員でも、メンバーとして「分科会」に参加している社員がいますよね。
- 西谷
- 「分科会」では10名程度のチームに分かれて一年間、各テーマについて共同研究をします。それなりに負荷のかかるカリキュラムなので、自ら学びたいという意欲をお持ちの会員が多いですね。
- 坂田
- この活動をアシストが運営する意義はどこにあるのでしょう?
- 西谷
- まず研究課題のテーマが、時代を反映している点。つまりトレンドについて学べること。もちろんITやICTに関わりのあるテーマが多いですが、もっと広範に組織運営や経営視点を養う場にもなっています。また、それらを研究しまとめていく一年間のプロセスで、メンバー間のコミュニケーション能力やプレゼンテーションのスキルも身につきます。
- 坂田
- もはや人材育成の場のような使われ方ですね。
- 宮田
- 僕ら営業も、積極的にご案内しています。いまやどこの企業も人材育成は大きな課題ですから、とても大きな関心を寄せていただいています。
- 西谷
- アシストのプロモーションの場ではありませんので、取扱製品やサービスについて触れないというのもポイントです。
- 岸和田
- 「ソリューション研究会」は1996年に発足ということですから、もう25年以上も続いています。
- 西谷
- 無料でスキルも身につくし、人脈もつくれるので、毎年、若手社員を派遣してくださっているお客様もいらっしゃいますし、リピーターも多いです。「エグゼクティブ交流会」とプロセスは違いますが、「ソリューション研究会」も絆づくりの意味があります。