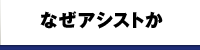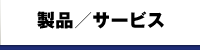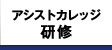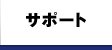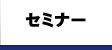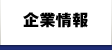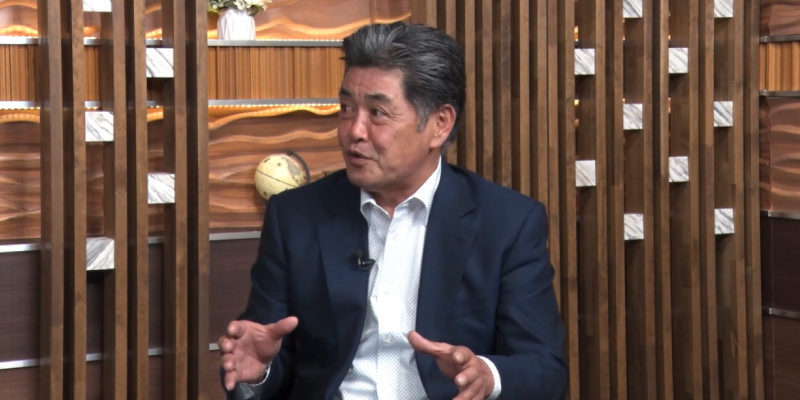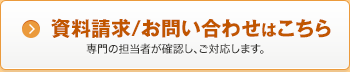常勝軍団ソフトバンクホークスを5度の日本一に導いた名将、工藤公康氏を迎え、巧みなリーダーシップの極意について伺いました。工藤氏の著書『プロ野球の監督は中間管理職である』を基に、ビジネスの場にも通じる組織マネジメント力、「勝たせ続ける」ことの意味、野球やビジネスにおけるデータ分析の課題などをテーマにアシスト社長の大塚辰男と対談しました。
● 監督の仕事とは、チームを「勝たせ続ける」こと
● プロ野球の監督は「中間管理職」である
● 「決める」ではなく「準備する」のが監督の仕事
● 勝ちから慢心が生まれる
● 「循環型」の組織をつくる
● 考える選手を育てる
● 「常勝」で生まれるデメリット
● データを分析するだけで試合に勝てるだろうか
● 最後に
監督の仕事とは、チームを「勝たせ続ける」こと

大塚
工藤さんの著書『プロ野球の監督は中間管理職である』にあった、「監督は勝たせるだけではない。勝たせ続けなければいけない。勝ち続けるチームを作らなければいけない」という一文に、経営者として最も感銘を受けました。どのような経緯からこのように思われたのですか。

工藤氏
最初は西武ライオンズで、勝ち続けることの大切さを広岡監督に教え込まれました。勝ち続けるためには自分自身を、そしてチームを進化させ続けなければなりません。それが、自分の選手人生を長くすることにつながります。ホークスで孫正義オーナーから10連覇できるチームを作るように言われた時にも、ホークスを常勝チームにしたい、そうすれば選手に現役を長く続けさせることができると考えました。
プロ野球の監督は「中間管理職」である

大塚
常勝チームを作る中で、ご自身の立ち位置を「中間管理職」と位置づけられましたね。会社であれば監督は「社長」に他ならないと私は思っていましたが、なぜ「中間管理職」だと思われたのでしょうか。

工藤氏
私も現役時代は監督が一番偉いと思っていたのですが、実際、監督になってみると、今ではほとんどの球団には監督の上にGM(以前は、球団本部長、代表などと呼ばれていた)がいて、GMがいわゆる社長でチームの将来や全体について考えています。
一方、監督は現場を任せられた人間です。選手を見ることが監督の一番重要な仕事ですが、何かをするときには必ず上にお伺いを立てないといけません。自分は一番トップではなく、「野球部門」の部長、つまり「中間管理職」であることに気づいたのです。チームを今後どうしていきたいのか、強くあり続けるためにはどういう選手を育てるべきかを上の人に説明する必要があります。そこからはとにかくちゃんと上に説明してOKをもらってからやっていこうと決めました。

大塚
それは決裁権のようなものが決まっているということですか。

工藤氏
例えば、ドラフトや外国人選手、トレード対象となる選手についての決定権は私にはありませんでした。

大塚
監督が決めているものだと思っていました。ドラフト会議でも監督がくじを引きますね。

工藤氏
監督がくじを引くので獲得する選手を決めているというイメージを持たれたかもしれません。もちろん監督も、希望や意見は伝えていると思いますけれど決定権はないです。監督は現場の選手を導くことに専念し、GMが選手獲得プランを立てて、監督はその報告を受けています。
「決める」ではなく「準備する」のが監督の仕事

大塚
監督の仕事は、決めるのではなくて準備をすることだともおっしゃっていますね。

工藤氏
コーチから「監督どうしますか?」と聞かれることについては、ある程度、事前にシミュレーションをしています。ピッチャーの起用であれば、データを基に自分の案を用意した上でコーチの案とその案にした理由を聞き、自分が納得すればコーチの提案を採用します。打順もデータを基に、1番から9番までの打順を3〜4種類準備していました。コーチが提示した打順が私と違えば、コーチは私の知らないデータを見ていたかもしれませんし、別の考えがあったかもしれません。
このようなやり取りをすることで、各コーチが選手をどう見ているかがわかり、観察力も向上しました。常に準備しておくことで、コーチのやりたいことをより活かしてあげられたと思います。

大塚
会社に置き換えれば、いかに社員が働きやすいように工夫するかということですね。

工藤氏
野球をするのは監督やコーチではなく選手です。選手がやりたいことができる環境を作ってあげられるかによってパフォーマンスも大きく変わってきます。そのために、監督やコーチがいるのだという考えでやってました。
勝ちから慢心が生まれる

大塚
「勝ちから慢心が生まれる」という表現も印象的でした。

工藤氏
そうですね。慢心とは自信と過信が合わさることです。自信を持つのはいいことですが、それが過信に変わってしまうと、練習を怠ることにつながります。30代中盤、後半と年を重ねて老化すれば、パフォーマンスが落ちて怪我をしやすくなります。だから、体を鍛える必要があると伝えますが、自分はまだ大丈夫との過信から訓練を怠れば、翌年怪我をするかもしれません。その時になって監督の言葉を思い出し、気持ちを改めてくれたらいいと思います。選手に慢心や過信をさせずに、意思の疎通をした上で成長を促すことが我々の役割であると思っています。

大塚
チームも選手も現状維持に甘んじたらダメだということですね。

工藤氏
絶対にダメですね。でも、各自がやることについては強制はさせません。なぜやる必要があるか理由を話して、納得してもらった上で、実行してもらいます。自覚してもらうことが一番大切です。
自分がやりたいと思ったことをやって失敗してもらってもいいんです。失敗しても、何が足りなかったのかを自分で考えてもらい、監督やコーチはその時に助言ができればと思います。
打率3割は大打者です。7割は失敗する野球はすごく失敗するスポーツなんです。7割失敗してもよいのではなく、技術を上げてわずかでも成功率を上げていく必要があります。その自覚を促すために、コミュニケーションをとり続けています。
「循環型」の組織をつくる

大塚
一軍のコーチを、二軍、三軍に行かせ、また一軍に戻すというようなローテーションをされていたとのことですが、その発想はどこから来たのですか。

工藤氏
選手を見るためです。一軍コーチが二軍に来れば、今、一軍でどういう選手が必要とされているのかを直接聞くことができます。そうすると、自分たちが身につけなければならないスキルがわかります。二軍では走攻守すべてを鍛えていきますが、実は一軍では一芸が求められています。
周東選手を例に上げると、彼はとにかく俊足でした。バッティングも得意ではなく、守備は外野の一角しかできない。その選手を一軍に上げて、どうなったかというと、代走に出せばセカンドくらいのヒットでもホームに帰ってこれました。それから彼はバッティングをよくしたいと思って自ら皆より早く出てバッティング練習をしたり、守備も工夫するようするようになっていきました。
彼を見て、一つの成功体験がいかに大切かを学ぶことができました。大事なのはモチベーションを高く持ちながら必要とされること、「君はこういうところで必要なんだ」と伝え続けることだと思います。
考える選手を育てる

大塚
まさに育成の部分ですね。コーチ陣が、一軍の経験を二軍、三軍の選手に伝え、選手はもちろんですけれども、コーチも二軍、三軍で教えることで成長し、一軍に戻ってさらに変化を起こしているということですね。

工藤氏
一軍ではマネジメントが中心です。今いるメンバーでどうやって戦っていけば勝てるのかを考えます。二軍や三軍は育成で、選手に技術やスキルを身につけさせるのが仕事です。役割が異なります。循環型の組織では、選手だけではなく、コーチにも成長してもらいたいという意図があります。育成ができるコーチにマネジメントをやってもらったり、その逆もしかりです。
監督の経歴を見ると、例えば一軍・二軍のコーチを経験した上で、二軍の監督を何年かやり、一軍の監督になった人が優勝しているようです。ホークスの小久保監督や巨人の阿部監督がそうですし、三連覇を達成したオリックスの中嶋監督も二軍の監督経験者です。ヤクルトの髙津監督も一軍のピッチングコーチをやって、その後二軍の監督を2年やって、一軍の監督になって連覇してます。育成とマネジメントの両方ができるようになると、いいチームが作れるのではないかと思います。
アシストはどうですか。

大塚
アシストだけではなく、今、社員の育成は多くの企業の経営課題ですね。DX人材の育成や、AIを使って自身の生産性や発想力を上げることができる人材の育成を求める企業が多いようです。ただ、マネジメントと育成を行ったり来たりしながらコーチ、ビジネスでいうと中間管理職を育成するという発想はあまり聞きません。

工藤氏
以前は、一軍は一軍、二軍は二軍というように分かれていましたが、今は三軍も含めて(ホークスは四軍まで)情報を共有しています。この共有ができていないと育成はうまくいきません。
「常勝」で生まれるデメリット

大塚
常勝で生まれるデメリット、勝ち続けることのデメリットについて教えてください。

工藤氏
日本一になったらその翌日から来年に向けてスタートして欲しいのですが、選手は勝つと浮かれるというか、ちょっとした油断が生まれます。
選手全員が集まる機会を狙って、「オフは体を鍛えるためにある」と伝えてみるものの、なかなかそうした雰囲気にはなりません。優勝した翌年は他球団が攻略法を考えてくるため、心技体すべてにおいてレベルアップしてなければ勝てなくなると選手には伝えます。しかし、それを実感させるのは難しく、練習不足により、普段はしないような怪我をキャンプ初日にしたりします。日本一になるために戦っているわけですが、勝ったからこそこうしたデメリットに直面することがあります。
大塚社長はいかがですか。

大塚
業績を重ねてきますと、心配が一番高まるのが10月ぐらいです。その年の決算が見えてくるのがその頃ですし、加えて来年1月からの売上見込みや、次年度の計画は大丈夫なのかという不安もあります。もし業績が下がったらどうしよう、社員に給料を払えなくなったらどうしようなど色々考えます。次年度の計画を立ててから2ヵ月でようやくその内容に腹落ちして、その不安が解消されてきます。

工藤氏
社長として自分が責任を取るという覚悟は最初からありましたか。

大塚
社長をやる時点で、業績は上げ続けていかなければいけないとは思っていましたが、大きく上げ続けていく必要はないと思っています。弊社のお客様への約束は「めげない、逃げない、あまり儲けない」ですので、売上目標も、緩やかに上げています。中には物足りないと思っている営業社員もいるかもしれませんが、チームの中で調整して個人の目標に落とし込んでもらっています。
技術職の社員向けにはキャリア充実プログラムというものを用意して、次はこういうことができるようになろう、などの少し高い目標を立ててもらい、その実現に向けて頑張ってもらっています。
データを分析するだけで試合に勝てるだろうか

大塚
これからの活動方針をデータを基に決めていらっしゃるということですが、それについて教えてください。

工藤氏
一人一人をどう見るかが原点です。例えば、ピッチャーの育成には、Trackmanという機械を使っています。初速度、終速度、回転数、回転軸、縦横の変化量などを測定する機械ですが、数値だけ見ていたのでは変化球の曲がりが良かったねで終わってしまいます。ピッチャーの成果は本人のコンディションに大きく左右されることはわかっています。良い時にはどの数値が良くて、悪い時にはどの数値が悪いのか見極めようとしました。
その時、選手はどう感じているのか、コーチや監督にはどう見えているのかを共有し、その時どんな練習をしたのかもデータ化しました。コンディションを維持したまま1シーズン通して戦うことができる人、途中で怪我をしてしまう人と色々ですが、データを見ると、何が違うかがわかるようになりました。
監督やコーチは、このデータを使って選手を見る目を養っています。

大塚
リアルタイムでベンチに持ち込めないんですか。

工藤氏
はい、現状は。データはいったんサーバに入って、翌日でないと見ることができません。コーチたちには、ピッチング中の投手の変化を見る目を養ってもらっています。ピンチだから交代させるのではなく、選手の調子を見て、調子が下がっていないようであれば続投させますし、もうここが体力的な限界だなと思ったらゼロ点で抑えていても変えます。それ以上投げさせたら怪我をするおそれがあるからです。
データや科学というのは、パフォーマンスや成績の向上に必要なことではあるのですが、パフォーマンスを上げるにはどういうトレーニングをすればよいかの方法論も必要です。間違えたやり方をすれば怪我につながります。これをちゃんとできる人が、野球界にはまだ少ないのが現状です。
チームにはデータを分析する専門家のアナライザーがいます。アナライザーは、監督やコーチから言われたデータを出すだけで、残念ながら、このデータをこう活用したら勝てますよと提案するシステムにはまだなっていません。また、アナライザーが出した分析をコーチや監督が理解できないと、せっかくのデータを活かすことができません。互いにデータを生かす知識を持っているか持ってないかでずいぶん変わってしまいます。

大塚
ビジネスの世界でも、様々な業種で以前からたくさんのデータが取得されていますが、あまり活用されていないという話をよく聞きます。データは保存しておくだけではゴミですが、技術の進歩とともにそれを宝の山に変えられる可能性が出てきて、各社それに一生懸命取り組まれています。弊社はそのデータ基盤の整備などを支援させていただいています。
最後に

工藤氏
私が監督として7年間やってきた中で、足りないところ、なかなかうまくいかないところを自分なりに考え、コーチや球団とも相談しながら、何とか強いチームを作ろうと取り組んできました。選手は常に不安を抱えています。自分は使ってもらえるんだろうか、一軍で活躍できるんだろうか、長く野球ができるんだろうかと。その不安を一つでも取り除いてあげたいという一心で頑張ってきたつもりです。十分とは言えなかったかもしれませんが、少しでも今回の話が企業の皆さんのお役に立てばと思います。野球界も変わっていかなくてはいけません。皆さんも工夫されていると思います。共に頑張っていきましょう。

大塚
貴重なお話をありがとうございました。