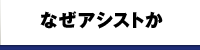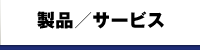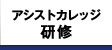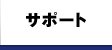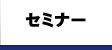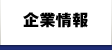RPAでもRBAでもない!? ビジネスゴールを見据えた自動化とは?
2021.12.10

|
|---|
<執筆者> 佐野 弘明 Sano Hiroaki
システム基盤技術本部 技術3部 部長
2003年新卒で入社以来、運用分野を中心に担当。
2年間の東京勤務を経て、以降は西日本のお客様に対する提案/構築支援に従事。
近年はセミナーやユーザー会等、各種イベントの企画/運営も担当。
週末は4歳児と1歳児の育成に従事。
「RPA」「RBA」とは
「RPA(Robotic Process Automation)」がエンタープライズIT分野で注目されて久しいですが、改めて「働き方改革」や「生産性向上」といった社会的テーマを実現する手段として関心が高まっています。
また、RPAと似た「RBA(Run Book Automation)」もシステム運用の現場では注目を集めています。
そこで、まずは「RPAとRBAの違い」を簡単に整理してみましょう。
「RPA」「RBA」とは
|
|
|
|
|
|
違いを端的にお伝えすると、RPAはGUI操作を、RBAはCUI操作を自動化する仕組みになります。
「RPA」「RBA」の活用事例
では、具体的にどういう業務で活用できるのでしょうか?
RPAツールは「このサイトのこのボタンをクリックしないと動かせない」ような操作をする時に便利です。
アシストの人事部門でもRPAツールを導入していますが、勤怠システムからデータを抽出→Excelで手動加工する部分を自動化しています。
Excelの加工自体はマクロで可能ですが、「勤怠システムからデータを抽出してくる」作業自体は、勤怠システムの仕様上、手動で実施するしかなく、様々なパターンでデータ抽出をするために膨大な時間がかかっていました。
そこで、RPAツールを導入したところ、半年で370時間もの工数削減に成功しています。
RPAツール導入事例

|
|---|
事例① 株式会社アシスト
導入から半年で370時間の業務時間削減!
RPAツールUFT導入により、新しい価値を創造する「攻めの人事」を実現
https://www.ashisuto.co.jp/case/industry/information/uft_ashisuto_20191001a.pdf
\
UFT One
を導入しました /
旧製品名は、Unified Functional Testing(UFT)。
もともと機能テストツールとして開発された製品ですが、「画面を記録し処理を実行する」という機能自体はRPAと同じです。
製品の品質としてもRPAとして十分利用できるものであるため、アシストではRPAツールとしておすすめしています。
RBAツールは、「コマンド実行作業の自動化」や「ITシステムの運用業務」に有効です。
RBAツールを導入することで、工程が多く複雑な定型作業の時間を80%削減できた事例もあります。
また、障害の切り分けや各種メンテナンス作業などで利用することで、工数削減だけでなく、作業ミスの軽減にも役立ちます。
RBAツール導入事例

|
|---|
事例② 京セラコミュニケーションシステム株式会社
自動化で作業時間を80%削減!ルーチンワークからの解放による業務改善の加速
https://www.ashisuto.co.jp/case/industry/information/KCCS_OO_2018.html
\
Operations Orchestration
を導入しました /
運用担当者のオペレーションを自動化する製品です。
8,000を超えるテンプレートと使いやすいGUIで、容易に自動化フローを作成することができます。
事例③ 鈴与システムテクノロジー株式会社
サーバ運用の品質強化と工数削減 二兎追う者を救った自動化とは
https://www.ashisuto.co.jp/seminar/report/detail/af2018_ssj1.html#6
\
JP1/Automatic Operation
を導入しました /
仮想サーバのデプロイ、障害の一時切り分け、各種メンテナンス業務など、様々な運用シーンで幅広く活用いただけます。
このように、「RPA」「RBA」は様々な業務で活用できます。
2020年以降のコロナ禍においては、テレワークとあわせて事業継続する手段としても「業務自動化」が注目されており、各企業において「RPA」「RBA」の検討/導入が進められています。
中でも「RPA」については、年商50億円以上の企業の導入率が4割に近づいており※、導入フェーズから活用フェーズに移っている状況とも言えます。
今後、ますます「業務自動化」が進むといえるでしょう。
※出典:RPA導入企業が活用を本格化、AI-OCR導入も約2割
https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=474
(2021年12月6日時点の情報)
RPAやRBAでビジネスゴールを達成するための「SRE」
では、「RPA」「RBA」の普及や活用で、本来のビジネスゴール「顧客への価値提供」が達成できるでしょうか?
「顧客への価値提供」をゴールに見据え、ビジネスの信頼性を維持/向上するためのITと捉えると、自動化による現場の省力化/効率化/コスト削減だけでは不十分です。
● DXの本質である「テクノロジーの力で新たな価値を生み出すこと」
● DXを支えるIT運用の「サービスをリリース/改善するスピード/確実性」
が必要になってくるでしょう。
そこでご紹介したいのが
「SRE」
という考え方です。
SREとは何か、以下のページで分かりやすく解説されていましたので、引用させていただきます。
SRE(サイト信頼性エンジニアリング)とは
“ サイト信頼性エンジニアリング (SRE) は、IT運用に対するソフトウェア・エンジニアリングのアプローチです。
SREチームはソフトウェアをツールとして使用してシステムを管理し、問題を解決し、運用タスクを自動化します。
SREは、これまで運用チームが多くの場合手作業で実行していたタスクを、エンジニアや運用チームに担当させ、
ソフトウェアと自動化を使用することで、問題を解決して本番システムを管理します。”
“ DevOpsと同様、SREではチームの文化と関係が重視されます。
SREもDevOps も、開発チームと運用チームの溝をなくしてサービスを迅速に提供する働きをします。
アプリケーション開発ライフサイクルの短縮、サービス品質と信頼性の向上、開発された各アプリケーションに
IT部門が費やす時間の削減といったメリットは、DevOpsとSREの両方を実践することで達成できます。”
出典:SRE (サイト信頼性エンジニアリング) とは
https://www.redhat.com/ja/topics/devops/what-is-sre
(2021年12月6日時点の情報)
要するに、
SREの考え方を取り入れ、運用タスクを自動化することで、拡張性/信頼性が高いシステムをスピーディにリリース/改善しましょう!
ということです。
「顧客への価値提供」のためには、サービスをリリース/改善する「スピード」と「確実性」が重要であることを踏まえると、SREの考え方とマッチしており、IT運用の一つの解といえるのではないでしょうか。
弊社では、今春から構成管理自動化ツール「Red Hat Ansible Automation Platform」の販売を開始し、SREの一端を担おうと考えています。
学習コストが低く、自動化できる対象が多いところが特長です。
もし興味があれば、以下サイトをチェックしてみてください。
構成管理自動化ツール「Red Hat Ansible Automation Platform」
構成管理自動化のデファクトスタンダード
インフラ構築やメンテナンスを自動化し、自動化のノウハウや仕組みを標準化します。
https://www.ashisuto.co.jp/product/category/system-management/ansible/
\ こんな自動化に向いてます! /
・サーバ管理(パスワード変更・ログ取得・OS設定)
・データベース管理(バックアップ・リストア・ログ取得)
・ネットワーク管理(config設定/取得/管理)
\ こんな自動化には向いていません /
・条件分岐のルール化が難しい
・判断基準が毎回変わる
さいごに
自動化といえば「省力化/効率化/コスト削減」が主な目的だと考えられがちですが、ビジネスの信頼性を維持/向上させるためには「スピード」と「確実性」が必要です。
そのための手段としても「自動化」を検討してみるのはいかがでしょうか?
「こんな業務があるけど、自動化できるのかな?」「こんな業務を自動化したいけど、どういうツールを使ったらいいの?」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本ページの内容やアシスト西日本について何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。